連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_banar.png)
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第24回目です。今回は、偉大で著名な作家の作品だからこその、謎に包まれた出版までの運命にまつわるエピソードを紹介します。担当編集者ならではの感性で捉えた、作家との縁、作品の誕生について語ります。
松本清張さんの長篇小説『熱い絹』は、私にとって、小説の内容にふさわしいような、ミステリアスな運命をたどった小説だと言っていい。
『熱い絹』は、「小説現代」に1972年2月号から連載をはじめ、1974年12月号に休載されたのを最後に、そのまま煙のように有耶無耶になってしまう。それが出版化されることがないのは当然だ。
『熱い絹』は、9年後の1983年から翌年の12月まで報知新聞紙上に、構想を変えて連載されて、完結した。1985年に、「小説現代」の版元である講談社から単行本『熱い絹』として刊行されるのである。
「小説現代」版は、1回1回の枚数も少ない上、23回の連載中、14回もの休載がある。
1972 年7月号に、早くもはじめての休載があり、編集後記に「作者病気のため、今月号に限り休載いたします」と書かれている。
その後、「作者都合により」とか「海外取材中のため」とか「外国旅行のため」あるいは「作者病気のため」などという理由が書かれた14回の休載が飛び飛びにあったのち、1974 年12 月号には、あるべき連載が姿を消して、編集後記などにも、この号の休載についてのなんの断りもないまま、以後、『熱い絹』の連載は作者からも編集部からも忘れられた存在になってしまうのである。
「小説現代」編集部では、普通、作家の担当は部員に任されていて、編集長が担当することはなかった。ただひとり、松本清張さんは編集長が直接担当していたから、特別な作家だったのだろう。
もちろん編集長の手足となって動く編集者が必要だったので、私がその役を仰せつかっていた。『熱い絹』の連載が、1972年2月号から始まっているから、担当の補佐と言われたのは、1971年頃だったろうか、私は、「小説現代」編集部に配属になって3年目、まだ駆け出しの文芸編集者だった。私は清張さんの、いわば担当補佐になっただけでも、ちょっと震えたものだ。
1972年というと、清張さんは、芥川賞を受賞した『或る「小倉日記」伝』はもちろんのこと、いまでも人気のある『点と線』『砂の器』『ゼロの焦点』などの推理小説のほか、『日本の黒い霧』や『昭和史発掘』などのノンフィクション作品など、主要な作品を書き上げていた。
もちろん、700点のほどの著作がある清張さんのこと、1970年代後半から1980年代にかけても、『黒革の手帖』(1978年から1980年にかけて「週刊新潮」誌に連載)や『空の城』(1978年に「文藝春秋」誌に連載したドキュメント・ノベル)や『詩城の旅びと』(1988年から1989年にかけて月刊「ウィークス」に連載)などの多くの作品を書いてはいるが、松本清張と言えば、押しも押されもせぬ巨匠だった。
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』 写真](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_image_.png)
『熱い絹』の連載がはじまる号の目次の惹句にも、「巨匠の新連載! 国際謀略推理小説 マレーシアの避暑地に突然消えた〈タイ・シルク王〉の謎!」と書かれているのである。
ちなみに、タイ・シルク王と呼ばれた、CIAと深い関係のあるジム・トンプソンが、密林が密室を作っている避暑地から忽然と姿を消したことは実話である。そして、その失踪の動機は不明だし、ジム・トンプソンは行方不明になったままだし、謎は深まるばかりであった。
清張さんの『熱い絹』は、そのことを核にして、タイの少数民族の中に溶け込んでいる元日本兵、タイのさまざまな美術品、ベトナム戦争とアメリカ軍、マレーの共産ゲリラなど、いかにも清張好みの素材をふんだんに使って書かれている。
『熱い絹』連載の第1回目のゲラを受け取ることと、これからお手伝いしますと挨拶も兼ねてうかがったとき、通された応接間には甲冑が置いてあるのが目についた。このときも、私はちょっと震えたものだ。
ゴトゴトと足音がして、2階から清張さんが降りてきて、甲冑の脇に、こちら向きに座った。
「ああ、ご苦労さん」
少し甲高い声でそう言った。それから、
「これゲラ。編集長によろしく言ってね」
と、ことづけを告げた。
「はい」
「ところで、駅伝ってあるよね」
「駅伝って、マラソンの……」
清張さんとスポーツは結びつかないので、陸上競技の駅伝という言葉が飛び出したので驚いたのだ。
「うん。その駅伝。いまはエキデンと言って世界的な競技になっているんだ」
「そうらしいですね」
「で、小説の中で、ヨーロッパの都市の名前をただ列挙して書いても、読者にはなかなか覚えてもらえないんだ」
「そうでしょうね」
「つまり読んでもらえない」
「ええ」
「でね、エキデンを開催することにして、エキデンのコースで、ヨーロッパの名前を並べたら覚えやすいんだよ」
「それはそうですね」
「そう思うかい」
「もちろんです」
「と、いうことは、読者が小説に入りやすいんだ」
「とてもいいアイディアですね」
そのことを、新米の編集者相手に、熱心に語る清張さんを目の前にして、松本清張作品がたくさん読まれる理由がいくつか分かったような気がした。清張さんは、自分の小説に読者をどう惹きつけるかと腐心していることと、なににもまして、清張さんは、子どもがおもちゃを与えられたみたいに、小説が好きでたまらないんだなと思ったのだ。
清張さんは、自分のアイディアを、私のような若い編集者が面白がっていることにご満悦だった。
私は私で、清張さんが単なる「巨匠」ではなく、小説の話をし出したら、相手が誰であろうと、熱心に語る小説家なんだと思い、いくらか気が楽になっていた。
この「エキデン」のアイディアは、『詩城の旅びと』という作品の冒頭に使われている。
新聞社の企画部長の木村信夫に、南仏・プロヴァンスのエキデン企画を提案する一通の手紙が届く。マルセイユから、エクス・アン・プロヴァンス、アヴィニョン、サンレミを通ってアルルまでの駅伝プランだ。
この企画書を読みながら、企画部長は、同時に書かれている、ゴッホやセザンヌなどの美術論に時間を費やす。こうして、読者は知らずのうちに、プロヴァンスの都市に慣れ親しみ、小説の世界にのめり込んでいくわけだ。
私は、清張さんに、『熱い絹』の冒頭に書かれている、タイのシルク王と呼ばれているジム・トンプソンの失踪のことが書かれている新聞の記事を預けられた。
大富豪になったジム・トンプソン(小説ではジェームス・ウィルバーとなっている)が、マレーシアのキャメロン・ハイランドの知人の別荘「月光莊」から謎の失踪を遂げたことを記事にした、当時の、「シンガポール・ガゼット」紙などの新聞の切り抜きである。
記事はすべて英語で書かれていた。
「君はICUを出たんだろ。これを訳してくれよ」
編集長はあっさりと言った。
私が卒業したICUの卒業生は英語が堪能な者が多いのは確かであった。だが、私は卑下自慢するわけではないが、ICUを出たには出たが、英語の方はからっきしだった。
だが、ことここに至っては仕方ない。辞書を片手に、新聞の記事をいくつか翻訳して、清張さんに届けた。
次に伺って、渡された原稿を見て、私はびっくりした。私が訳した新聞の記事の、間違いと言い回しの怪しげなところは万年筆で直してあったが、そっくりそのまま、原稿として活かされていたのだ。
その部分は連載の3回目の4ページほどではあるが、1972年4月号に掲載されている。
私は、小さな部分だが、巨匠・松本清張の代筆をしたわけである。
清張さんから編集長に電話があった。
次の回の原稿を書くのに、タイのバンコクの博物館のパンフレットが必要だが、家を探してみても見つからないので、至急、それを取ってきてほしいということだった。
次回の原稿というと、今日明日にもバンコクに行って、トンボ帰りで帰ってこなくてはならないほど切羽詰まっていた。
編集長が私をじっと見ていた。またもや、ICU卒の力で何とかならないかという視線を感じた。いくら清張さんの要請でも、部員にバンコク往復の出張をさせることは、時間的にも、経済的にも(こちらの理由が主だったが)、やりたくないのだ。
私は、ICUの同期生のひとりが、日航のパイロットになっていることを思い出していた。
「そいつに頼んだら、バンコク便に乗っている乗務員にそのパンフレットを取ってきてもらえるかもしれません」
と、言ってみた。
「それだ」
編集長は叫んだ。
私は、日航に電話を入れて、運よく日本にいてくれた友人に、事情を説明して、難題解決を頼んだ。
友人から、手に入ったから取りに来いと電話があったのは、それから2日後だったと思う。さすがは天下のJALだ。
パンフレットは、手にしてみると、カラーではあったが、とても薄いものだった。
すぐさま、編集長は、入手経過は秘密にしたまま、
「パンフレットを手に入れたので届けます」
という電話を清張さんに入れた。
その電話の中で、もう一度探してみたら、見つかったので届けなくて結構と言われたようだ。
私はあまりのことに、呆気に取られたが、編集長は、
「作家は愛情乞食と言ってね、いつも編集者の愛情を確かめたいんだよ。清張さんほどの巨匠になってもそうなんだな」
と深く頷いていた。
その編集長が、北九州市にある「松本清張記念館」が発行している「松本清張研究」という冊子の「第九号」に、「《天然の密室》と松本清張さん」という随筆を書いている。
「小説現代」では未完に終わって、報知新聞に連載する『熱い絹』のための取材同行記である。 清張さんは、1978年に至って、作品の再開を思い立って、もう一度、マレーシアやバンコクなどに行くことになったのである。
1983年から、報知新聞で連載をする作品のため、講談社の編集者が取材に同行するというのも不思議な話だが、たぶん、単行本は講談社が出していいということになったのだと思う。
1978年には、私は、「群像」編集部に異動していて、翌年には村上春樹さんの新人賞受賞などがあって多忙をきわめていて、この取材同行のことは知らなかった。
清張さんと野村芳太郎監督、脚本家など、編集長を含めて7人の一行だったそうだ。
7泊8日の旅で、1泊ずつ宿泊した場所を挙げてみると、強行軍だったことがわかる。
シンガポール→クアラルンプール→カメロン・ハイランド→ペナン市内→ペナン島ビーチ→バンコク→香港→帰国。
清張さんのタフなことに驚かされる。
同じ「松本清張研究」の号に、京都大学教授の玉田芳史氏の、「タイと太平洋戦争─『熱い絹』の背景─」という小論文が掲載されている。
興味深いのは、玉田氏が、太平洋戦争のマレー作戦のことに触れていることだ。
イギリス軍に屈辱的な敗北を味わわせたこの作戦の参謀が辻政信氏であり、戦後は衆議院議員から参議院議員になったこの人物は、単身、ラオスを目指したことは判明しているが、その後、行方不明になり、謎の失踪として話題になった。
『熱い絹』の中に登場する旧日本軍人が、この辻政信氏を彷彿とさせるのも、清張さんが意識したことだ。
『熱い絹』は、1983年から報知新聞で連載がはじまり、1984年に完結、1985年に講談社から単行本になる。
なぜ、「小説現代」では、執筆が難渋し、結局未完に終わったのだろうか。
「小説現代」の連載の第5回の小見出しに「サマーセット・モームの後輩」とあり、第7回には
「サマーセット・モームからの鼓舞」とあって、モームの『作家の手帖』からの、少し長めの引用がなされている。
サマーセット・モームは作家であるが、同時に諜報部員として活動した人でもある。
たとえば、モームの『月と六ペンス』という小説は、タヒチに住み込んだゴーギャンをモデルにして書かれている。モームの芸術への造詣の深さや、小説がスリリングな展開に支えられている点や、文体の分かり易さなど、清張さんは自分の小説作法にも似たものがあると感じたはずだ。
清張さんは、そのモームの文学感を、『熱い絹』に取り込もうとしたのに、まだそのテーマが熟しきっていなかったのか、あるいは、それは『熱い絹』には不必要だと思えてきたのだろうか。
ともかく、報知新聞版では、モームのことはバッサリと削られている。
なるほど、『熱い絹』には、モームのことは無くとも、充分なほどたくさんの素材が詰め込まれているのだ。
「小説現代」版が未完になっていった理由を、私は今でも、こうしてさまざま探ってみたりしている。
そうして、これは無いものねだりになってしまうが、私は清張さんに、小説家にして諜報機関に従事していたサマーセット・モームが主人公となるような小説を書いて欲しかったと思っているのである。
だいぶあとのことになるが、私がバンコクに旅行したとき、「ジム・トンプソンのタイ・シルク」の店に寄ってみた。観光客で混んでいたが、ここで買ったシルクのクッション・カバーは、いまでも私の家の居間のソファに置かれている。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

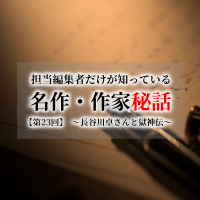
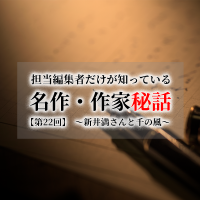
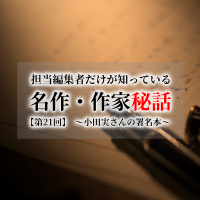
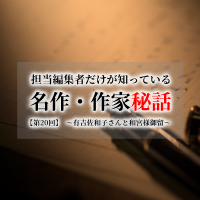
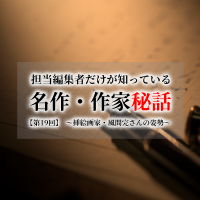
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_banar-600x315.png)