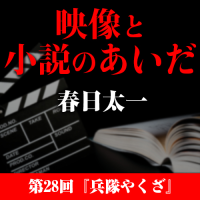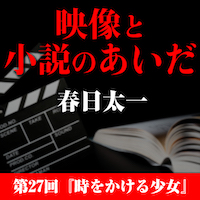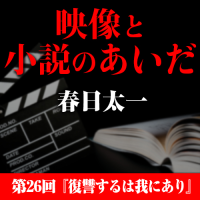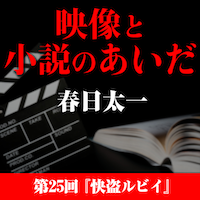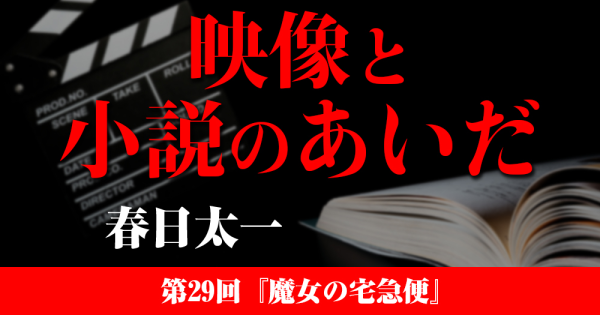連載第29回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
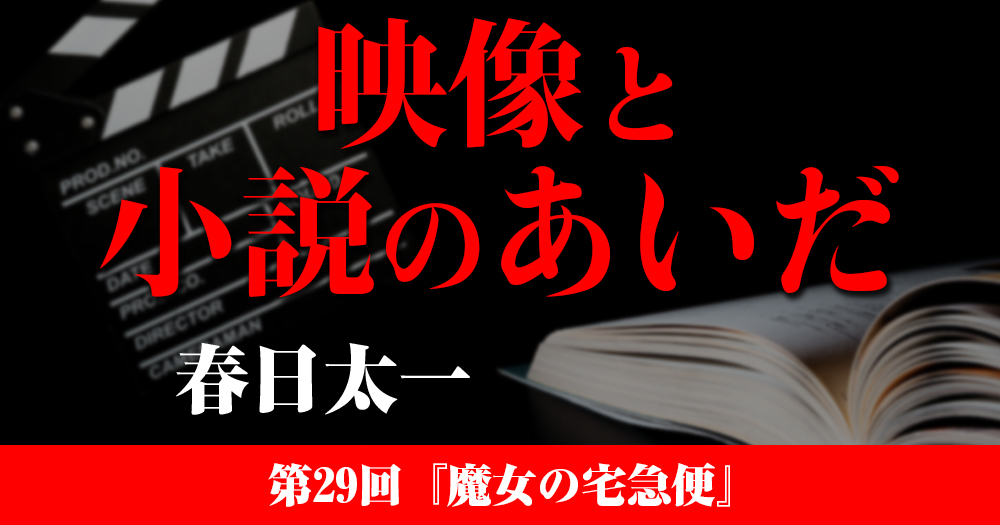
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『魔女の宅急便』
(1989年/原作:角野栄子/脚色・監督:宮崎駿/制作:スタジオジブリ)
「少し自信がついたみたい。落ち込むこともあるけれど私、この町が好きです。」
魔女の血を引く女性は13歳になると、修行のためどこかしら魔女のいない町に住み、一人で生活しなければならなかった。母を魔女に持つキキも13歳になった際に親元を離れ、愛猫のジジとともに海辺の大きな街・コリコで暮らすようになる。ホウキに乗って飛ぶ魔法しか使えないキキは、パン屋に居候しながら自身の特技を活かして運送業を営むことに。そして、荷物の運搬やその際の人々との触れ合いを通じて成長していく――。
そんな角野栄子の児童文学は全6巻が刊行され、キキがやがて結婚し家庭を持つまでの大河ストーリーになっている。アニメ映画版はそのうちの第1巻を中心に第2巻の一部も交えて映像化、13歳のキキに絞って物語は展開する。
このアニメ、基本的な設定は原作と変わらないのだが、受ける印象は大きく異なるものになっている。
その要因の一つに挙げられるのは、キキの性格設定が変更されている点だ。どちらも元気な少女であることには違いはない。ただ原作は、友だちの誕生日にドレスを着る、レースの下着を着る、旅立つ前からカラフルな服を求めたりスカートの丈を短くするよう頼んだり――といった具合に、最初からどこかマセたところがある。また、遠慮なく自分の生き方を貫きたいという意思も持っている。そうした自我が既に芽生えつつある原作に対して、映画のキキはとにかく無邪気で快活。まだ子どもっぽい雰囲気を強く残した状況で旅立っている。「相変わらず下手」と母に言われるほどホウキの操縦は上手くなく(原作ではそうした言及はない)、人間としても魔女としても未成熟さが強調されていた。
そこは、コリコで暮らすことになる経緯にも表れている。原作では、空を飛んでいる際に、その光景を見初めて自身の意思で選んでいる。それに対して映画は、雷雨に打たれて落下し貨物列車で雨宿りしていたところを電車が動き出し、そのまま街に着いて、結果としてそこが気に入る――という流れになっており、偶発的だった。
こうした原作と映画でのキキの設定の違いを最も象徴しているのが、同年代の少年「トンボ」との関係性だ。ここの描き方は両者で全く異なる。
トンボが飛行クラブに参加しているという設定は同じなのだが、原作のトンボは魔女のホウキの研究をしているのに対し、映画では自身で飛行できる装置を開発している。そのことが、出会いも関係性も違うものにしていた。
原作のトンボはキキが海辺で海水浴をしている間にホウキを盗む。自身で試すことで、魔女がどのように飛ぶかを知りたいからだ。そのためにキキは不慣れなホウキで飛ばざるをえなくなり、ピンチに陥る。それが二人の出会いだった。そこから二人は仲良くなっていくのだが、「女の子っていう気がしないもんな。なんでも話せるし」というトンボの無神経な言葉にキキがイラついたりするなど、無邪気なトンボに対してキキはお姉さん的な立ち位置で描かれている。
それに対して映画での出会いは、街にやってきたキキが警察官から職務質問を受けているところをトンボが救うというもの。さらにその後も、トンボがパーティに誘ったり、落ち込んだキキを飛行自転車の後ろに乗せて元気を出してあげたり――と、トンボの方がキキをリードしている感がある。キキはそんなトンボにつれない態度をとったりと直情的なところがあり、やはりここでも子どもっぽいリアクションが目立つ。
その一方で、映画のキキは原作に比べてどこか暗い陰がある。
その要因としては、一つには世界観が大きく作用している。映画は自動車、列車、飛行機、テレビなど、近現代文明が日常に根差している様が頻繁に登場する。原作にはそれらはない。また、街にやってきたキキが警察やホテルのフロントで身分証の提示を求められたりするなど、「現代的システムにあっては魔女が存在しにくい」という点が序盤から強調されている。その結果、キキが時代から取り残された存在であることが浮き彫りになっていた。原作でも当初は街で受け入れられないのだが、それは魔女への偏見によるもので、「面倒はごめん」という態度で敬遠されているに過ぎない。
そうした状況に置かれた映画のキキにとって特にキツイのは、同年代の女子との対比だ。華やかな服を着た同年代の女子たちの姿や、オートバイでデートに出かける若い男女と、魔女として地味な格好をするしかない自分を見比べる度に暗い気分になってしまう。つまり、同年代の女子に対して強いコンプレックスを抱いているのである。
しかも、人命を助けて英雄となったことで街の人々に受け入れられる――という原作では序盤に出てくる展開が終盤に回されているという構成の変更がある上に、原作ではキキ一筋だったトンボすら同年代の女子たちとオープンカーで遊び回る設定になっており、キキの孤独さは話が進行するにつれて一段と強まっていくのだ。そして、それに追い打ちをかけるように、原作ではずっと一緒で言葉も通じ合えた愛猫のジジも異性との恋に落ちたことでキキと別行動をすることが多くなり、ついには言葉も通じ合えなくなる。
キキの暗さの決定打となるのが後半、ニシンとカボチャの包み焼きを届けるシークエンスだ。これも原作にはないオリジナルの展開なのだが、キキが老婆の頼みで一生懸命に焼いて雨の中を必死に孫娘に届けるも、その孫娘に迷惑がられてしまう。挙句にその孫娘は派手なパーティ服を着ていた。自分の仕事に自信とモチベーションを無くし、コンプレックスも抉られ、キキは一気に落ち込む。熱で倒れたのもあいまって、ネガティブ志向に囚われていった――。
「素直で明るいキキはどこかに行っちゃったみたい」
そうつぶやきながら、暗い屋根裏部屋で一人食事をするキキ。ジジと話ができなくなったことに気づいたのは、この時だ。魔法が弱くなったことに気づいたキキはホウキで飛ぶこともできなくなり、練習中にホウキを折ってしまう。原作でも似たように、自身の仕事にキキが疑問を抱くようになり、ホウキを折る展開はある。だが、原作は街に完全に馴染んだ第二巻のエピソードだったのに対し、映画はまだ街で浮いた存在でいる段階。それだけに、キキの追いつめられ方はより容赦ないものに映っていた。
本作が見事なのは、こうした変更が全て、終盤に展開される映画オリジナルのクライマックスにおいて伏線として効いてくることだ。
街に不時着した飛行船が突風に煽られ、空中で制御不能になってしまう。それを止めようとしたトンボも、引っ張られてもろとも空中に上がる。ロープにかろうじて捕まるも、力の限界を迎えようとしていた。この時、キキがトンボを救うため一念発起。掃除のオジサンからデッキブラシを借りると、それに乗って浮遊。不安定な操縦ながらも、命からがらトンボを救出するのだった。
それまでの強い落ち込みの描写は、その反動としてキキの復活劇を大いに盛り上げる効果をもたらした。また、それまでトンボよりも子どもじみていたがキキという設定だったからこそ、そんなキキが救うという展開が彼と対等に並んだことを示すことで、ドラマチックな感動を作り出す。原作では序盤にあった「不馴れなホウキでの人命救助」をトンボ相手に変更した上で物語のクライマックスに据えたために、それまでの全ての脚色がここで「キキの成長」を浮き彫りにするための仕掛けとして収斂されているのだ。巧みな構成である。
もちろん、ラストも大きく異なる。
原作では一時的に里帰りするキキに、トンボが手紙を渡す。そこには、彼のほのかな恋心が綴られていた。キキもまた、トンボから「女の子」と認識してもらえたことに喜ぶ。そんな思春期ならではの淡い恋愛感情を匂わせて、物語は終わる。
それに対して映画は、トンボだけでなく、同年代の女子たちも交えた中で心から楽しげに遊ぶキキの姿とともに幕を閉じる。つまり、コンプレックスの超克という形で、彼女の成長が描かれているのである。
そして、故郷の両親にキキが送った手紙の締めくくりが、冒頭に挙げたセリフだ。一人の少女が自立へと足を踏み出すという点に物語の焦点が絞り込まれていることが、ここでもよく伝わってくる。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。