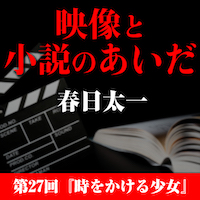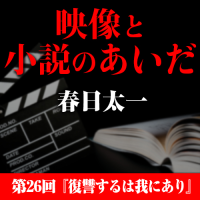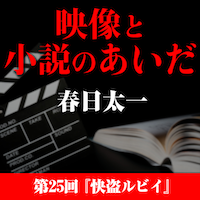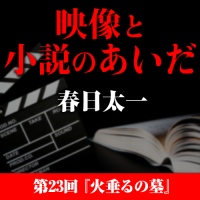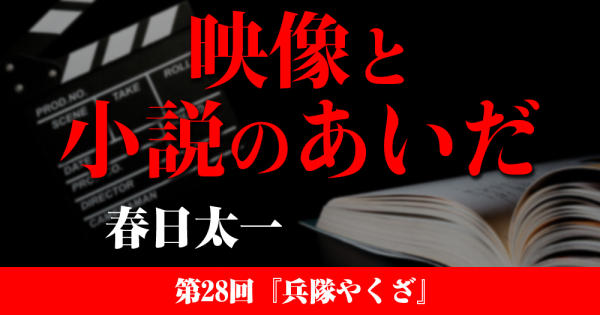連載第28回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
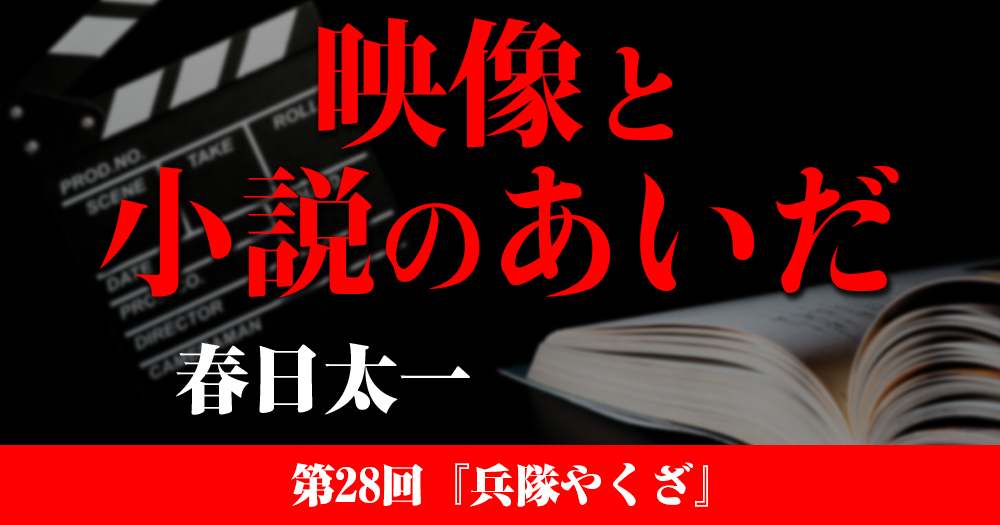
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『兵隊やくざ』
(1963年/原作:有馬頼義/脚色: 菊島隆三/監督:増村保造/制作:大映東京撮影所)
「俺はあいつを見捨てても、あいつは俺を見捨てない!」
時は第二次世界大戦中、ソ連との国境近くにある満州北部の町・孫呉の駐屯地に初年兵として大宮貴三郎が配属される。元やくざの大宮は規律に厳しい帝国陸軍にあって型破りで、気に入らないことがあれば上官だろうが上等兵だろうが平気で喧嘩を仕掛ける暴れん坊だった。そんな大宮の世話係を命じられた三年兵の手記のような形式で有馬頼義が記した小説『貴三郎一代』は後に映画化され、『兵隊やくざ』というタイトルで公開された。
映画の基本的な設定や展開は、原作を踏襲している。暴れまくる大宮(勝新太郎)と、彼を庇う三年兵の有田(田村高廣)がさまざまな軍隊の理不尽とぶつかりながら友情を育み、やがて脱走を企てるようになる──という内容だ。
ただ、原作から大きく脚色しているポイントが二つある。一つはメッセージ性だ。映画は軍隊の過酷さが強調されており、反戦作品としての色合いが濃い。原作でも上等兵による暴力や上官による過剰な制裁、脱走兵の哀れな末路など、軍隊生活は過酷なものとして描かれていた。ただ、それは当時の状況としては当然のこととも受け止められる書き方になっている。
だが、映画はそうではない。彼らの置かれた前線の状況の非人間性を訴え、戦争や軍隊への批判精神が表立って痛烈に表現されているのだ。そうした作り手たちのスタンスは、冒頭のナレーションからハッキリと打ち出されている。
「逃げようにも逃げられない、荒野に孤立した巨大な刑務所」「猛烈な訓練と厳しい軍律で有名な部隊」「地獄のような苦しみに耐えられず、よく脱走しては失敗」
といった具合に、これから描かれる世界がいかに過酷なものであるかを伝えているのだ。原作では、孫呉の駐屯地をそこまで異様なものとは記していない。
また、映画は原作からいくつかのエピソードを抜粋して物語を構成しているのだが、その抜粋の基準もスタンスが明確だ。多くある原作のエピソードから、軍隊の理不尽さが際立つ内容に絞ってピックアップしている。大宮と有田が戦友の遺骨を届けるために東京へ向かう場面や、新京の娼館でのドタバタ劇といった、二人が外界の風を浴びるような、ともすれば牧歌的とも受け止められる場面は全てカット。ほとんどが駐屯地の重苦しい空気の中で展開されていった。
それに合わせるように、二人の設定も脚色が加えられている。
原作は、大宮が配属されてからの二年間が描かれる。そのため中盤で大宮は二年兵に進級、それにつれて当初のヤンチャぶりは収まるようになり、上層部からも安心される存在となる。一方、映画は一年間の話としたため、大宮は初年兵のままだ。配属した時の勢いを保ち続けて、徹底して反抗的な態度を貫く。
それ以上に設定が変わっているのが、有田だ。原作では二年目に伍長に昇進しており、基本的には軍務を真面目にこなしている。だが、映画ではそうではない。
わざと幹部候補試験を落ち、普段はズボラを決め込む。ナレーションで「とにかく軍隊は大嫌いだった」と語るように、軍務にあまり身をいれていないのだ。「こうしなければ、軍隊のような無法で理不尽な組織では生きられなかった」と語っており、軍のあり方を徹底的に毛嫌いしている。原作でも、有田はあと一年で内地帰還ができるため、そのことを第一に考えて暮らしている。だが、映画のように明確に軍隊へのアンチの姿勢は示していない。
こうした設定を追加した結果として、二人の関係性も原作とは異なるものになっていく。それが、二つ目の脚色ポイントだ。
映画も原作も「本能のままに動く大宮」「それを必死に庇う理知的な有田」という構図は同じだ。が、両者の間、特に有田に流れる感情が異なるのである。
原作では、子どものようなヤンチャ坊主であれる大宮に対して、有田は困り果てながらも義務感と同情心から世話を焼く。それは規定通りに内地に帰還するために、余計なトラブルを起こしたくないからだ。
だが、映画はそうではない。まず、先に挙げた設定の追加により、大宮も有田も軍隊に反発のスタンスをとっている者同士という共通項が生じている。そのため、有田は大宮の暴れっぷりに手を焼くような様子は見せず、むしろ頼もしくすら思っているような節がある。
そして、過酷な軍隊生活とそれへの反抗の想いを重ねながら、この同志的な結合が熱い友情へ転じていく──という展開が映画の主軸となっている。
二人の関係性を強めるために、原作から設定が大きく変わった人物がもう一人いる。それが、二人の所属する内務班の班長だ。原作での班長は有田と同様に大宮のよき理解者であり、事あるごとに有田をバックアップしていた。大宮がトラブルを起こしたり巻き込まれたりする度、班長と有田で相談しながら対処に当たっている。そのため原作の前半では、有田の相棒は大宮というより班長という感すらあった。
だが、映画には班長の阿部(仲村隆)と有田の間にバディ感はない。基本的には大宮のトラブルに手を貸そうとせず、それどころか、時には大宮への制裁を黙認・追従することすらある。この脚色は、駐屯地の「地獄」という空間にふさわしい救いの無さを体現してもいる。だがそれ以上に、大宮のサポート役が有田一人に絞られたことで、大宮にとっても有田にとっても「この場で味方は互いしかいない」ということになり、その関係性をより濃密なものにしていた。
その結果、有田の大宮を想う気持ちは全編にわたって色濃く出ることになった。
それが最も現われているのが、大宮が単身で炊事班に殴り込みをかけ、有田が班長に援軍を求める、終盤の場面だ。原作では頼りになる班長は既に転属しており、新任の班長に持ちかける。だが、班長の言い分の前に納得して、有田は引き下がってしまう。
一方の映画では、班長は変わらず阿部のままだ。そして阿部は有田の懇願に、こう返している。
「いかんなあ、止めろ」「大宮が悪い」
これが原作の阿部であれば、すぐにでも援軍を出したかもしれない。が、映画はにべもない。ここでの大宮の味方は、有田しかいないのだ。
それでも、原作と違い有田は簡単には引き下がらない。
「だが可愛い奴だ。頼むよ!」
そう必死に頼み込む有田に、阿部はこう言い放つ。
「お前は可愛いだろうが、俺はもうご免だ。これ以上ゴタゴタを起こしたくない」
ここでわかるのは、有田は大宮を「可愛い奴」と思っていることだ。これは、原作では描かれていない感情だ。それに対する阿部の返答は、その感情を有田以外は抱いていないということを示すものである。
この直後の展開が、まさにそうした有田の孤立無援の状況を示している。原作では有田の頼みで四年兵の仲間たちも加わって大宮救援に向かっているのに対し、映画では有田がただ一人で乗り込んでいるのだ。
終盤も同様の手法で脚色されている。話の展開自体は同じなのだが、そこでの有田の言動や感情が異なるものになっている。
たとえば、大宮が南方戦線に転属することが決まった際のリアクション。原作では「私は、今度の編制がえについて、ひどくあっさりと認めてしまったが、やはり一度は准尉に相談をするべきだった、と思った」とあるように、後悔はしているものの簡単に通してしまっている。一方、映画では准尉(内田朝雄)に大宮の残留を必死に頼み込んでいるのだ。
そして、大宮の姿が駐屯地から見えなくなる。この時、原作では有田が善後策を新任班長に相談し、班長の命令で有田は町に捜索に向かった。有田に先んじて、班長は大宮が脱走したわけではないと判断していたのだ。むしろ有田の方が最初は大宮の脱走や自殺を想定していた節がある。
が、映画は異なる。大宮は南方に送られることを嫌がり、脱走したのだ──班長はそう考えていた。そして、「見かけによらず臆病者だ。やっぱりヤクザだな」と嘲笑う。そんな班長に対して有田は「大宮は絶対に脱走しない!」と断言する。そして、その根拠を問われた際に答えたのが、冒頭に挙げたセリフだ。大宮は脱走するにしても、絶対に自分を置いていくはずがない。そこには、大宮への確固たる信頼があった。大宮のことは我がことのように理解している。唯一にして最大の理解者。それが、映画での有田なのだ。
そして実際に、戻ってきた大宮は有田に、二人での脱走を持ちかけることになる。共に南方に送られることになった二人が、機関車の機関部を切り離して脱走する──という展開は、原作と変わらない。ただ、大宮が有田に脱走を持ちかける際のセリフが大きく異なっている。原作での大宮はそれとなく脱走を匂わせているのに対し、映画の大宮は有田に堂々とこう言い放つのだ。
「上等兵、黙って俺についてこい!」
これに対する、有田の返しはというと──。
「ようし、ついていこう。俺もお前と別れたくないんだ!」
この時、二人の間にはもはや軍の階級は存在しなくなっていた。全ての枠を飛び越え、互いを敬い、理解し、想い合う、最高のバディが誕生したのである。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。