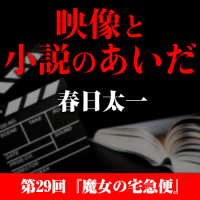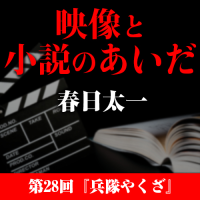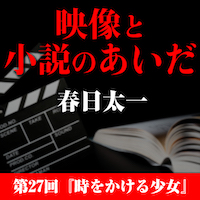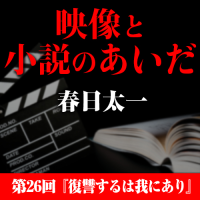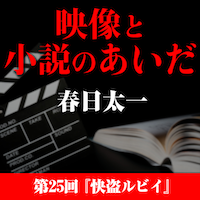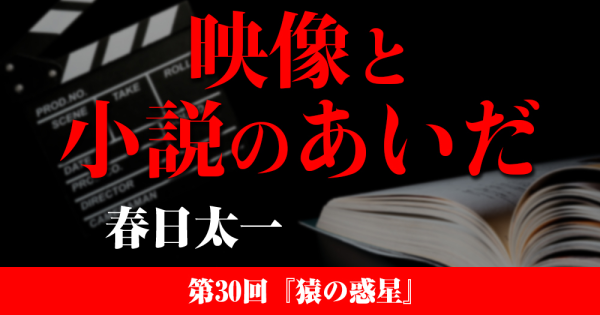連載第30回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
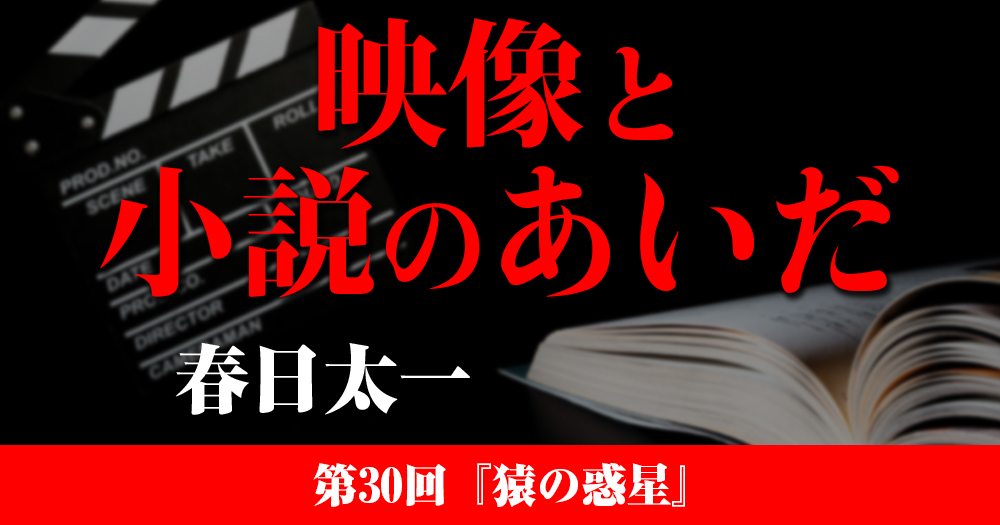
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『猿の惑星』
(1968年/原作:ピエール・ブール/脚色・監督:アーサー・P・ジェイコブス/制作:20世紀フォックス)
「 We finally, really, did it, you idiots!(字幕訳:ついに、本当にやっちまったのかよ、馬鹿野郎! )」
宇宙飛行士がある惑星にたどり着く。そこには空気も水も文明もあり、風景は地球にとてもよく似ていた。だが、大きく異なる点があった。それは、人類には文明がないどころか言語もないほどに退化しているということ。そして、その星の支配者として君臨しているのは猿類だった。彼らは文明も言語も持ち、人間たちを下等な生き物として扱っていた――。
ピエール・ブールの書いた小説「猿の惑星」は現在に至るまで何度も映画化されてきた。特に、最初の1968年版は不朽の名作として名高い。その基本的な設定は上記の通り、その惑星では猿と人間の関係性が逆転しているという内容で、原作と変わらない。
前半の大まかな展開と主要キャラクターの関係性も同じだ。自分たちと全く異なる原始的な人類の姿に驚愕するところから始まり、主人公は猿による人間狩りによって囚われる中盤へ。そこでは人類は檻に入れられ、研究者たちによる実験対象になっていた。ただ一人だけコミュニケーション能力を持つ主人公に対して、女性科学者のジーラとその恋人のコーネリアスは学術的な発見だ、と喜び、好意的に接する。その一方、上司のザイウスは主人公の能力を頑なに否定しようとした――。
このように、物語の基盤は原作に準拠している。だが、他は多くの点で脚色が施されている。
まず、主人公の設定だ。原作の主人公・ユリスは新聞記者で、異星のルポルタージュを書くつもりでこの計画に参加していた。そのため、この星での様子や自分自身の心理状況を細かく客観的に観察する傾向にあり、そうした中でジーラとの交流を通して檻の中での生活にも順応していく。
だが、映画のテイラー(チャールトン・ヘストン)はそうではない。タフな軍人で、檻の中にあっても脱出の機会を絶えずうかがい続ける。猿の兵たちとも互角以上に戦うし、ジーラとの交流も脱出のための手段に過ぎない。
その一方でテイラーは地球の人類に強い絶望を感じている。宇宙船の船内では六ヶ月しか経過していないが、地球上では映画開始時点で既に700年以上が経っており、冒頭では「未来の人類」に次のように想いを馳せている。
「いまだに殺し合いをしているだろうか」
「飢えている同胞を見殺しにしているだろうか」
(※いずれもソフト版の吹き替え訳)
つまり、戦争や貧富の差が絶えない地球における人類に強い絶望感を抱く、厭世的なニヒリストなのである。原作のユリスにはそうした描写は見られず、人類を「万物の霊長」と語っている。
また、惑星の描写も大きく脚色されている。まず、原作では主人公はこの星を「惑星ソラール」とハッキリ認識しているのに対し、映画は不意の事故によりたどり着いたため、この星がどこなのかわかっていない。文明の度合いも違う。原作では現在の地球と同じように、自動車などの機会文明が発達しており、初期段階ながらも宇宙飛行への実験も始まっている。だが、映画はそうではない。猿たちの移動手段は馬であり、住宅も石や木などで造られたもの。銃はあるもののそれ以外の機会文明は発達しておらず、地球でいう古代後期~中世初期くらいの様子で描かれている。その前提としてあるのは、原作の「猿の惑星」は緑も資源も豊富であるのに対し、映画では大部分が不毛な砂漠に覆われているといことだ。
惑星を支配する価値観も同じだ。「猿は人間が進化した存在」と主張するジーラ&コーネリアスに対し、それを否定するザイウス――という構図は変わらない。ただ、原作のそれが科学者同士の学説的な対立軸なのに対し、映画ではそうではないのだ。映画には地球における欧米のような聖書が存在しており、中世ヨーロッパのようにその価値観が絶対視されている。そして、聖書には「猿は神がその姿に似せて作った万物の霊長」と記されおり、進化論はそれを冒涜する異端という位置づけになっている。そして、ザイウスはこの価値観を絶対視している。つまり、科学対宗教という対立軸が映画には加わっているのだ。
その象徴として出てくるのが、聖書に「決して踏み入れてはならない」とされている「forbidden zone(禁断の地域)」である。そこに進化論を証明する遺跡があるに違いないと主張する二人に対し、ザイウスは強硬に反対していた。この「禁断の地域」もまた、原作には登場しない。
こうした多くの変更点があるため、後半の展開は全く異なるものになっていく。
原作では、ユリスはジーラ&コーネリアスと共謀して学会発表でザイウスを失脚させ、猿と同等の文化的な生活を手に入れる。一方、映画では、テイラーはジーラ&コーネリアスとともに「禁断の地域」を目指す。テイラーは猿に支配されない安息を求めて。ザイウスにより異端の烙印を押されたジーラ&コーネリアスは、自説の正しさを証明するため。
「禁断の地域」で彼らは人類の遺跡を発見する。そこには人形があった。それは、かつて人類にも文明があったという証拠である。この描写は原作にもある。が、その意味するものは大きく違う。原作における「人類」は、主人公にとってあくまでも「異星人」だ。が、映画はというと――。
映画のテイラーは期せずしての墜落事故により惑星に着いたため、地球に帰還する手段はない。原作では母船は惑星軌道上に残されたままなので、地球に戻ることができる。これも、ラストに向けて重要な脚色となる。
原作の終盤は、ユリスは檻で生活を共にしてきた人類の女性・ノヴァが妊娠・出産したために猿たちから危険視される。さらにザイウスが復権してジーラたちの立場がなくなったことで、地球への帰還を決意。妻子とともに地球に帰還するも、そこも既に猿が支配していた――というラストになっている。
だが、映画でのラストは全く異なる。
遺跡で一行に追いついたザイウスは、聖書の次の一節を伝える。
「人類は万物の死を招くものなり」※吹き替え版訳より
そして、次のように語る。
「人類は感情に囚われやすく、せっかくの才能を戦に費やし、周囲を巻き込むばかりか己をも滅ぼす」
「禁じられた地域はかつてパラダイスだった。お前の同類が砂漠にしてしまったんだ」
ザイウスは既に人類がなぜ文明を失ったのかを知っていたのだ。人類は自ら開発した高度な文明を戦争のために使い、そして自身を滅ぼすばかりか惑星をも壊滅させた、と。そのために彼は人類を畏れ、忌み嫌い、そして宗教を利用して真実を隠蔽してきた。それは、この星を護るためでもあった。ここで、科学的な価値観を是とし、宗教的な価値観を否とするこれまでの展開が反転する。原作では、猿が覚醒したことで人類を戦いによって支配した設定になっているが、映画の人類は自滅したのだ。その後で猿の覚醒が始まる。人類に二度と愚かなことをさせないためにも、聖書による支配が必要だったのである。
テイラーはジーラたちに別れを告げ、「禁断の地域」のさらなる奥へと向かう。
「You may not like what you find.(吹き替え訳:答えを知っても悲しむだけだ)」
そう言って止めるザイウスに耳も貸さずにテイラーは旅立つ。そして、その果てにたどり着いた時、テイラーが発したのが冒頭に挙げたセリフだ。
泣き叫ぶテイラーの前には朽ち果てた自由の女神像が。テイラーが飛び立ってから、テイラーの計算上では2000年が経っていた。ここは、その2000年後の地球だったのだ。猿の聖書が示す人類とは、まさに我々と同じ地球の人類だった。人類は核戦争により自らの手でその文明を失っていた。
「God damn you all to hell!(字幕訳:皆 地獄で苦しめ!)」
というテイラーの叫びとともに、物語は終幕する。
主人公のニヒリズム、不意の事故により着いた不明な星、発達しきっていない文明、聖書と「禁断の地域」――。全ての変更点が、このラストに向けて完璧に効いている。「衝撃の結末」としてよく知られる作品だが、そこに向けて数々の緻密な脚色を施したからこそ、ただの衝撃だけでない物語としての説得性をもたらすことになったのである。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。