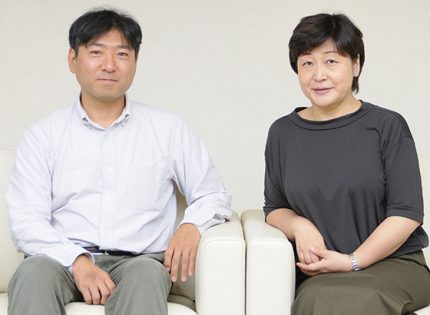連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:加藤直樹(ジャーナリスト)
関東大震災のもうひとつの闇とも言える朝鮮人大虐殺。当時を記録した膨大な資料をもとに、当時の社会や人々の姿を見つめた加藤直樹さんと、差別のない未来を作るためにはどうすればよいかを語り合いました。
第十七回
民族差別の種火を消そう
ゲスト 加藤直樹
(ジャーナリスト)
Photograph:Hisaaki Mihara

加藤直樹(左)、中島京子(右)
なぜ小池都知事は、追悼文をやめたのか
中島 今年九月一日に墨田区の都立横網町公園で開催された「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」に際して、小池百合子東京都知事が追悼文の送付を取りやめました。それに抗議する声明文を出したいと、加藤さんから声をかけていただき、私も二つ返事で賛同しました。
加藤 中島さんから、作家の平野啓一郎さんや星野智幸さんなどにもお声をかけていただき、最終的にはすごい顔触れの方々に賛同していただくことができました。ありがとうございます。
中島 私自身は名前を書いただけで、加藤さんは、声明文を起草するなど獅子奮迅の大活躍だったのですが……。都知事のあの判断は、世間的にも話題となって、新聞などにも大きく取り上げられましたね。
加藤 じつは、最初から小池都知事に対する批判の声がこれほど大きくなると思って行動していた訳ではないんです。
中島 えっ、そうなんですか?
加藤 そもそも「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典」が横網町公園で行われていること自体知られてないし、都知事がそこに追悼文を送っていることも、ほとんどの人は知らなかったでしょう。
中島 確かに。私も各地で追悼式が行われていることはなんとなく耳にしていましたが、場所や内容までは……。
加藤 八月中旬に、都知事が追悼文送付を取りやめようとしていることが分かったとき、いくつかの新聞社に伝えたのですが、知事が追悼文を出さないことが問題なのかどうなのか、すこし考えさせてくださいという反応もありました。
中島 ええっ! それはひどい。
加藤 マスコミが動き始めたのは、八月二十四日に東京新聞が一面で取り上げてからですね。追悼文をやめるのはおかしいという声が一気に広がりました。

加藤 去年から右翼団体が、横網町公園にある関東大震災朝鮮人犠牲者追悼碑を撤去しろと騒ぎ始めていました。それを受けて今年三月の都議会で古賀俊昭都議が追悼碑に書かれている〈あやまった策動と流言蜚語のため六千余名にのぼる朝鮮人が尊い生命を奪われました〉という文言を問題にしたのです。「朝鮮人が暴動を起こしているという流言飛語によって迫害され虐殺されたと書いてあるが、朝鮮人暴動は流言ではなく事実だ。この文言は事実に反する。死者数も根拠が希薄だ」、と。
中島 それこそ史実の捻じ曲げですね。
加藤 小池都知事は、もともと右寄りだといわれていましたが、まさか追悼文送付をやめるとは思いませんでした。
中島 これまで慣例でやってきたことですからね。
加藤 古賀都議は、「慰安婦問題と同様に、そのうちに韓国から日本に対して謝罪要求が突きつけられる。だから、虐殺自体を認めないという態度を取るべきだ」という意味の発言もしています。
中島 加藤さんが当時の新聞記事などの資料を丹念にあたってお書きになった『九月、東京の路上で 1923年関東大震災ジェノサイドの残響』(ころから刊)を読むと、多くの朝鮮人たちが根も葉もない流言蜚語がきっかけとなって虐殺されたことは、紛れもない事実だということがわかります。

中島 彼らは、虐殺された朝鮮人が六千人という数字を問題視しているようですが。
加藤 確かな人数は誰にも分かりません。当時の日本政府はそれを調査しようとせず、むしろ矮小化しようとした。だから全体像が分からないのです。
中島 隠そうと思ったんですね。
加藤 二〇〇八年に内閣府の中央防災会議がまとめた「1923関東大震災報告 第2編」では、虐殺された朝鮮人や、朝鮮人に間違えられて殺された日本人、中国人の総数を千人から数千人と推定しています。
中島 国がまとめた最新の研究・調査にも、虐殺の事実は当然記載され、人数も千人単位とされていると。
加藤 さらに当時の内務省や警察が流言を拡散したことが事態を悪化させたこと、軍の一部は自ら殺害に手を染めたことなども記載されています。この報告書は内閣府のホームページで公開されているので、誰でも読むことができます。
日本人は、流言蜚語に扇動された
中島 加藤さんはなぜ朝鮮人大虐殺の記録とその記憶を書き残そうと思ったのですか?
加藤 この事件の記憶を共有してほしかったのです。これは決して忘れられてはならない記憶だからです。ちなみに、『九月、東京の路上で』には悲惨な出来事が多く出てきますが、私は資料に残されているものの中でも、あまりに残酷なものはむしろ取り上げないようにしたんです。あまりに残酷な記録をそのまま読むと、それに対するショックでかえって思考が止まってしまいますから。
中島 それでも、これだけの内容になるということなんですね。加藤さんの記述は淡々としています。
加藤 センセーショナルに煽りたいわけではなくて、事実を事実としてとらえて、どうしてこんなことが起きたのだろうと考えることを、読者と共有できればいいと思って書いたんです。
中島 二〇一一年三月十一日の東日本大震災直後にも、いろんな噂が飛び交いましたね。
加藤 そうですね。たとえば石巻周辺で外国人の窃盗団が横行しているという噂がありました。当時石巻でボランティアをやっていた青年が、そのときの話を聞かせてくれました。仲間どうしで、「外国人の窃盗団が横行しているから気をつけよう。夜道を一人で歩かないようにしよう」と言い合っていたそうです。まさかそれがデマだったとは当時は誰も考えなかった、すっかり信じていたと言っていました。災害時に外国人差別に基づく流言が現れることは、今でもあることなんです。ましてヘイトスピーチがネット上にあふれている最近の状況を思えば、用心しなくてはいけない。

加藤 関東大震災のときに決定的だったのは、内務省や警察が流言を広めてしまったことなんですよね。制服を着た警官が、「朝鮮人が襲ってくる」と言ってまわれば、みんな信じてしまう。行政機関や政治家が差別的な流言に対して抑制的であることがとても大事だということが分かります。
中島 最近の、北朝鮮危機を煽る傾向も不安ですね。政府やメディアに、怖い、怖いと思わされているところに、デマを流されたら、動揺する人が出てしまいそう。
加藤 そうですよね。関東大震災のときも、朝鮮人が井戸に毒を入れているとか、放火しているという流言をなぜ人々が信じたかと言えば、震災前から育っていた朝鮮人に対する認識のゆがみがあったからです。「あいつらならそういうこともやりかねない」というものです。さらに、仮に、百歩譲ってその流言を信じたとしても、警察に連れて行けばいいのに、殺してしまう。
中島 そうですよね。なぜ、殺してしまったのか。
加藤 相手が日本人なら殺せなかったと思うんです。朝鮮人だから殺してもいいと思ったわけですよね。民族差別が作ったゆがんだ認識が惨劇を引き起こしたわけです。流言を信じ、暴力に向かった背後には、「あいつらは怖い存在だ」と「あいつらは殺してもいい存在だ」という二重のかたちであらわれた民族差別意識がある。
中島 差別感情自体をなくすのはなかなか難しいかもしれないけれど、わたしたちひとりひとりが意識を変えていく努力をすることはできると思います。
加藤 あいつらは何人だから悪さをするに違いない、というような民族差別的な意識が社会の中で普通に横行して、場合によっては行政を担う人たちまで、そういうことを考えるようになると、すごく危険なことになるということですよね。だからこそ、朝鮮人虐殺の記憶は決して忘れてはならないのです。とくに多くの民族的ルーツを持つ人が多い東京にとって、あの事件は重要な「負の原点」だと思うんです。
外国人という人はいない
中島 一方で、外国人が多いというのは、じつは東京の魅力のひとつですものね。
加藤 そう思います。東京は現実に多民族都市です。さまざまな地方、さまざまな国から来た人々が、東京の魅力を作ってきました。私自身も、東京でいろんな国の人たちと出会い、友だちになってきた。中国人、アメリカ人、韓国人……。いろんなルーツをもつ人々がつくる多様性こそが、東京のよさだと思います。一九八〇年代には、YMOが『テクノポリス』という曲で「TOKIO!」って連呼してたじゃないですか(笑)。あの頃は、東京は国を超えた世界都市だと豪語していたわけで。
中島 そうそう。あの頃の日本はイケイケでしたものね(笑)。
加藤 それがいつの間にか、外国人が多くていやだなんていう否定的な言葉ばかり聞こえるようになってきた。じゃあ日本人しかいない東京がいいのか。 私が育ってきた東京はそういう街じゃなかった。絶対に。
中島 それが、なぜ排他的、差別的になってきたのでしょう?
加藤 長い歴史的な視点で見ないといけないでしょうね。私が思うに、日本は日清戦争で中国を破り、周辺諸国を植民地化して、さらに戦後は高度経済成長で、アジアのトップに立った。だから他とは違う特別な国である、アジアにおける発展の唯一のモデルであるという自己イメージをずっと持っていたと思うんですよね。それが九〇年代以降、あれよあれよいう間に世界が動いて、中国や台湾、韓国が新しい世界経済の中で大きな存在となってきた。しかも日本とは違った姿のままで。つまり日本はアジアのトップでも唯一のモデルでもなくなった。本当はもともと、そんなことなかったのだとぼくは思っていますが。いずれにしろ、この変化が受け入れられないんだと思うんです。だから、まだ大丈夫だ。強い日本を取り戻すんだ。と、後ろ向きの意識にしがみついているのが、今の日本に根強い発想なんじゃないでしょうか。それが、民族差別が煽られる風潮の背景にある。
中島 特別じゃなくても、いいのにね。
加藤 「中国は発展しているように見えるけれども、本当はいずれ崩壊する」「韓国の映画やK‐POPは、オリジナルに見えるけど本当は全部日本のパクリなんだ」とかね。感情的に現実を否定している。そういうこわばったことを言い張って、昔の栄光を取り戻そうとして歯を食いしばっているから、かえってどんどん苦しくなっちゃうんじゃないかと私は思うんですけどね。
中島 いまの日本は、自分で自分の首を絞めているのかもしれませんね。

中島 その子が日本に来て、嫌な思いをするんじゃないかと思うと呼べなかった。
加藤 そうなんです。
中島 流言蜚語を信じがちな傾向とか、差別感情や同調圧力、そういうものを全てきれいに消し去ろうと思っても、人の中に種火のように潜んでいて、なにかがあるとそれがニュッと伸びてきて、ぼわっと火がつく。だから、火がつきそうになったら、自分で消してしまうような感受性をひとりひとりの心のなかに育てなければいけないんでしょうね。
加藤 そうですね。私も、百年前の関東大震災のときと全く同じことが再現されるとは思っていません。だけど今でも、災害時に民族差別に基づく噂が広がって誰かがそれによって暴力を振るわれたり、傷つけられたりする事態は起き得るんです。大事なのはそういう差別的流言を許さず、広がらせない社会をつくることだと思うんですよね。
中島 そうですね。二〇〇二年のサッカーワールドカップ日韓共催や、映画『シュリ』、テレビドラマの『冬のソナタ』などを契機に、日本では「韓流ブーム」がおこりました。そのあとK‐POPが来て、日本と韓国はずいぶん近づいたでしょう。政治的にはどうあれ、草の根レベルでの交流がもっと盛んになれば、差別意識の種火も消えてしまうかもしれません。
加藤 同感です。もっと交流があったほうがいいと思います。
中島 民族ではなく、ひとりひとりの人間として、相手の顔を見て友だちになる。『九月、東京の路上で』の中にも、そういう関係ができていた人たちは、流言蜚語に惑わされずに、命を救ったというエピソードがありました。凄惨な事件ですが、そこからは一筋の光が見えた気がしました。
加藤 人と人としての関係が大事ですよね。私はネットで嫌韓の書き込みを見ていると、自分の韓国人の友だちのことを悪く言われているような気持ちになって、すごく腹が立つんです。「こいつが嫌い」ならともかく、「韓国人」という民族それ自体を否定するのは、私の好きな友人たちもまとめて存在を否定することなわけで。
中島 名前と顔を持つ友だちを思い浮かべれば、その人を傷つけたくないと、自然に思いますよね。
加藤 そう思える機会を、もっといろんな形でつくるべきだと思います。日韓の高校同士が交流したといったニュースをたまに見ますよね。ああいうのはすごくいいことだと思いますね。
中島 そういえば、加藤さんは大久保のご出身ですよね。子どもの頃から韓国の人との交流は深かったのですか?
加藤 いまはもう住んでいませんけれど、大久保生まれの大久保育ちです。ただ、私の子どものころは、在日の人は相対的には他の地域より多かったと思うけど、今のような「韓流タウン」では全くなかったです。でも今では、私が卒業した小学校などは外国人の子どものほうが多いぐらいなんですね。韓国人だけではなくて、いろんな国の人がいる。日本語ができない子どももいるから、学校側も日本語の勉強のために時間をつくってサポートする。だからすごく、いい雰囲気なんだそうです。まあ、子どもの数が少ないからできるっていう面もあるのでしょうが。
中島 子どもにとって、それは素晴らしい環境ですね。
加藤 私の姪は亜美という名前なのですが、彼女がまだ幼いときに、大人が「亜美のクラスは外国人ばっかりだよね」と尋ねたら、亜美が「えっ、外国人の子なんかいないよ」と言うんですよ。「そんなことないじゃない。たくさんいるじゃない」と聞き返したら、「うーん、なになにちゃんはタイ人だし、なになにちゃんは韓国人だし、なになにちゃんは中国人だけど、『ガイコク人』の子はいないなあ」って。
中島 かわいい。偉いね、亜美ちゃん。
加藤 いろんな国の人がいるのが当然で、「外国人」 はいない。本気でそう思っているんですね。それは周りの大人や先生がそういう雰囲気を支えているから、できているんだと思うんです。
中島 いい話ですね。それこそ、私たちが目指すべき未来の東京の姿。そんな未来がやってくることを切に願います。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
加藤直樹(かとう・なおき)
1967年東京都生まれ。新宿区大久保で育つ。法政大学中退。出版社勤務を経てフリーランスに。著書に『九月、東京の路上で』(ころから)、『謀叛の児 宮崎滔天の「世界革命」』(河出書房新社)、共著に『戦争思想2015』(河出書房新社)など。翻訳にチェ・ギュソク『沸点 ソウル・オン・ザ・ストリート』(ころから)がある。
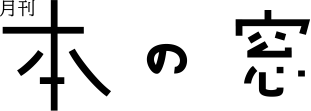
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2017/11/20)