【後編】「いじめ」への処方箋 ~いじめ問題を真正面から描いた小説5選~

決してなくならない、いじめ。脳科学者の中野信子が2017年に発表した『ヒトは「いじめ」をやめられない』では、脳科学の視点からいじめ問題が考察され、反響を呼びました。小説の分野でもこの問題に真正面から向き合った作品は少なくありません。今回は前編に引き続き、いじめを真摯に考える小説2編を紹介します。
いじめられたことを親や教師に言えない子どもの心理をリアルに描く――田中慎弥『冷たい水の羊』(『図書準備室』所収)
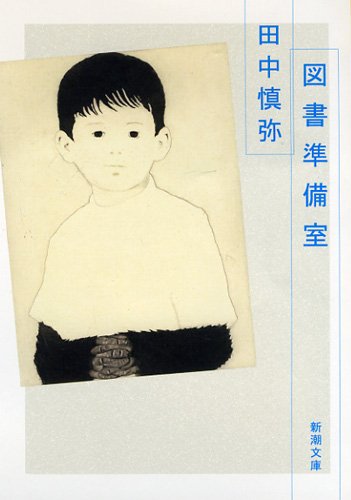
https://www.amazon.co.jp/dp/410133482X
いじめられっ子が自殺したとき、親や教師は、「どうしてもっと早く言ってくれなかったのか」というようなコメントを言いがちです。いじめられっ子は、自分がいじめられていることを誰にも知られたくないと考えるわけですが、『冷たい水の羊』を読めば、その理由が分かるかもしれません。
作者の田中慎弥は、高校卒業以来、アルバイトを含め一切の賃労働に就かず、十数年間の引きこもり生活の後、2005年本作で第37回新潮新人賞を受賞してデビューしました。本作は、いじめを題材にしたものですが、作者のいじめに対する考え方には特異さが際立っています。
本作の主人公の大橋真夫は、小学生の頃から勉強も運動も苦手で、クラスの隅に追いやられているような生徒です。クラスメートに貸した物が返って来なかったり、体育のバスケットボールではいつも空気の抜けたボールしか使わせてもらえなかったりと、客観的に見ればいじめの端緒とみられる現象に、当の真夫はこう思い込むことで切り抜けようとするのです。
“一般的に言われている、いじめられたと感じた時点でいじめが成立する、という論理を当て嵌めてみた。つまり、いじめられたと思わないようにしようと決めた。こうすればいじめられていることにはならない。いじめられていないと思うのではない。いじめられていることにならない、という事実が大切だ。この論理は完全だ。”
現在一般的に浸透している考えとして、いじめられる側がそれを苦痛に思えば、いじめる側に悪意はなかったとしても、それはいじめである、というものがあります。つまり、受け手がどう感じるかということが全てである、という認識です。では、この理屈を逆手に取って、どんなにひどいいじめを受けていても、それを受けた本人がいじめだと感じていなければ、それはいじめではない、ということになるのでしょうか? 真夫の論理は、「気の持ちよう」を通り越して、あまりにも突飛でマゾヒスティックです。
それからしばらくして、真夫は担任教師から呼び出され、いじめられているのではないかと問い質されます。どうやらクラスメートの水原里子が、真夫がいじめられていることを教師に密告した模様。水原は真夫が淡い恋心を抱いている相手でもありました。真夫は教師に対し、いじめられていないと必死で主張しながら、水原に対してこう思うのです。
“いじめだと認識しているのは水原の勘違いだし偏見だ。いじめられていることを周りからも認められ、正式ないじめられっ子になる、それは最悪だ。”
ここに、いじめられっ子が、自分がいじめられていることを誰にも悟られたくないと思う心理がよく表われています。すなわち、いじめられていることを自認すれば、それは現実のこととして定着してしまうのであり、また、自分が弱く惨めな存在であることをも認めることになるからです。いじめられっ子にとって、いじめられること自体よりも、いじめられたことを知られることが一番こたえるのでしょう。自分がいじめられていることを、勇を鼓して教師に告げてくれた水原に対し、感謝の念を持ちこそすれ、恨むのはおかしいと考えるのは、本当にいじめられたことのない者の言い分かもしれません。
“いじめられている男はかわいそうだと思われていることに気づくとプライドが崩れる。水原が憐みの籠もった目で自分を見ている、その何の力にもならない視線を送って来た時、水原里子を道連れとして意識した。殺すところを想像してみる。包丁を選んだのは相手を求めていたからだ。無理心中というやつだ。”
真夫は、恋心を抱いていた水原に無様な姿を見せてしまったのがやるせなく、殺したいくらいの倒錯した憎悪を募らせてゆくのです。水原を包丁で刺して、自分も刺す。そうすれば、自分がいじめられていたという事実を、この世から抹消できるとでも考えているかのようです。本当に刺し殺すべき相手は、真夫から金銭を巻き上げたり、真冬に冷たい水を張ったドラム缶の中に素っ裸にした真夫を浸したり、下半身を裸にして肛門にほうきの柄をねじこんだりといった、陰惨ないじめをしている生徒たちのはずですが、そうした正論は、極限まで追い詰められたいじめられっ子には通用しないのです。真夫はそれ以来、常に鞄に包丁を隠し持ち、水原を襲うチャンスを狙うようになるのですが、手に汗握る展開に、最後までページをめくる手が止まりません。
いじめからは逃げるのが正しいか? 立ち向かうのが正しいのか?――江國香織他『いじめの時間』
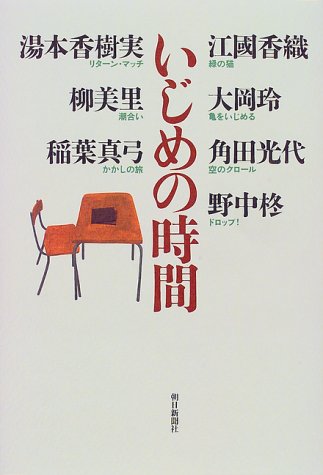
https://www.amazon.co.jp/dp/4022571497/
『いじめの時間』とは、タイトルからしてインパクトがありますが、ここ収められた、江國香織、角田光代、柳美里ら実力派作家による7つの短編は、いわば、様々ないじめの場面の現場報告書です。
読み進めていくうちに、この7つの小説に登場するいじめられっ子たちの反応が、3つに大別できることに気づきます。すなわち、いじめられた時、そこから逃げる「回避型」か、それに立ち向かう「報復型」か、逃げもしないが報復もしない「無反応型」かということです。
「回避型」を描いたのは、野中柊『ドロップ!』、稲葉真弓『かかしの旅』です。
『ドロップ!』の主人公は女子高生の「私」。「私」が長期欠席後、久々に登校すると、「私」の席には見知らぬ誰かが座っており、「私」の席はどこにもないことが判明します。あわててクラスメートに聞き回る「私」。しかし、皆はとぼけた反応をするばかりで、誰も親身になってくれません。そのくせ、「私」の持っているドロップ飴を目ざとく見つけた時だけは、「友だちだよね?」と皆が一斉に手を伸ばしてくるいやらしさ。「私」は座席のない教室で
“ねえ、外に行こうよ。外はお天気だよ。こんなところ、出てゆこうよ。青空の下を歩いたら、きっとすごく気持ちがいいよ。さあ、帰ろう。あそこには私の居場所がある”
学校を抜け出した「私」は、爽快な足取りで自分の居場所があると信じる「あそこ」へ向かいます。その「あそこ」がどこなのかは、読者一人ひとりの想像に委ねられていると言えるでしょう。
『かかしの旅』の主人公は小学3年の伊藤卓郎。卓郎は、幼時の事故で脚が不自由で、人前で話す時に言葉が上手く出て来ないことから、自嘲的に「かかし」と名乗っています。「かかし」は、クラスの腕白な男子・金井、望月、松岡、山田から日常的に暴力を受けたり、小遣いをひったくられたりしていました。そのことを苦に家出をした「かかし」は、家出先から金井たちへ手紙を書くのです。
“ぼくをいじめたように、まだいじめをやっているんだろうか。ぼくは知っているんだ。いじめられるのも、いじめるのも、たいして違わないってこと。ぼくは思う。本当は、みんな(注・金井、望月、松岡、山田のこと)も怖いんだろうなって。だれかを追い詰めて、とかげのしっぽ切りみたいなことをしていないと、体が震えるほど孤独なんだ。金井、君のお母さんは、いまどこで誰と暮らしているんだろう。望月、父親に殴られているのを、いつも自転車で転んだと同じウソをつくな。松岡、ぶらぶらしているお父さんの職はみつかったんだろうか。山田、一年のとき、上の学年の奴にいじめられているのをぼくは見てしまった。いろいろなことを知っているということは復讐になるんだろうか。けど、復讐はしないよ。そこへはもう戻らないつもりだから”
いじめられる者よりいじめる者の方が可哀想なのだという理論で、自らをかろうじて保っている「かかし」。家出をして公園でうろうろしていた「かかし」は、そこで仲間を見つけます。不登校や高校中退で昼間から公園でふらふらしている子どもなど、大人から見れば眉をひそめる存在ですが、彼らは皆、他に行き場所がない子たちであり、「かかし」は、ここで初めて自分の居場所を見つけるのでした。
『ドロップ!』と『かかしの旅』は、学校が世界の全てではなく、そこから逃げることは恥ずかしいことではないこと、学校以外にも素敵な世界は無限にあることを示唆しています。
しかし、いじめられたら何とか仕返ししてやりたいと思うのもまた、人間の本音ではないでしょうか。角田光代『空のクロール』、湯本香樹実『リターン・マッチ』、大岡玲『亀をいじめる』で描かれている「報復型」では、いじめられたらいじめ返すことの何がいけないのかという問題に、ギリギリまで迫っています。
『空のクロール』の主人公「わたし」は、私立の女子中学校で水泳部に入部しますが、水泳未経験者で入部したのは「わたし」が初めてでした。すぐに辞めると皆に思われていた「わたし」が、しぶとく続けていると、部のエースである女子・梶原が「わたし」を迷惑だと言い、溺れかけの老人が泳いでいるようだと「ババア」呼ばわりするようになります。使用済みの生理用のナプキンを机に入れられたり、水着の乳首と陰部の三か所を切り抜かれたり、コンドームを買いに行かされたりと、男子の目がないからこそのいじめがエスカレートしてゆく中、唯一「わたし」の味方をしたのは、同じくいじめられっ子で、顔中にきびだらけという理由で「月面」呼ばわりされている花崎だけでした。花崎は、いじめをするような卑劣な人たちのことは心の中で見下して無視していればよいのだと「わたし」にアドバイスします。しかし、「わたし」は、その意見には承服できません。
“いつかここを抜けでることができるとか、違う場所に行けば違う自分になれるとか、そんなことはもうなんにも信じたくない。(いじめっ子は)バカだの下品だの低俗だの、思いあたる言葉をつらねても、どこかへ行けるわけではないのだ。私が今いるのはここで、ここ以外になくて、いるべきところもいるはずの場所も全部ここなのだ。”
「わたし」の言い分は、前出の、学校以外にも素敵な世界は無限にある、という考え方を真っ向から否定するものです。「いま」「ここで」勝たなければ、これから「どこ」へ行ってもずっと負け続けるのだと思う「わたし」が、梶原の運動靴に、ペットショップで買って来た大量の金魚を水ごと忍ばせて、陰惨な喜びに浸ることを、読者はだれも咎められないでしょう。
『リターン・マッチ』の主人公は中学生のトモユキ。体育会系のヤンキーが幅をきかせる公立中学で、映画に詳しい文科系のトモユキは異端の存在。トモユキは、いじめられた仕返しに、いじめっ子それぞれの下駄箱にこんな手紙を書いて入れることを思いつくのです。
“放課後、屋上二来イ。誰ニモ言ワズ、ヒトリデ来イ。誰カニ言ッタリ、来ナカッタリ、アルイハ仲間ヲ連レテキタラ、僕ハ自殺スル。ソノ場合、遺書ニハ君ノ名前ト、君ガ僕ニシタコトヲ書クツモリダ”
トモユキをいじめていたことで屋上にひとりで呼び出された柔道部のケンは、トモユキの勇気に感心しつつも、非力なトモユキでは、たとえ一対一の対決でも暴力を振るわれたら勝てないと、彼の作戦を止めさせようとします。するとトモユキはこう言い放つのです。
“負けるのは、わかってた。でもいいんだ。百パーセント負けるとわかっていても、やるしかないことってある”
たとえ負けると最初から分かっていても、いじめられた以上受けて立つしかないと言うトモユキの覚悟に心を打たれたケンは、トモユキに柔道の技を伝授して、彼がリターン・マッチで勝てるように秘密の練習を重ねるのです。しかし、その練習はどうやら必要なかったようで、
“(トモユキが)屋上に誰かを呼び出す度に「正々堂々闘え」っていうんだけど、みんなそんなのお断りなんだ。一対一になった途端、態度ががらっと変わって、こそこそ逃げだすやつだとか、機嫌をとるようなことを言うのまでいたっていうから、驚いたよ。ケットウジョウのことが始まってから、トモユキを密かに尊敬っていうか、勇気あるっていうか、だんだんそういうふうに見るようになったやつもいたんだ”
トモユキは、いつも仲間と一緒でなくては自分をいじめられない男子たちが、一人では何も出来ない臆病者だと知り抜いていたのです。いじめられっ子が、頭脳戦でいじめっ子を見事に見返した、快哉を叫びたくなるほどの「リターン・マッチ」が描かれます。ところが、このことがトモユキの母に露見すると、トモユキの母は、自分の息子を被害者扱いし、クラスの男子たちを訴えると言い出すのです。トモユキが、自分はいじめられっ子ではないと言い張っても母は認めず、トモユキのプライドは傷つけられます。一連の成り行きを見ていたケンは、トモユキの母に腹を立て、不覚にもガラスの置物で彼女を殺そうとするのです。いじめを発見して通報する人物に対し、感謝の念どころか憎悪の念を募らせるという、倒錯した心理状況は、前出の『冷たい水の羊』にも通じるものがあるでしょう。
『亀をいじめる』の主人公は高校の男性教師・池田。彼は、受け持つクラスでいじめの萌芽があろうとも、見て見ぬ振りでやり過ごし、どこか他人事のように、深く関わろうとしません。教育者としてそうした無関心な態度はいかがなものかと思われますが、彼には彼なりの言い分があるのでした。
“中学・高校時代小柄な彼(池田)は、よく標的にされた。数人のクラスメートに、教育実習の女性が来る前の教壇に縛り付けられた。そしてあのライター。火がだんだん近づいてくるのを見ながら、こわさのあまり絶叫していた。チリチリと毛が焦げる匂い。それなのに、あの新米の女教師。ヒトのみっともない姿を目の当たりにするやいなや、悲鳴を上げて逃げた。それも半分笑いながらだ。何も笑いながら逃げることはないだろう。他人の痛みをわかるなんて、金輪際できっこないのだと悟ったのは、たぶんあの瞬間だった”
自宅で買っている亀の甲羅に熱湯を浴びせかけることで日々のストレスを発散させる池田。彼は子供の頃から、いじめを受けた憂さ晴らしに動物虐待をする奇癖を持っているのですが、それは、弱肉強食、食物連鎖といった自然界の残酷なシステムを想起させます。池田は教師であるにも関わらず、学校そのものに対して不信感を持っており、娘の学校でいじめが起こった時にも、内心、
“集団教育なんていったい何の役に立つっていうんだ。社会生活の基礎を築くなんて嘘の皮だ。それなら、人を貶めたり欺いたりする技術を身に付けさせた方が、よっぽど手っ取り早い。いじめいじめられる関係式こそ、生きる本質なのじゃないか”
と、諦念を混じえて思うのです。いじめられっ子の親を挑発するような匿名の手紙を書き、そのことで事態がさらに紛糾してゆくさまを、残忍な喜びに浸って眺めている池田。しかし、彼とて初めからそうした人間だったのではなく、自身がいじめられた体験や教師としての無力感から、次第に歪んだ思考を持つに至ったのであり、読者は彼を安易に責められないのです。
以上3作は、やられたからといってやり返すのはよくない、という世間一般の道徳に対し、一石を投じる問題提起がされています。
「無反応型」を描いたのは、江國香織『緑の猫』と柳美里『潮合い』です。
『緑の猫』は比較的裕福な子女の集う、女子高でのエピソード。主人公・萌子には、クラスにエミという唯一無二の親友がいます。ある時、エミは強迫神経症にかかり、日に何度も手を洗わないと不潔に感じたり、真っ白い食品以外は食べられなくなったり、登下校中に蟻を踏んでしまわないように下ばかり見て歩くようになったりし、挙句、生まれ変わったら人間ではなく「緑の猫」になりたいと言い出します。クラスの皆がエミを遠巻きにしてもなお、萌子がエミの味方をしようとすると、クラスの皆が萌子の間にもさっと線を引いたのです。萌子の母は娘を心配してこう諭します。
“「萌子は親友っていうものをはきちがえているのよ。仲がいいのは結構ですけどね、二人っきりでべったりっていうのは不健全よ。みんなと仲よくしなさい。お友だちは多い方がいいのよ。財産なんだから」”
しかし、母の助言に対し、萌子は懐疑的でした。
“ばかみたいなセリフだ、とあたしは思う。この人はいったい、「みんな」って誰のことだと思ってるんだろう。「みんな」なんてどこにも存在しないのだ。誰かをハブにするとき以外は。あたしは、「単独行動者」になった。高校を卒業するまで、もう絶対友だちはつくらない。”
「ハブ」とは、仲間外れという意味の若者言葉ですが、確かに、萌子が考えるように、少数の異質な者を排斥することで、その他大勢の集団の結束が高まる、ということはよくあることです。誰か一人を「ハブ」にしなければつながり合えない集団なら、そこに進んで加わりたいとは思わない、無理に馴染む必要はない、というのが萌子の持論です。その後、エミの病状が悪化して入院することになると、萌子は学校で一人ぼっちにならざるを得なくなるのですが、萌子は「緑の猫」のように超然とした態度で、それを気にしないことにして、残りの高校生活をしのぐのです。
『潮合い』で、いじめのターゲットになるのは、転校して来たばかりの里奈。小学校6年生の2学期と言う中途半端な時期に転校してきたことから、前の学校で何かあったのではと、皆から
“わたしから声をかけるなんてほんとはおかしい、あっちから声をかけるべきなんだ。湧きあがってくる不快感の正体が麻由美にはわからなかったが、しかし里奈が自分をむかつかせる厄介事を持ち込んできたことだけは確かだ。”
麻由美は、里奈のワンピースに下着のラインが透けていると言いがかりをつけ、服をぬがせようとしても反応が薄かったり、プールに落とそうと仕組んだら、自らあっさり飛び込んでしまったりする里奈に、不気味なものを感じ始めます。
“泣き出そうともしないで無表情で真っ直ぐ前を向いている里奈に馬鹿にされている気がした”
いじめっ子は、いじめられっ子が過剰に反応するのを見て面白がる、というのは真実なのかもしれません。里奈のように、柳に風と受け流すという処世術を使えば、いじめっ子は、いじめの潮時を失うのでしょう。この心理戦の勝者は、麻由美ではなく里奈なのです。
おわりに
いじめを題材にした小説には、目を覆ってしまいたくなるような痛ましい描写が多く、時に読み進めるのが辛くなることがあるでしょう。また、これらの小説を読んだからといって、問題を解決する特効薬にはならないかもしれません。しかし、ロシアの作家・チェーホフは「文学の使命は問題を解決することではない。問題が何であるかを正確に示すことだ」と言っています。いじめを取り巻く状況を読書のなかで「体験」し、正確に理解するということが、まずは大切なのではないでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2021/03/20)

