【直木賞・大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』が受賞!】第161回候補作を徹底解説!

2019年1月17日に発表された、第161回直木賞。文芸評論家の末國善己氏が、今回も予想! 結果は、大島真寿美氏の『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』でしたが、当初の予想はどうだったのでしょうか? 候補作5作品のあらすじと、その評価ポイントをじっくり解説した記事を、ぜひ振り返ってみてください!
前回の直木賞(第160回)を振り返り!
今回の直木賞予想も、前回の答え合わせから始めたい。
「平成」最後となった第160回直木賞は、森見登美彦『熱帯』を本命、真藤順丈『宝島』を対抗、垣根涼介『信長の原理』を穴と予想したが、結果は真藤順丈『宝島』だったので、またも外れとなった。これまで外した時は、対抗にも穴にも挙げていなかったダークホースが受賞していたが、前回は対抗が受賞という微妙な結果になり、予想は2勝3敗の負け越しとなってしまった。
林真理子の講評によると、『宝島』は第1回投票で圧倒的な支持を集め、
「『二次投票をすべきか』という議論になり、『これだけ票差がついているのに二次投票をするべきなのか』という声を受け、二次投票はしませんでした」(「産経新聞」2019年1月16日)
という。前回の予想で「沖縄問題は、辺野古の埋め立ても含め、日本人なら真剣に向き合わなければならない課題である。そこに正面から切り込み、一級のエンターテインメントに仕立てた手腕は、直木賞に相応しい」と書いたが、この評価ポイントは選考委員と変わらなかったようだ。一方で、『熱帯』については、「作家として小説とは何かという根源的な問題に切り込んだ心意気は、同業者にこそ評価されると信じたい」としたが、選考委員の琴線には触れなかったらしく、特に東野圭吾の選評
「本作には○も△も×も付けられなかった。この作品の何を楽しめばいいのか、まるでわからなかったからだ」「候補になっているのだから、ほかの人にはわかる美点があるに違いない。それが全く見えないのは、私に文学的素養がないからだろう。つまり本作は純文学なのだ。たぶん」(「オール讀物」2019年3・4月号。以下、第160回直木賞の選評の引用はすべて同誌)
は手厳しい。作者に失礼ながら思ったより高評価だったのが今村翔吾『童の神』で、全共闘世代の北方謙三が
「単純な構造である。権力と反権力。結局はそういうことだが、反権力が、権力によって、人ではないものに仕立てあげられている」「時代を通して、この国の闇の声として聞えては消されてきたものを、物語として書こうとした志を、私は評価する。大方の賛同は得られなかった」
と評価したのは納得だが、東野圭吾も
「読んでいる最中、頭に浮かんだのは『アベンジャーズ』であり、『ジャスティス・リーグ』だった。特殊な能力を持った登場人物たちが平安京を跋扈するヒーローものだと解釈した」「暗い歴史を仄めかす伝承は、どこの国にもある。こういう形で光を当てると同時に、自分自身も楽しもうとしている作家の姿勢を評価したい」
と高評価で、物語の面白さとテーマの設定に必然性があれば、時代考証など細かなミスをあげつらって批判しない選考委員がいると分かったことは、予想をする立場では参考になった。
「令和」初となる第161回直木賞は、朝倉かすみ『平場の月』、大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』、窪美澄『トリニティ』、澤田瞳子『落花』、原田マハ『美しき愚かものたちのタブロー』、柚木麻子『マジカルグランマ』と、史上初めて候補者全員が女性なのも話題を集めている。だが1980年代以降の女性作家のジャンルを問わない活躍をリアルタイムで見てきたので、この状況になるのが遅過ぎたのではとの印象の方が強い。
また「平成」の最末期に発表された作品が多いためか、『トリニティ』『マジカルグランマ』『美しき愚かものたちのタブロー』が日本の近現代史を背景に、そこで人生を切り開こうとした人たちに焦点を当てている。このほかにも『トリニティ』『落花』『美しき愚かものたちのタブロー』は文化を軸に歴史を切り取った作品といえるし、『平場の月』『トリニティ』『マジカルグランマ』は死や老いといったアクチュアルな問題を描いているのなど、今回の候補作はモチーフやテーマに共通点が少なくない。
さらにいえば、年末にミステリーや時代小説のベスト10が発表されるため、出版社は話題作をベスト10のアンケートの〆切間際の9月、10月あたりに集中的に刊行する傾向にあるので、1月選考の直木賞には力作が、7月選考の直木賞は小粒な作品が並ぶことも常態化していたが(第159回直木賞予想を参照していただきたい)、今回は『平場の月』が既に第32回山本周五郎賞を受賞しているように、各作家の中でも傑作が揃っているのだ。
ということで今回も予想が難しいのだが、概観はこのくらいにして候補作を作家名の50音順で紹介していきたい。
なお選考委員は前回と変わらず、浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆきの9名である。
候補作品別・「ココが読みどころ!」「ココがもう少し!」
朝倉かすみ『平場の月』

https://www.amazon.co.jp/dp/4334912567/
2003年に「コマドリさんのこと」で第37回北海道新聞文学賞を受賞、2004年に「肝、焼ける」で第72回小説現代新人賞を受賞した朝倉かすみは、2008年に『田村はまだか』で第30回吉川英治文学新人賞を受賞した後は賞レースから離れていたが、2017年に『満潮』が第30回山本周五郎賞の候補になり、2019年、『平場の月』で第32回山本周五郎を受賞した。直木賞へのノミネートは今回が初だが、『平場の月』が2冠達成なるかが話題を集めており、いきなり最有力の候補になったといえる。
『平場の月』の内容を端的にまとめると、純愛&難病もの。朝倉が「きらら」(2019年2月号)のインタビューで、編集者に「『世界の中心で、愛をさけぶ』みたいなものがやりたい」といって書き始め、「渡辺淳一さんの『阿寒に果つ』と住野よるさんの『君の膵臓をたべたい』」も読んだと発言しているように、『平場の月』のテイストは一昔前に流行した携帯小説、もしくは明治中期に一世を風靡した家庭小説に近い。しかしベタで古臭く思える展開だからこそ、物語を作る朝倉の巧さが際立って感じられるのである。
中学生の頃、いわゆるスクールカーストの上位にいた青砥健将は、クラスメイトの須藤葉子に告白するもフラれてしまった。時は流れ、50歳になり地元・埼玉県の印刷会社に勤務している青砥は、検査で訪れた病院の売店で働く須藤と再会する。それぞれに波乱万丈な人生を送ってきた二人は「互助会」と称して酒を飲む仲になるが、すぐに須藤が末期の大腸がんであることが発覚する。
デス・エデュケーション(死の準備教育)に、5枚のカードに大切なものを書き、それを1枚ずつ捨てていくことで、死に向かう過程で生まれる喪失感を疑似体験する方法がある。『平場の月』を読んで真っ先に思い浮かべたのが、この5枚のカードを使うデス・エデュケーションだった。結婚がゴールでなく、性欲に突き動かされることもない大人の純愛も、須藤が経験するがん治療の実態も(金銭に不安のある須藤が、生活保護を受けて治療費の捻出を考えるなど、凡百の難病ものとは一線を画す生々しさがある)、闘病する須藤を支える青砥の献身も読み応えがあったが、須藤が最後に残そうとしたもの、それを受け取った青砥が何を考えたのかが描かれる終盤には身近な話題だからこそ深い感動があり、誰もがどのように生き、死んでいくのが美しいのかを考えることになるだろう。
『平場の月』は、唯川恵の山本周五郎賞の選評によると
「一回目の投票で選考委員の意見が一致」し「呆気ないほどあっさり」(「小説新潮」2019年7月号)
と受賞作になったようだ。これは作品のクオリティからいっても、貧しくても懸命に生きる庶民を活写した山本周五郎の名を冠した賞という意味でも相応しいといえるが、それが直木賞でも通用するかがポイントになる。
大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』
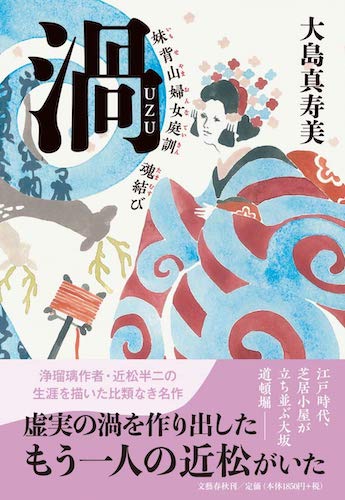
https://www.amazon.co.jp/dp/4163909877/
大島真寿美は、1985年から1992年まで劇団「垂直分布」を主宰し、脚本・演出を担当した。1992年、「春の手品師」で第74回文學界新人賞を受賞。同年、第15回すばる文学賞の最終候補となった「宙の家」を表題作とする作品集で小説家デビューする。初の時代小説となる『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』は、第152回直木三十五賞の候補になった『あなたの本当の人生は』以来、2回目のノミネートである。
藤原鎌足・淡海父子の蘇我入鹿討伐に、大和に伝わる数々の伝説を織り込んだ『妹背山婦女庭訓』は、浄瑠璃作者・近松半二の代表作(松田ばく、栄善平、近松東南、三好松洛との合作)である。本書は、現代まで名作として演じ続けられている『妹背山婦女庭訓』の誕生秘話となっている。
近松門左衛門を敬愛する儒者・穂積以貫の息子として生まれた半二は、幼い頃から浄瑠璃に囲まれて育った。やがて父から門左衛門愛用の硯を譲られた半二は、浄瑠璃作者の真似事を始めるが、成功までの道のりは平坦ではなかった。半二が本格的に活動を始めたのは、門左衛門時代の一人遣いの人形から三人遣いの大型人形にシフトし、人形芝居の浄瑠璃が下火になり歌舞伎の人気が上がっていた節目の時代だった。そのため半二は、人形遣いが起こした騒動に巻き込まれることもあった。しかも弟分だと思っていた並木正三に、デビューも売れっ子になるのも先を越された半二は、なかなかヒット作を生み出せないのに、浄瑠璃を背負う立場になってしまうのである。実家の都合で一人の少女を不幸にしたかもしれないという後悔を抱く半二が、それをバネに『妹背山婦女庭訓』を完成させるまでが中盤以降の読みどころとなる。
おそらく大島が近松半二を主人公にしたのは、劇団を主宰した影響も少なくなかっただろう。初めての時代小説ということもあり、芸道ものとしては特段に完成度が高いわけではないが、浄瑠璃は、過去の名作、同時代に書かれた作品、芝居を作る裏方、応援してくれる観客などが渾然一体となった「渦」の中から生まれ、作者はその「渦」から新作を書き上げているとの芸術論は、実体験がなければ書き得ない輝きと独自性があった。浄瑠璃の人気が下降するなか、名作を出すことで観客を繋ぎ止めようとする半二の作家魂は、出版不況の中で戦っている大島自身が反映されているようにも思えた。
決して悪い作品ではないが、初の時代小説なので“新境地”と好意的に受けとめられるか、“付け焼刃”と批判されるか微妙なところである。森見登美彦『熱帯』が選考委員に支持されなかったことからもうかがえるように、どうも作家は、創作の覚悟や制作秘話、物語をめぐる物語などを書くのは好きでも、ほかの作家が書いた作品はあまり評価しない傾向があるのではないか。『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』も、『熱帯』と似た評価になるような気がしてならない。
窪美澄『トリニティ』
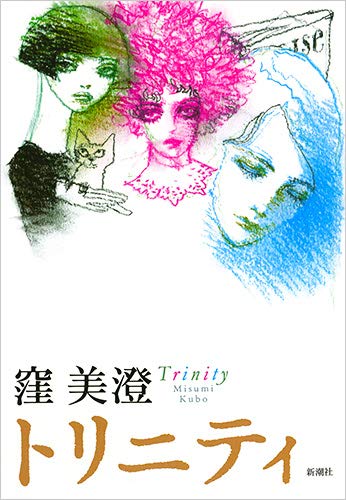
https://www.amazon.co.jp/dp/4103259256/
2009年に「ミクマリ」で第8回「女による女のためのR-18文学賞」を受賞してデビューした窪美澄は、同作を含む連作集『ふがいない僕は空を見た』で第24回山本周五郎賞を受賞、二冊目の単行本『晴天の迷いクジラ』で第3回山田風太郎賞を受賞した。それなのになぜか直木賞とは縁遠く、『じっと手を見る』が2018年上半期の第159回の候補作になったのが初めてで、『トリニティ』は2回目のノミネートである。
タイトルの“trinity”は「三重」「三組」の意味だが、“the Trinity”になると「父」「子」「聖霊」が一体となった存在(三位一体)を唯一神とするキリスト教の教えになる。『トリニティ』は、1960年代に若者文化を牽引した雑誌編集部で働いていた早川朔、佐竹登紀子、宮野鈴子の女三人、鈴子たちの世代、娘の世代、孫の世代へと続く女三代、女性の人生における仕事、結婚、子供の取捨選択の難しさなど、象徴的に“3”を使いながら終戦直後から現代まで、女性の目から見た日本の現代史を紡いでいる。
72歳の鈴子は、精神的に追い詰められブラックな出版社を辞めた孫の奈帆を誘い、イラストレーターとして一時代を築いた朔の葬儀に出掛ける。そこで鈴子は、かつては人気だったが、零落したフリーライターの登紀子と再会。登紀子に興味を持った奈帆は、その人生と、朔、鈴子との関係など長い話を聞いていく。
貧しい家庭に育ち母が苦労して美大に通わせてくれた朔は、潮汐出版が創刊した週刊誌「潮汐ライズ」の表紙を描くイラストレーターに抜擢されるセンセーショナルなデビューを飾る。「潮汐ライズ」には、祖母も母も作家で贅沢な暮らしをしてきた登紀子がフリーライターの草分け的な存在として働いていた。東京下町の佃煮屋の娘だった鈴子は、高校卒業後に潮汐出版に入社し、お茶くみなどの雑用をするOLになっていた。
窪は、今よりはるかに男性中心の社会だった1960年代に、才能を武器に戦いを挑み、新しいライフスタイルを作った朔と登紀子を軸に物語を作っていくが、単純なサクセスストーリにはしていない。「潮汐ライズ」の後、二人の主戦場は新創刊の女性誌「ミヨンヌ」に移るが、ファッション、旅、ショッピングの記事で日本女性に自分らしく生きる楽しさを伝える雑誌でありながら、編集長などの幹部はすべて男性で占められていたエピソードを書くことで、女性向けの情報であっても、それが男性によって“検閲”されている事実を指摘してみせる。さらに編集者になるチャンスを示されながら、お見合いした大手建設会社の社員と結婚し、専業主婦になる道を選んだ鈴子を描くことで、専業主婦も女性が抑圧されている社会に抗っていたことを示したのだ。その意味で『トリニティ』は、男vs女、働く女vs専業主婦といった二項対立ではなく、女性を圧殺するさらに複雑な社会システムの存在に迫った政治ドラマとしても秀逸なのだ。それだけに、1968年10月21日、国際反戦デーの見学に新宿へ行った朔、登紀子、鈴子が、デモ隊にまぎれて男性社会への不満をぶつける場面は、強く印象に残る。
社会の常識や良識へのカウンターとして登場した若者が、いつの間にか権威になり、新たに登場した若手に追い立てられる構図は、芸術だけでなく、ビジネスの世界でも起こりうる。上に立った人間が抱く普遍的な不安、恐怖を表現するためにも、ライバルや若手に追われていく朔と登紀子をもっと丁寧に描いて欲しかったが、そこが駆け足になっておりバランスを欠いていた。第一線から転落する朔たちを描いていれば、奈帆が上の世代からバトンを受け取るラストがもっと印象深くなったように思え、その意味でも残念でならない。
朔は大橋歩、登紀子は三宅菊子、「潮汐ライズ」は「平凡パンチ」、「ミヨンヌ」は「an・an」をモデルにしており、実在した人物は小説の素材なので改変するのは作家の自由だが、歴史時代小説における時代考証と同じで、窪のアレンジも選考員によっては否定的な評価をされる危険性がある。
澤田瞳子『落花』

https://www.amazon.co.jp/dp/4120051749/
澤田瞳子は、第153回の『若冲』、第158回の『火定』に続き3回目の直木賞ノミネートとなる。前2回とも強く推す選考委員もいたようだが、惜しくも受賞を逃した。澤田の不幸は、特に古代史ものに顕著だが、一般的な日本人には馴染みのない時代を最新の歴史研究を踏まえて書いているので、純粋にエンターテインメントとして楽しむのであれば何の問題もないが、作品を“評価”するにはそれなりの予備知識が必要なことである。例えば織田信長であれば、家臣を使い捨てにする苛烈な武将との共通認識があるので、第160回直木賞の候補になった垣根涼介『信長の原理』のように、冷酷になった理由を少し目新しくしただけで独自の信長を創出したように見える。ただ『落花』の主人公の寛朝は、何をした人物かすぐに答えられる読者は少ないだろう。寛朝が朝廷の命を受け東国に向かい、調伏により平将門の命を奪ったとされる僧だと知っていないと、そのイメージを覆した本書の仕掛けや凄さは十分に伝わってこないのである。
宇多天皇の孫で仁和寺の僧・寛朝は、11歳の時、「至誠の声」で朗詠する豊原是緒に魅了される。節を付けて経典を歌う梵唄を得意とする寛朝は、22歳の時、行方不明になった是緒が東国にいると聞き、その教えを受けるため京を旅立つ。従者の中には、音楽で出世をするため、是緒が持つ伝説の琵琶を手に入れたいと考える千歳もいた。折しも東国では、平将門が困っている人を助ける侠気ゆえに同族との争いを拡大させていた。やがて寛朝たちは、将門と朝廷との争いに巻き込まれていく。
『落花』には、梵唄、雅楽など様々な音楽が出てくるが、その描写は素晴らしく、恩田陸の第156回直木賞受賞作『蜜蜂と遠雷』に勝るとも劣らない。
物語は、将門が起こす戦乱と、その渦中にあっても梵唄や琵琶を極めようとする寛朝、千歳を対比しながら進んでいくが、戦争を悪、音楽(文化)を善とするような単純な構図にはなっていない。澤田は、馬のいななきや兵士の声といった戦場に立ち込める音に心ならずも感動してしまう寛朝や、伝説の琵琶を手に入れるためなら手段を選ばない我欲によってはからずも戦争の引き金を引いてしまう千歳を通して、争いを浄化する力にもなれば、果てしない欲望を刺激し騒乱の種にもなる文化の両義性を描いてみせたのである。
考え方や文化の違いが現在でも紛争の原因になっていることを踏まえるなら、『落花』は決して過去の特殊な事件を描いているのではなく、普遍的なテーマを読者に突き付けたといえるだろう。
『落花』のネックは、『火定』の直木賞の選評(「オール讀物」2018年3月号)に
「この作品のテーマを象徴する〈火定入滅〉の思想は大乗仏教のもので、この時代にはまだふさわしくないのではないかという指摘には『う~ん』と唸ってしまいました」(宮部みゆき)
とあるように、自称仏教に詳しい選考委員が、時代考証の問題点を批判し、小説の評価まで議論が進まない危険があることだ。もう一つは、山本周五郎賞を『平場の月』と争い敗れていること。選考委委員が「周五郎賞の選考委員は分かっていない。この作品は直木賞にこそ相応しい」と判断するか、「『平場の月』に負けた作品を議論しても仕方ない」となるかで結果が変わってくるように思える。
原田マハ『美しき愚かものたちのタブロー』

https://www.amazon.co.jp/dp/4163910263/
大学卒業後、キュレーターなどを経て作家になった原田マハは、美術を題材にした小説に定評がある。過去に直木賞の候補になった『楽園のカンヴァス』(第25回山本周五郎賞受賞)、『ジヴェルニーの食卓』、『暗幕のゲルニカ』もこの系譜に属しており、今回の『美しき愚かものたちのタブロー』も、松方幸次郎が買い集めた膨大な西洋美術のコレクションがたどった数奇な運命と、松方の遺志を継いだ人々によって国立西洋美術館が建設されるまでを追っている。
『美しき愚かものたちのタブロー』は、美術史家の田代雄一(モデルは矢代幸雄)と文部官僚の雨宮が、モネ「睡蓮」の展示で有名なオランジュリー美術館を見学している場面から始まる。総理大臣・吉田茂の命を受けた二人は、敵国の資産としてフランス政府に没収された松方コレクションの返還交渉を行うことになっていた。ヨーロッパに留学した時、松方に購入すべき美術品をアドバイスした過去がある田代は、今回の交渉に特別な思い入れがあった。ここから物語は、第一次大戦中に文化のパワーを痛感し、モノクロ写真でしか西洋美術を見たことのない日本の若者のため、私財をなげうって美術品を購入する松方や、自分が苦労して美術史を学んだがゆえに松方の理想に共鳴する田代の動向、そして第二次大戦下もフランスに留まりコレクションを守った日置釭郎の知られざる活躍や戦後の返還交渉の行方など、時系列をカットバックしながら進んでいく。
美術が専門の原田だけに、圧倒的な知識と情報量で松方コレクションの成立と、没収されたコレクションが日本に帰国するまでのドラマをダイナミックに描いている。ただ、ある程度、美術の知識があるとよく知られたエピソードばかりで、特に斬新な視点があるわけでもないので小説としての面白さが十分に伝わってこないのだ。国立西洋美術館60周年、それに伴う「松方コレクション展」に間に合わせるためか、連載にさほど手を入れないまま単行本にしたようで、同じ説明が何度も繰り返され冗長だったのも否めない。また松方が亡くなったのが1950年、関係者の多くが存命だということもあってか、松方はひたすら文化後進国の日本を憂えて美術品を購入した偉大な人物とされており、“負”の部分がまったくないので深さが感じられなかった。最も気になったのは、本物の美術を届けるという使命を抱いた、いわばディレッタントな啓蒙家たちが物語の中心にいるので、松方コレクションがどれほど戦後の日本人に勇気を与え、後世の芸術家たちがどれほど影響を受けたのかという視点が少なく、押し付けがましく感じたことである。これは同じ時期に刊行された中島京子『夢見る帝国図書館』が、少ない予算に苦しみながらも帝国図書館の発展に尽力した職員と、無料で使える帝国図書館に通い近代文学史に名を残すまでになった作家たちの物語を大胆なフィクションを交えて描き、図書館がどれほど“夢”ある場所なのかを示したのと好対照である。
今回の候補作は「各作家の中でも傑作が揃っている」と書いたが、『美しき愚かものたちのタブロー』は原田のほかの作品と比べても、ほかの候補作5作と比べても一段落ちるが、情報小説としては優れているので、読むと「松方コレクション展」(2019年9月23日まで)に行きたくなるだろう。
柚木麻子『マジカルグランマ』

https://www.amazon.co.jp/dp/4022516046/
今回は最年少の柚木だが、第150回の『伊藤くんA to E』、第151回の『本屋さんのダイアナ』、第153回の『ナイルパーチの女子会』(第28回山本周五郎賞受賞)、第157回の『BUTTER』に続く5回目の直木賞候補は最多となる。第157回の直木賞予想では『BUTTER』を酷評したが、『マジカルグランマ』は本当に面白かった。
アメリカ映画において、白人の主人公を助けるため、古くから伝わる知恵や神秘的な力を使う黒人キャラクターは“マジカルニグロ”と呼ばれる。“マジカルニグロ”は類型的な黒人として設定、描写されることが多く、知らず知らずのうちに人種差別を助長しているともいわれる。タイトルの『マジカルグランマ』は、その老婦人版で、世間が押し付けてくるイメージとどのように向き合うかがテーマの一つになっている。
正子は、高校卒業の直前、友人の陽子に誘われ大女優・北条紀子の妹役オーディションに合格し女優になった。しかし鳴かず飛ばずのまま映画監督の浜田と結婚して引退、広い洋館で暮らし始める。時は流れ、74歳になった正子は、離婚はしていないが夫とは4年も口を聞いていない冷めた関係になっていた。自活の道を探していた正子は、シニア専門の芸能事務所に登録。今も姉と慕う紀子のアドバイスで外見を変えた正子は、CMで人気俳優と共演するほどブレイクしてしまう。このまま老婦人のサクセスストーリが続くと思いきや、物語は急展開する。同じ敷地に住んでいるのに夫の死に気付かず、葬儀で冷淡な発言をした正子の好感度は下がり、事務所との契約を打ち切られてしまうのだ。追い打ちをかけるように夫に多額の借金があることが発覚、売りに出そうと考えていた洋館も解体に1000万円もの費用がかかることが判明するのである。
窮地に立たされた正子は、夫のファンで映画監督志望だという杏奈、いつも家の庭で娘と遊んでいる明美、自宅にゴミを貯め込んでいる近所のおじさんらと協力し、洋館を使ったお化け屋敷の運営を始める。意外な展開をたどる小説はかなり読んできたつもりだが、夢をかなえた老婦人の話が、おばけ屋敷の経営にシフトするとは想像もしていなかった。終盤にも正子の回想としか思えなかった描写が伏線となり、どんでん返しとしかいいようのない再度の急展開があるので、最後までハラハラ、ドキドキが満喫できるはずだ。
純粋にエンターテイメント小説として優れている『マジカルグランマ』だが、老後をどう生きるべきか、その時、近所の人たちや若い世代とどのような関係を結ぶべきなのかといった今日的な問題もちりばめられている。“マジカルグランマ”役者だった頃は、何の疑問もなく世間が求める“かわいいおばあちゃん”を演じていた正子だったが、お化けを演じることで、そのことに疑問を持つようになる。ただ柚木は“マジカルグランマ”を頭から否定するのではなく、誰もが他人の前では演技をしているのだから、どのように振る舞うべきなのかを自分で考えるべきではないかと問い掛けており、テーマも腑に落ちるものだった。
とても楽しめた本書だが、正子たちの計画がすべて順調に運び、登場人物全員が収まるべきところに収まる幕切れなので、ご都合主義で予定調和だという批判を受けるようにも思えた。
ズバリ予想! 本命は? 対抗は?
以上を踏まえ、第161回直木賞を予想してみたい。
本命は、窪美澄『トリニティ』。前回受賞の真藤順丈『宝島』は、沖縄問題という政治ドラマを一級の娯楽小説に仕立てていたが、トリニティも女性を抑圧する社会という政治問題をベースにした物語であり、選考委員が前回と同じことを考えても受賞の確率は高い。『宝島』くらいの分量を使い、全盛期を過ぎた三人のその後を描いていれば自信を持って推せたが、中盤にやや消化不良なところがあり、そこが懸念材料である。
対抗は、柚木麻子『マジカルグランマ』と迷ったが、朝倉かすみ『平場の月』にしたい。ありきたりのエピソードをここまでの完成度にした手腕が評価されるか、ベタな話のままと酷評されるか、山本周五郎賞とW受賞が相応しいとされるか、まだ直木賞には早いとされるか、受賞してもしなくても選評が楽しみな作品だ。そのため穴は柚木麻子『マジカルグランマ』となる。物語とテーマの融合、ハッピーエンドを排除しながらも希望を感じられるラストを作ったところなどは『トリニティ』の方が確実に上だ。ただ現実の社会が厳しさを増しているだけに、明るく前向きな『マジカルグランマ』の方が好意的に評価される可能性はあるし、功労賞の要素を加味すれば柚木が有利なのは確実だ。
選考会は、2019年7月17日、築地・新喜楽で開催される。結果を楽しみに待ちたい。
<筆者・末國善己 プロフィール>

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』などがある。
初出:P+D MAGAZINE(2019/07/12)





