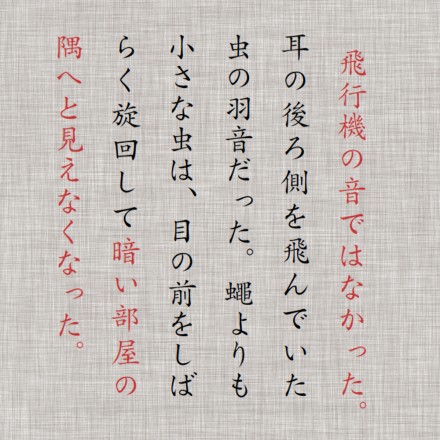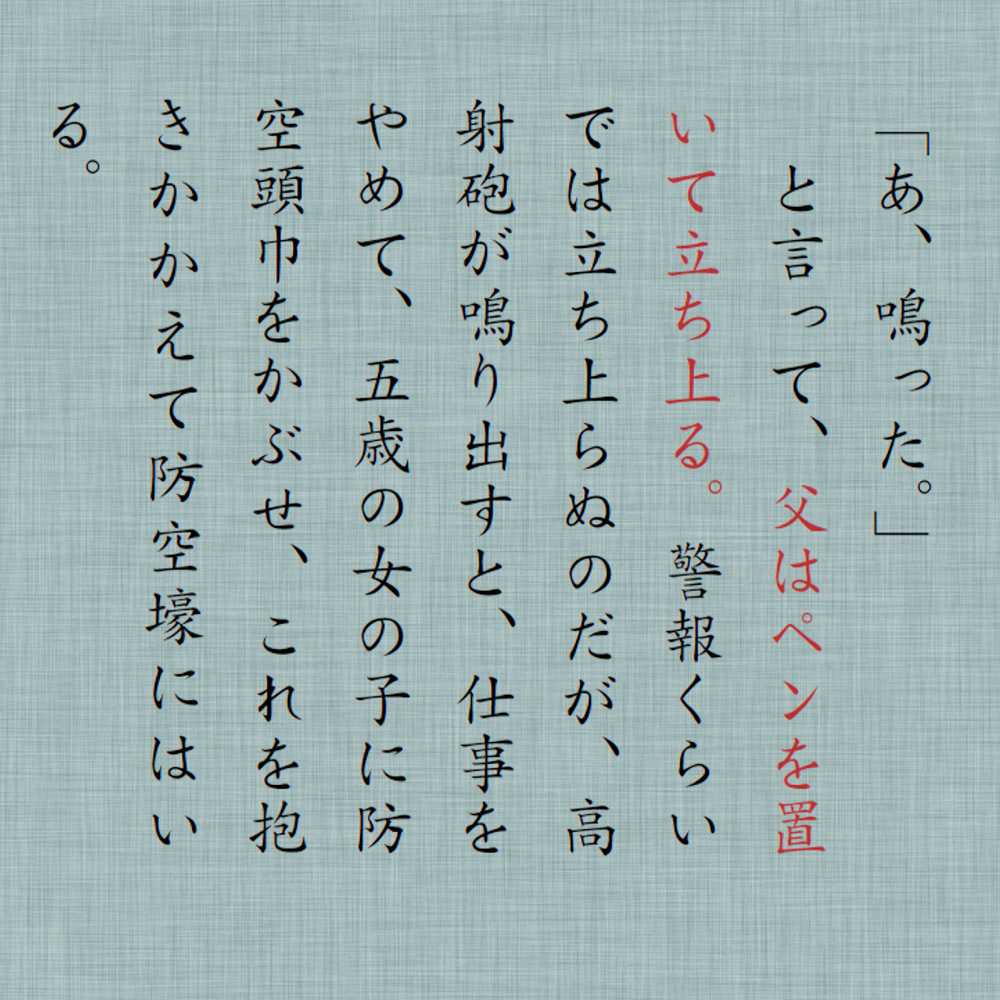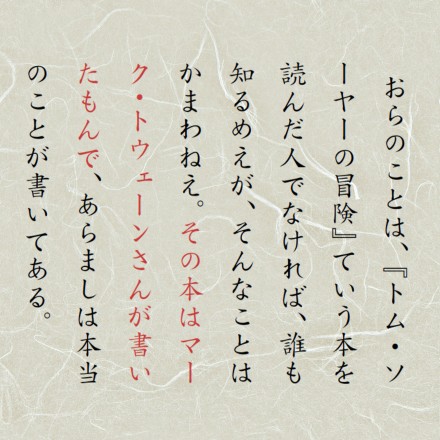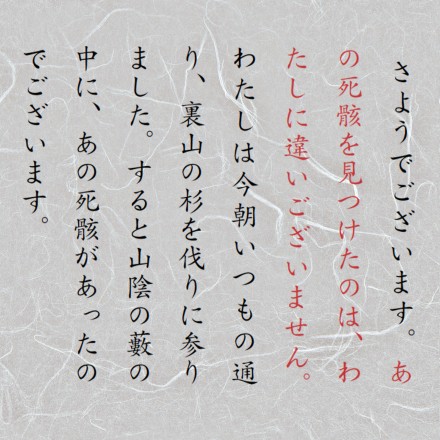小説は書き出しが命!昭和文学に学ぶ冒頭文の「反則テクニック」5選。
3. とりあえず耳を澄ませよう(村上龍『限りなく透明に近いブルー』)
「目覚め」や「誕生」と同じように、「音」もまた〈無〉から〈有〉を作り出す存在。皆さんは、ビートルズの「ハード・デイズ・ナイト」という楽曲はご存知ですか? この曲の冒頭でかき鳴らされる「ジャーン!」というギターの音は、これ以上なくシンプルながらも、ロック史に名を残すイントロとしていまだに愛され続けています。
小説でいえば、綿矢りさの芥川賞受賞作『蹴りたい背中』の冒頭文「さびしさは鳴る。」が例として挙げられます。開始のシグナルとして「音」を用いることによって、「アテンション・プリーズ」から始まる機内アナウンスのように、読者の注意をページのうえに集中させることができるのです。
村上龍の衝撃的なデビュー作『限りなく透明に近いブルー』の書き出しは、まさにそのような「音」の効果を紙面上で巧みに使っています。「飛行機の音ではなかった」という書き出しは読者に不思議な違和感を与えますが、やがてその音は一匹の蝿に姿を変え、「暗い部屋の隅へと」見えなくなっていきます。
この冒頭文のなかで、「聴覚」から「視覚」への切り替えがきわめて自然に行われているのがわかるでしょうか? このように、ぼんやりとしたイメージから少しずつリアルな姿を立ち上がらせる手法のことを、批評家のイアン・ワットは”delayed decoding”(解読の遅れ)と呼んでいます。最初からくっきりはっきりした姿を提示しないほうが、よりリアルな体験へと読者を誘うことがあるのです。
4. 書き手の存在をあぶりだせ!(太宰治『お伽草紙』)
お笑いの分野で「楽屋オチ」と呼ばれる手法がありますね。例えば、コントの設定を演じている筈の芸人さんが、「あと1分でこのネタ終わらせなくちゃいけないから」と急にネタの尺のことを話し始めたら、これは楽屋オチ的な手法といえます。虚構(フィクション)の層のなかに、自己言及的に現実の層が組み込まれることによって、「物語」の虚構性が強調されることになるのです。
このように「物語」の構造を入れ子状にさせる表現手法のことを「メタフィクション」と呼びますが、その例としてアメリカ文学の古典のひとつ、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』(西田実訳、岩波文庫)から冒頭文を紹介します。
主人公であるハックルベリー・フィンの一人称で語られているこの冒頭文のなかで、ハックは彼が作者であるマーク・トウェインによって造り出された虚構内存在であることを自ら暴露しています。フィクションの作り手である「書き手」の存在をあぶりだすこと。これもメタフィクションの方法のひとつです。
さて、「恥の多い生涯を送ってきました。」(『人間失格』)、「メロスは激怒した。」(『走れメロス』)など、インパクトのある冒頭文で知られる太宰治。そんな太宰が戦時中に発表した『お伽草紙』の前書きは、空襲警報のなかで執筆をする「父」の姿から開始されます。
父親は防空壕のなかで五歳の娘をなだめるために、「ムカシ ムカシノオ話ヨ」とおとぎ話を語りはじめるのですが、物語の外部に位置する「戦争」という状況がメルヘンチックなはずの物語のなかにも影を落としていくという、メタフィクションの強みを存分に活かした構成になっています。
5. いっそのこと嘘をついてみよう(芥川龍之介『藪の中』)
そもそも小説で描かれる内容はほとんどが虚構の出来事であるのに、読者は作品に没入すればするほど、語り手のいうことを一語一句「そんなことがあったのね」と真に受けてしまいがちだったりもします。なので、語りの内容に食い違いがあったり、非現実的な飛躍があったりすると、「こんな嘘っぱち、読んでられるか!」と憤ったりする人もいるのです。
しかし、ときにそんな読み手からの信頼を逆手にとるのが小説家という職業。たとえば、「ここにあることは、まあ、だいたいその通り起った。とにかく戦争の部分はかなりのところまで事実である。」そんな書き出しから始まるカート・ヴォネガットの『スローターハウス5』は、作者自身の実際の戦争経験をフィクションとして再構成しながら、UFOに連れ去られたり、時間旅行をしたりといったブッとんだSF要素を盛り込んだ大傑作です。
文学批評の世界では、このような語り手は「信頼できない語り手」と呼ばれます。「本当の話なんだけど」と切り出してみせながら、事実と異なることを語る場合の他にも、語り手自身の記憶に欠落があったり、なにか特定の話題に関して口を閉ざし続ける場合など、「信頼できない語り手」のバリエーションはじつに様々です。
昭和の文芸作品で「信頼できない語り手」を登場させた一番の例はなんといっても芥川龍之介の『藪の中』。ある藪の中で発見された男の死体をめぐって、7人の男女が証言をするのですが、語られる内容は食い違いだらけ。読者は「語り」の背後にあるであろう隠された真実を嗅ぎ回るうちに、豊かな解釈をめぐらせることになるのです。
「完璧な書き出し」は存在しない!?
書き出しの文章ひとつとっても、文学作品には様々なテクニックが隠されていることがお分かりいただけたでしょうか?
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」といえば、村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』の有名な冒頭文ですが、文章で思いのすべてを伝えきることなどできないからこそ、文学者は様々なテクニックを補助線にして「完璧」に近づこうとしているのかもしれませんね。
皆さんも、「伝え方」に悩んだ時には過去の名作を手にとってみてください。その冒頭を読むだけでも、伝え方のヒントが見つかるかもしれませんよ?
初出:P+D MAGAZINE(2015/12/17)
- 1
- 2