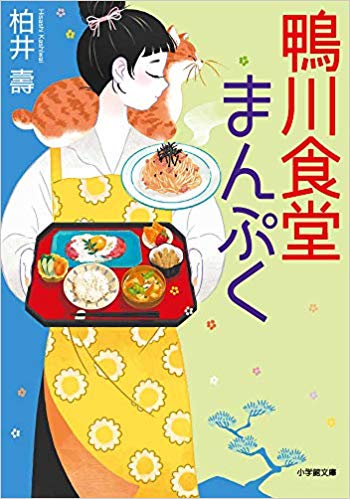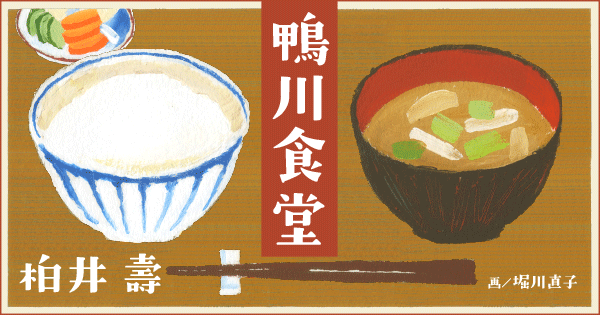「鴨川食堂」第38話 チキンライス 柏井 壽

つかれた体に、ほっと一息。どうぞ召し上がれ。
第38話 チキンライス
「そういうものなんですか。てっきりお店をやめてしまったものと決め込んでいました」
「テナント料が折り合わなんだ、っちゅうことは続ける気持ちがあったという表れなんですわ。さぁ、ほしたらどこで代わりの店を捜すかとなりますわな。となると、もっと安い賃料の店を捜すはずです」
「それとのう調べてみたんですけど、東京のお店の家賃てめっちゃ高いですねぇ。びっくりしましたわ。京都も高いと思うてましたけど、ケタが違いますやん。その分お客さんの数も多いんやろけど」
こいしが横から言葉をはさんだ。
「わしやったらどうするやろ。そう考えて思い付いたんは故郷です。ハルさんは中国の生まれやったそうですけど、日本を離れることはないんやないかと思いました。子どものころに家族で日本に移住しはったんやから、それほど中国には思い入れがない。それより最初に日本で移り住まはった和歌山で店を開こうとしはったんやないかと推測しました。そこで思い当たったんが〈南海飯店〉っちゅう屋号ですわ」
「和歌山と南海がつながるんですか?」
香織が身を乗りだした。
「関東のかたにはなじみが薄いかもしれまへんけど、和歌山には南海電鉄っちゅう私鉄がありますねん。その南海かも分かりまへんけど、わしは海南(かいなん)市っちゅう地名に目を付けましたんや。海南をひっくり返したら南海ですやろ」
タブレットの地図アプリを立ち上げて、流が海南市を指さした。
「お父ちゃんは元刑事やさかい、推理するのが得意ですねん」
「こいし、余計なこと言わんでええ」
流が横目でこいしをにらんだ。
「おっしゃるとおり、南海電鉄というのは聞いたことがあるような気もしますが、海南市という地名は存じませんでした」
「ここまでたどり着いたら、あとは現場捜査だけです。と言うのもネット検索をこいしがしてくれよったんですが〈南海飯店〉っちゅう店には行き当たらなんだんです。わしの勘が間違うとらなんだら、かならず見つかるはずやと思うて、海南市へ行ってきました」
「ありがとうございます。わたしにはとても思いつかないお話です」
「海南市っちゅうのが、思うたより広いとこでしてな、それだけは誤算でした。うろうろ歩き回っとったら、なんぞヒントが見つかるやろと思うとったんですが甘かったですわ。こら、ちょっと腰据えんとあかんなと思うて、ホテルを捜しましたんやが、頃合いのとこが見つかりまへんでして、なんとか一軒だけ予約できたんが幸いするんでっさかい、人間っちゅうもんはほんまに不思議ですわ。海っぺりに建ってるホテルですんやが、駅にもインターにも近ぅて便利なとこにありますねん。近所の居酒屋でそれとのう訊き込みをしました」
「お父ちゃんにとって訊き込みはお手のもんです」
こいしが口をはさむと、流が目でそれをとがめた。
「海南市というぐらいですから、海辺の街なんですね」
「海辺なんやが山のほうにも伸びとるんです。海っぺりからずーっと東のほう、ここに小さい神社があるんでっけど、ここへ行ってみたらどうや、て居酒屋のお客さんが教えてくれはったんで行ってみました」
「〈杉尾(すぎお)神社〉。この神社がなにか?」
流がディスプレイに神社の写真を映しだして見せると、香織はけげんそうな顔つきで首をかしげた。
「ただひとつ、あなたが覚えてはったヒント、──腹の黒いのはなおりゃせぬ──はこの神社の言い伝えにつながりますねん。くわしいことは省きまっけど、ここは〈お腹の神さん〉で有名なとこらしいて〈おはらさん〉て地元の人は呼んではるんやそうです。わしが居酒屋で──腹の黒いのはなおりゃせぬ──て節をつけて唱えたら、すぐに周りのお客さんが反応しはりましたさかい、地元ではよう知られとるみたいです」
「この神社とあのおばちゃん、いやハルさんがつながっていたんですか」
香織がディスプレイに目を近づけた。
「ハルさんの印象に強ぅ残ってたいうことは、この神社の近所に住んではったんやないかと思うて行ってみましたんや。けっこう急な石段を昇った上に神社が建っとるんやが、ええ佇まいでした。この〈おはらさん〉がハルさんの居場所を教えてくれはったんです」
「神さまのお告げかなにかですか?」
「そんなようなもんです。お参りを済ませて石段を降りはじめたら、赤い看板が目に入りました。よう目をこらしてみたら〈なんかい飯店〉て読めました。これはもう絶対間違いない。そう確信してその店に行ったっちゅうわけです」
「なんだかテレビドラマみたいですね」
「ときどき現実がドラマを超えることがあります。それを引き起こすのは人の思いっちゅうやつですわ。あなたが十五年前のチキンライスをもういっぺん味おうてみたい、と思わはった、その力が強かったんですなぁ。そしてその思いは料理を作ったハルさんもおんなじやったんです。〈なんかい飯店〉にはねぇ、〈チキンライス〉っちゅうメニューがありましたんや。最初はハルさんから話を聞いて、と思うとったんですが、なんにも余計なこと言わんと〈チキンライス〉を注文しましたんや。そしたらハルさんが、ふつうのチキンライスと違うけどええか、て訊かはりましたんで、もちろんそれでええ、て言うかそれを食べとうて京都から来たんやて言うたら、びっくりしはりましてな。それから話が弾んだっちゅうわけですわ」
「今いただいたのが、その〈なんかい飯店〉の〈チキンライス〉なのですか?」
「正確に言うとちょっと違います。お店で出してはるのは鶏肉がライスの上に載ってますねん。〈海南鶏飯〉やとか〈シンガポール風チキンライス〉やとか言われとるもんに近い料理でした。さいぜんお出ししたんは、ハルさんがあなたのために作らはった十五年前のもんとおんなじレシピです」
「〈シンガポール風チキンライス〉て実際にあるんですか? ハルさんはそれをアレンジして作ってくれたということなんですか?」
香織が矢継ぎ早に訊くと、流がこっくりとうなずいた。
「わしらはチキンライスていうたら、ケチャップ味のを思い浮かべますけど、アジアでは鶏の炊き込みご飯っぽいほうが主流みたいです。と言うよりケチャップ味のチキンライスは日本独特のもんなんですわ」
「そうだったんですか。チキンライスと言えば赤いものだと思いこんでいましたから、意表を突かれた感じでした」
「あなたが好物やて言うたはったんは、その赤いチキンライスやと分かってたはずやのに、なんでハルさんはこんなチキンライスをあなたに食べさせようとしはったか分かりますか?」
流が訊くと、香織はおし黙ったままで、ゆっくりと首を横に振った。
「うちもなんでか分かりませんでした。せっかくメニューにない好物を作ってくれはったのに、別もんやったら嬉しないですよね。ケチャップがなかったんやろかと思うてました」
こいしがそう言うと、即座に香織はそれを否定した。
「ケチャップはありましたよ。それもかなり大きな缶に入っていて」
「こんな缶と違いましたか?」
流がディスプレイを香織に向けた。
「そうです、そうです。こんな缶でした。これも〈なんかい飯店〉にあったんですか?」
大きく目を見開いて香織が訊いた。
「これは〈ハグルマケチャップ〉いうて、和歌山で作っとるんですわ。ハグルマのロゴマークは南海電鉄のもんやったんやそうです。ハルさんは子どものころから、このケチャップに慣れ親しんではったんでしょうな。関西と違うて、関東の中華屋はんはケチャップを甘酢にしてよう使うと聞いて、このケチャップを使うてはったんやと思います。酢豚やとか天津飯にもケチャップをよう使わはります。せやから関西の人間が東京で天津飯食うたら、ちょっとびっくりしますねん。関西の天津飯っちゅうたら、たいてい塩味ベースのスープ餡でっさかいにな。人によっては、こんな出来損ない食えるか、て言うて怒って帰る人もあるんやそうです。天津飯っちゅうたらこんな味や、て思いこみがきつ過ぎるんですやろ。チキンライスもおんなじですわ」
流が意味ありげな視線を香織に向けた。
「ひょっとしてハルさんは……」
眉根を寄せて、香織は思いを巡らせている。
「問わず語りっちゅう言葉をご存じでっか?」
流が訊いた。
「なんとなく」
「まさにそれでしたんや。〈なんかい飯店〉でチキンライスを食い終わったら、ハルさんが感想を訊いてきはったんで、話を振ってみましたんや。これも旨いけど、ちょっとケチャップ味も欲しいなぁ、て。正直そう思うたんですわ。そしたらハルさんがこう言わはったんです。むかしいっぺんだけそういうのを作ったことがあるけど、二度と作らんて決めたんや、て。ほかにお客さんもやはらへんし、詳しいに訊いてもええかて言いました。そしたらハルさんが、十条にあった〈南海飯店〉の写真を見せてくれはりましてな、十五年前の話をしださはったんです。わしも最初はあなたの話をしよう思うたんでっけど、黙って聞くことにしました」
流がコップの水を飲みほしてひと息入れた。
「ハルさんもちゃんと覚えてはったんやて聞いて、なんやせつないなぁ思いました」
こいしが流と香織に茶を淹れた。
「〈南海飯店〉の常連客に若い女の子がおって、娘のように思うてた。その子が彼氏を連れて来て、良かったなぁと思うてたら、次の日池袋のデパートで、その男が別の女性と買い物してるとこを偶然見つけた。最初は姉さんか妹かと思うたけど、手ぇつないでベタベタしてる。高そうなブランドバッグを買うて、支払いはその女性がしてた。よっぽど文句言おうかと思うたけど、もうちょっと様子を見ようと思うてあとを付けたら、ホテル街のほうにふたりで歩いて行った。ふた股かけてるのか、それともホストかなんかの仕事をしてて、女性に貢がせてるのか、どっちにしてもええ話やない。けどそれをそのまま常連客の女の子に伝えてええもんかどうか、迷うに迷うたけど、結局よう言いだせんかった。その子がどんなに傷つくか分からん、っちゅう思いと、もうひとつは信じてもらえんやろという思いもあって、見たままのことは言わんかったけど、別れたほうがええとだけ言うてしもた。結果的にそれが中途半端なことになってしもて、それ以来その女の子は店に来んようになった。後悔してもし切れんのや、とも言うてはりました」
流がそう話すのを、香織は目に涙をため、うなだれて聞いている。
「肝心のチキンライスでっけどな、最初はあなたの好物のケチャップ味のもんを出そうと思うてはったんやそうです。そして機嫌ようなったところで話を切りだそうと。けど、はたと思いつかはったんが、さいぜん食べてもろたチキンライスです。思いこみはあかん、そう伝えとうて、シンガポール風チキンライスに急遽(きゅうきょ)切り替えはった。あなたが思うてるような男性やない。ぜんぜん別の面がある、そう伝えたかったんやそうです。ところがそこでまた迷いが出てしもた。あなた好みのケチャップ味を鶏肉だけには付けておこうと。折衷案ということですわな。まるっきり別のもんやとあなたが可哀そうやと思わはった。ご自分では変な親心が出てしもたて言うてはりました。結果としてあなたに伝わらなんだだけやのうて、気まずいことになってしもた。なんであんなことしたんやろ。あれやったら、見たまま、ありのままを話したほうがよかった。そう後悔してるていうことでした。複雑なような単純なような、人の気持ちっちゅうのは不思議なもんですなぁ」
「では、ハルさんにはわたしのことは?」
香織が訊いた。
「なんにも言うてまへん。ハルさんの問わず語りっちゅうか、ひとり語りを黙って聞いとっただけです。初めてのお客さんに余計な話をしてしもた、て最後に謝ってはりましたけどな」
流が首をすくめた。
「きっと十五年間、ハルさんもそのことがずっと引っかかってはったんやろねぇ。誰かに言いとうてたまらんかったんやわ」
こいしがしんみりとした口調で言うと、香織は深いため息を吐いた。
「あのときそのことに気付いていれば、大金をだまし取られずに済んだんですよね」
香織は悔しそうに唇を嚙んだ。
「人間っちゅうのは、そないうまいこと行かんもんです。人をだますより、だまされるほうがよろしいがな。無責任な言い方に聞こえるかもしれまへんけど」
流の言葉にこいしが大きくうなずいた。
「そんなことがあって、時間はかかったけど、結果的にご両親にはお金を返せたんやし、ええ人もできたんやし、よかったんと違います? きっとこれからたくさんええことがある思いますよ」
「なぐさめていただいてありがとうございます。済んでしまったことは、もうもとに戻せないんだから、悔やんでもしょうがないですね。これからの人生をたいせつにしないと」
香織は自分に言い聞かせている。
「またお作りになるようなことは無いやろと思いますけど、いちおうレシピを書いときましたんで、参考にしてください」
こいしがファイルを差しだした。
「ありがとうございます。これですっきりしました」
晴れやかな顔で香織がそれを受け取った。
「わしも今回はええ勉強さしてもらいました。思いこみにはたえず気ぃ付けてんとあかんのやと。ついつい人間は一面だけを見て決めつけまっけど、別の見方もせんといかん。そう思うてはおるんやが、現実にはなかなかそうはいかんもんや。それともうひとつ。時間というもんはえらいもんや、ということにも気づかせてもらいました。あなたは十五年かけてリセットしはった。長いと言うたら長いけど、人生八十年とも九十年とも言われる今の時代やったら、大した時間やないんですわな」
「そう言っていただけると、いくらか気が休まります。二度とおなじ失敗をしちゃいけませんけどね。ほんとうにありがとうございました。前回のお食事代と合わせてお支払いをさせてください」
「うちは探偵料も食事代も特に決めてませんねん。お気持ちに見合うた分をこちらに振り込んでください」
こいしが折りたたんだメモ用紙を渡した。
「承知しました。帰りましたらすぐに」
香織がメモを財布にしまい込んだ。
「気ぃつけてお帰りくださいや」
店を出た香織の背中に流が声をかけた。
「ありがとうございます」
向き直って、香織がふたりに深々と一礼した。
「しあわせになってくださいね」
「はい」
こいしの言葉に香織は満面の笑みで応え、正面通を西に向かって歩きだした。
「香織はん、忘れもん」
流が白い封筒をひらつかせている。
「はい?」
香織が立ちどまった。
「〈なんかい飯店〉の地図。住所と電話番号も書いときました。土日はお休みしてはりますさかいな」
流が封筒を香織に手渡した。
「ありがとうございます」
拝むようにして受け取って、香織がゆっくりと歩きだした。
見送ってふたりは食堂に戻った。
「ハルさんに会いに行かはるんやろか」
「決まってるがな。新しい彼を連れてあいさつに行きとうて、チキンライスを捜してはったんやさかい」
「やっぱりそういうことやったんか」
「ある意味では、香織はんにとってチキンライスてなもん、どうでもよかったんや。ハルさんとの接点がそれしか思い浮かばなんださかい、それを捜してはった」
「どうでもええ食を捜してたていうわけなんか?」
こいしが気色ばんだ。
「そんなこわい顔せんでもええ。言葉のあや、っちゅうやつやがな。どうでもええ、というのはちょっと違うかな。どんなチキンライスでもよかった、て言い換えとくわ。食いもんっちゅうのはそういうもんなんや。人生の曲がり角で出会うた食いもんのことは一生記憶に残る。食そのもんの記憶は飛んでしもても、それを食べたときの思いは死ぬまで忘れん。おかしな言い方になるかもしれんけどな、それをもういっぺん食うことで、そのときの気持ちをリセットできることもある。複雑な気持ちもあるやろけど、香織はんは前を向いて歩こうと決めはったんや」
流が仏壇の前に正座した。
「だますよりだまされるほうがええ。お母ちゃんもそう思う?」
こいしが写真の掬子に問いかけた。
「人間はな、だましだまされ生きていくもんや。なぁ、掬子」
「お母ちゃんもずっとだまされ続けてはったんかな」
こいしが横目で流を見た。
「神さんに誓うてそんなことはあらへん」
顔を引きしめて流が手を合わせる。
「そうなんやて。よかったなぁ、お母ちゃん」
こいしが線香をあげた。
第39話は「STORY BOX」2020年1月号でお楽しみください。