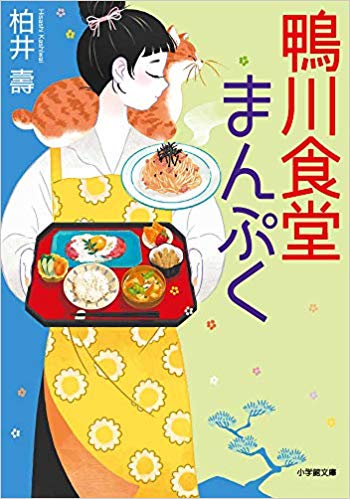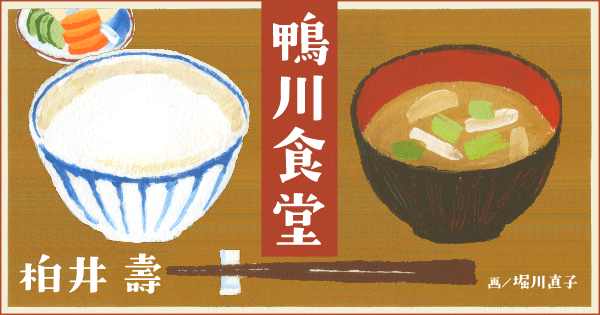「鴨川食堂」第40話 ハムカツ 柏井 壽

あなたが探したい、思い出の食べものはなんですか?
第40話 ハムカツ
ハマグリはたしかマリネと言っていたが、どんなマリネ液に漬けたのか。淡く桃色に染まっているから、ベリーを使ったのか。そしてまたしても油が分からない。オリーブオイルでないことだけはたしかだが。ピリッと辛い香辛料はなんだろう。食べたことのない味わいだ。そうだ。ハーブを混ぜなきゃ。細かく刻まれたハーブはおおよそ分かる。イタリアンパセリ、フェンネル、タイム、オレガノ。ざっとそんなところだろう。だが、正直に言うならこのハーブは要らない。ほんの一年ほど前だったらこういう趣向を喜んだものだが、今の自分なら余計なものは足さない。マリネしたハマグリの旨さをストレートに味わいたい。
などと偉そうな口をきいているが、これまでさんざん自分でもやってきたことで、今でもしばしばこういう足し算をしている。これはある意味で料理人の性(さが)だとも言える。なにかしらひと手間加えないと、手を抜いているように思えてしまうのだ。
もっと美味しくできないか。料理と対峙してそう思わない時間などいっときもなかった。きっと流もおなじなのだろう。
もっとも気になっていたのは牛タンの煮込みだ。
牛タンをアレンジすることは少なくない。精肉以外のビーフを嫌うシェフもいるが、清三は内臓肉も好んで使う。それは食材を極力無駄なく使いきりたいという思いからでもある。コールド・タン、タンシチューはもちろん、コートレットにすることもある。
見たところドミグラスソースで煮込んだタンシチューのようだ。洋辛子を添えるあたり、むかしながらの洋食を意識しているに違いない。
デミカップに入った牛タンを箸で取ろうとして、そのやわらかさに指先が驚いている。ほろほろと崩れそうになる牛タンに洋辛子を付けて、そろりと口に運ぶ。口のなかで繊維が解け、広がる味わいに予想を裏切られた。
味噌味なのである。辛さと甘さが絡み合う味わいからすると、八丁味噌と白味噌、それに麦味噌を合わせているのだろう。そしてかすかに感じるのは山椒の香りだ。
たしかに牛タンと味噌の相性はいい。仙台で味噌漬けを食べたこともあるから、味噌味で煮込んでもなんの不思議もないのだが、こうして食べてみると、実に新鮮な味に感じるのである。
酒が進む。四合瓶はすでに半分近く減っている。それほど酒に強くない清三にとっては、めったにない酒量だ。なのにまるで酔ってはいない。頭のなかは研ぎ澄まされ、五感は鋭くなるいっぽうなのが不思議だ。
まるで心のなかを見透かされているようだ。
おなじ調理場ではたらくスタッフたちも、月に二度三度と足を運んでくれる常連客も、情報を求めに来るライターや料理評論家たちも、清三が料理のことで悩んでいるなど、みじんも思っていない。五年続けて二ツ星を獲得し、いつ三ツ星に昇格するのかと周囲はみな注目しているのだ。
ただ料理を無心に食べればいいものを、余計なことばかり考えてしまう。
「どないです。お口に合うてますかいな」
様子を見に流が厨房から出てきた。
「大満足です。ひと品ひと品に心がこもっていて、何ひとつ奇をてらったわけではないけど、細かな工夫がなされている。僕などにはとても真似できません」
正直な感想を口にした。
「おほめいただくのはありがたいですけど、同業のかたにそない言われると、なんやお尻のあたりがこそばゆうなりますわ」
「僕はお世辞を言えない人間なので、正直に言ったまでです。失礼なことを訊きますが、どこで修業なさったんですか?」
「修業らしい修業はしたことがおへんのや。見よう見まねでここまで来ましたんで」
「お師匠さんはどこのどなたです?」
「それもいてまへんのや。強いて言うなら義父でっけどな、それも不義理して棒折ったもんやさかい、大きい顔して師匠て呼べるもんやおへん」
「ということは、すべて独学ですか」
「まぁ、そうなりまっしゃろな」
流は、ふっ、と小さなため息をついた。
流の言葉をどこまで信じていいのか、清三には見極めがつかなかった。
夜間高校を卒業してすぐ、地元の食堂に勤めてから、洋食屋、フレンチレストランと店を替えながら料理を学び、フランスに渡ってからは十年近く修業を積んだ。その間、師匠と呼ぶべき料理人の数知れず。それぞれから学んだことやレシピを記した大学ノートは、今も百冊ほど手元に残していて、命の次にたいせつなものだと思っている。
それがあるからこそ、これまで自信を持って料理に立ち向かうことができたのである。そういうものが流にはまったくないというのか。
「ぼちぼちご飯をお持ちしまひょか」
「お願いします」
流に声を掛けられなければ、いつまでも飲み続けてぶっ倒れているところだった。
「最近は土鍋で炊いたご飯をそのままよそうことが多いみたいでっけど、やっぱり椹(さわら)のお櫃に移して、ちょっとうましてからのほうが旨いんと違うかなぁと思うてますねん」
清三の前に流がお櫃を置いた。
「お櫃ですか。そういえば最近は見かけなくなりましたね。和食のお店は土鍋ばかりだ」
「土鍋で炊いたご飯も美味しいもんですけど、そればっかり、っちゅうのもねぇ。このごろは流行りに乗る料理人がようけおるさかい、しょうがおへんけどな」
お櫃から木賊(とくさ)柄の飯茶碗に流がよそっているのは、アワビ飯だ。ざく切りにしたアワビが白飯のすきまを埋め尽くすという、なんとも贅沢な〆である。
小ぶりのおろし金に載った擂り柚子を、流は茶筅でアワビ飯に振りかけた。
「お櫃ごと置いときまっさかい、お好きなだけ召しあがってください。漬けもんとお汁も置いときます。お代わりしはったときは、お汁掛けにしてみてください。ちょっと味が変わって美味しなる思います」
言いおいて、流は厨房に戻っていった。
さて、アワビ飯はどんな味付けをしてあるのか。ひと口食べて拍子抜けした。
なんともあっさりした味付けなのだ。おそらく一番出汁で炊いたのだろう。昆布とかつお節の味わいがかすかに感じ取れる程度で、アワビそのものの味が際立っている。塩も醬油もわずかしか使っていない。何より驚くのはアワビの食感だ。嚙むまでもなく歯がすーっと入り、舌と上あごですり潰せるほどやわらかく仕上がっている。志摩のリゾートホテルで食べたアワビのステーキとも違い、数寄屋橋の鮨屋で食べた煮アワビとも違う。しかしその旨さは二軒に勝るとも劣らない。
一膳目を食べ終えてハッとした。具のアワビもだが、ご飯に沁みこんだアワビの香りが清々しいあと口を残すのである。なるほどと思い至った。
あたりまえのことだが、蒸し煮にしたアワビと白飯を一緒にして食べるのと、アワビ飯はまったく別ものなのだ。アワビよりも、アワビの旨みを吸いこんだ飯が主役と言ってもいいかもしれない。
お汁がまた旨い。中華料理の清湯(チンタン)を思わせるスープは青みがかっていて、それはアワビのキモが溶けこんでいるからだろうと思う。
二膳目を半分ほど食べたところで、流の奨めにしたがって汁掛け飯にしてみた。
見た目は似ていても、リゾットとはまるで違う食べものだ。似た味わいを探して思い当たるのは海苔茶漬けだろうか。しかしそれとは比べものにならないほど、高貴な味わいがするのはアワビの力だ。
キモの香りはすれど、舌にはキモ特有の臭みなどまったく残らない。どんな下処理をしたらここまで洗練された味わいになるのか。
いっそのこと、流に弟子入りして教えを乞えば、すべて解決しそうな気がしてきた。
「いつでも奥にご案内できまっさかい、ええとこで言うとぉくれやす。娘が待っとりますんで」
「そうでした。あまりに料理が美味しいものですから、ついついお尻が重くなってしまって。ごちそうさまでした。今すぐ参ります」
あわてて箸を置いて、清三が立ちあがった。
「せかしてるんやおへんのでっせ。お忙しいしてはるかたやと聞いてますし、あとのご予定もあるやろさかいと思うただけで」
「料理は作るのも好きですが、食べるのはもっと好きなもので、美味しいものを前にすると時間が長くなる悪いクセがあるので、言っていただいてよかったです」
「せかしたようになってしもうて、すんまへんでしたな。どうぞこちらへ」
先を歩く流についていくと、細長い廊下に出たが、そこでも清三は驚きの声をあげてしまった。
「これはなんですか」
「見てのとおり、料理の写真ですわ。わしはレシピを書き留めたりはせんもんで、写真に撮って残してますんや。ずぼらなこって」
流が苦笑いした。
細長い廊下の両側に貼られた写真の数はおびただしいものだ。そしてそこに写っているのは多種多様な料理である。半分以上は和食だが、中華ふうのものもあれば、イタリアンっぽいものもある。
「まさかこれをぜんぶおひとりで作られたんじゃないでしょうね」
「なかには誰ぞと一緒に作ったもんもありまっけど、ほとんどはわしが作った料理です」
「くどいようですが、料理は独学なんですよね」
「独学てな言葉を使えるほど学んだわけやおへん。見よう見まねです」
「これもですか? 比較的新しいフレンチですよね」
立ちどまって、清三が食い入るように写真を見つめている。
「フレンチて言えるようなもんと違いまっせ。グジをアセゾネして、カダイフを巻いて揚げたもんです。たしかソースはシェリー酒で風味を付けたクリームソースやった思います」
流が清三の真横に立った。
「ソースに野菜を使っておられるようですが」
「タマネギやとかエシャロット、ニンジン、カブラやらを弱火でエチュベしてソースに混ぜたような記憶がありますな」
学んではいないと言いながら、流は塩コショウすることをアセゾネと言い、やさしく蒸し焼きにするという意味のエチュベというフレンチ用語を使う。
「あとは娘にまかせてまっさかい」
いつの間にか廊下の突き当たりまで歩いていた流が、ドアをノックした。あわてて清三が駆け寄るとドアが開いた。
「どうぞお入りください」
ソムリエエプロンを外し、黒のパンツスーツに着替えたこいしが迎えた。
思ったより広い部屋には、むかしふうの応接セットが置かれていて、清三はこいしと向かい合う形でロングソファに腰をおろした。
「面倒や思いますけど、いちおう探偵依頼書に記入してもらえますか。簡単でええので」
こいしがローテーブルにバインダーを置いた。
住所氏名年齢からはじまり、職業、家族構成など迷うことなく書き終えて、清三がこいしに返した。
「米山清三さん。どんな食を捜してはるんですか」
こいしがノートを開いた。
「ハムカツです」
清三は即座に答えた。
「うちもハムカツは好物ですねん。どこかのお店で食べはったもんですか?」
「ええ。大分駅の近くにあった洋食屋で食べたものです」
「あった、ていうことは今はもうないんですね」
「一年前に捜しに行ったのですが、見つかりませんでした。お店がなくなってしまったのか、僕の記憶があいまいなのか。どちらかはっきりしませんが」
「ちょっと詳しいに教えてください」
こいしが身体を乗りだした。
「僕は大分県豊後大野(ぶんごおおの)の緒方(おがた)というところで生まれました。近くに石仏の遺跡があるような長閑(のどか)なところで、両親は農家を営んでいました。特にこれといった特色もなく、いろんな作物を作っていたような記憶があります。はっきり言って貧しい家でしたねぇ。兄弟姉妹が六人もいて、僕は下から二番目でした。食べるのが精いっぱいの暮らしだったので、みんな中学を卒業すると働きに出るようなありさまでした。僕は大分市内の叔父の家に下宿させてもらって、家具工場に勤めながら夜間高校に通っていました」
清三は固い口調で当時を振り返った。