連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:高野秀行(ノンフィクション作家)
怪獣、麻薬、海賊、ゲリラ……。辺境・秘境民族への体当たり取材で、前人未到のノンフィクションの境地を切り拓いてきた高野秀行氏。新たなテーマは謎に包まれたアジア納豆!
第七回
怪獣と納豆、謎の深さは同じです
ゲスト 高野秀行
(ノンフィクション作家)
Photograph:Hisaaki Mihara

高野秀行(左)、中島京子(右)
中島 高野さんといえば、早稲田大学の探検部時代に、コンゴの奥地にいるという伝説の怪獣ムベンベを探しに行ったのを端緒に(『幻獣ムベンベを追え』)、ミャンマーのアヘン栽培を生業にする地域で種まきから収穫まで実体験したり(『アヘン王国潜入記』)、海賊で有名なソマリアという国のなかにソマリランドという民主国家があると知れば危険を顧みず突入してしまう(『謎の独立国家ソマリランド』)などなど、ノンフィクションというジャンルには収まりきらない体当たり取材で、数々の話題作を生み出してきました。ところが、近著のタイトルは『謎のアジア納豆』(新潮社)。これまで、普通の人が足を踏み入れることのない辺境秘境を旅してきた高野さんが、なぜ納豆をテーマに選んだのですか?
高野 じつは僕にとっては、ムベンベもソマリランドも納豆もみんな同じなんです。
中島 いや、ムベンベから納豆、相当の落差だと思うのですが……(笑)。
高野 わからないものが出てくると、それを探りたくなる。僕の探検は、すべてその一点から始まるんですね。最初はタイの庶民的な賭博をテーマに何か書こうと思ったんです。でも、なんか違うな、と悩んでいるときに目の前に現れたのが「納豆」だったんです。そもそも私たちは、納豆は日本独自のものだと思い込んでいるでしょう。でも、アジアにも納豆があるんです。そう話すと、みんな驚きますよね。
中島 たしかにそうですね。外国の方に「納豆を食べたことがありますか」と聞いているときには、海外に納豆があるはずはない、という思い込みが前提になっている気がします。
納豆の起源という禁断の領域に足を踏み入れた

中島 麻薬王の秘密工場で納豆!(笑) これまたダイナミックな出会いですね。
高野 彼が持ってきた納豆は、乾燥した薄焼き煎餅のような円盤状の物体でした。それを炙って、杵でついて粉状にしてスープの調味料にしていると教えてもらいました。
中島 ねばねば糸引いてなくても、たしかに味は納豆だったのね。
高野 麻薬地帯への潜入を計画していた時期でもあったので「なぜこんなところに納豆が?」という思いが深まるには至りませんでした。自分のなかで、納豆への興味が発酵していなかったのでしょう(笑)。
中島 それから二十数年の発酵期間を経て、ふたたび「納豆」に出会ってしまったわけですね。
高野 そうなんです。二〇一三年に東京で暮らしているシャン族の友人に「日本の納豆には味がひとつしかない。シャン族の納豆にはいろんな味があるし、いろんな食べ方をする」と聞いて、あの煎餅納豆の記憶が蘇ってきたんです。謎や未知の世界がどんどんなくなってきている時代に、こんなに身近にまったく未知のものがあった。シャン族の納豆とは、いったい何なのだ。そもそも納豆とは何者なのだ。頭のなかに謎がうずまくような、最大級の衝撃を受けました。
中島 そして、納豆の起源という禁断の領域に足を踏み入れてしまった(笑)。
高野 これまで多くの人たちが日本の納豆の起源を調べてきたのですが、さっぱりわからないらしい。日本の常識の範囲内で考えたら行き詰まるけれど、アジア納豆の視点から探ったら起源がわかるのではないかという野望に取り憑かれてしまったんです。
中島 そもそも日本では藁についた納豆菌で発酵させた糸引き納豆が納豆だという常識がありますよね。
高野 アジア各地で作られている納豆を食べてきた結論から言うと、茹でた大豆を包む大きさがあれば、どんな木の葉っぱでも納豆を作ることができるんじゃないか、と思います。藁にこだわることはない。そもそもアジア納豆は、山岳地帯を中心とする辺境食なので、そこにあるもので作るしか方法はないんです。
中島 う~ん。しかも、つぶして煎餅にしたり、粉にしたりするんだもの。藁にこだわる日本の納豆のほうが、じつは「偏狭食」のように思えてきた(笑)。
高野 たしかに、そのとおりかもしれませんね。

高野 僕も世界各地を取材している過程で、いつも同じようなことを感じています。辺境ノンフィクションは、そこが面白いんですよね。取材を始めた段階では、どこからどんな話が飛び出してくるのかまったく想像できない。わからないことだらけです。だから日本で調べているときは手の届く範囲でぐるぐる回っているだけで、煮詰まってしまうことも多いんです。でも、一歩外国に踏み出してみるだけでまったく違う見方ができる。今回の納豆もその一つの典型例です。どうして自分たちは、納豆を日本独自の伝統食品だと思い込んでいたのだろう。今となっては、不思議な感じがしますよね。
中島 大陸から作り方が伝来したわけではなさそうですね。だから多くの日本人は、納豆は日本独自の伝統食品だと信じ込んでいます。
高野 調べてみると、そう勘違いするのも仕方ないほど、日本の納豆文化は古くから続いているんです。納豆を食べ始めた時代については諸説ありますが、現在の糸引き納豆と思われるものが最初に登場する文献が、室町時代に書かれた『精進魚類物語』です。納豆関係の資料を読むとあたかも真面目な文献のように記載されています。ところが読んでみると「鮭の大介鰭長」率いる魚と肉の連合軍が「納豆太郎種成」を大将とする山菜や豆腐などの精進料理連合軍と宴会の上席を巡って合戦をおこなうという突拍子もないバトルファンタジー小説なんです。
中島 設定だけで爆笑ものの小説だけど、食文化史に関わる方々は、これ、みんな読んでるんでしょうか。
高野 原典には当たらず、学者の著書にちょこっと載っていたのを孫引き、孫引きで紹介しているのでしょう。しかし、そこにはとんでもない物語が眠っていた。
中島 高野さんは、まるで学者のように文献に当たりまくっていますものね。『謎のアジア納豆』を読めば、現在解明されている納豆の全容がほぼ理解できる気がします。
高野 ありがとうございます。そう言っていただけると、納豆にまみれた数年間の苦労が報われます。文献を調べていると意外なこともわかってきて、箸でかき混ぜて糸を引かせた納豆をご飯にかけて食べるようになったのは、せいぜい幕末ぐらいから。それ以前は、納豆汁一辺倒だったんです。しかも日本で全国的に糸引き納豆を食べるようになったのは、ここ二十~三十年くらい。ごく最近のことなんです。
中島 たしかに、そうですね。私たちくらいの年齢の関西出身の人に聞くと、子供の頃に納豆は売っていなかったと言いますよね。
高野 ところが、千利休が貴人に納豆汁を出していたという記録もあるので、その頃にはきっと京都や大坂でも納豆は一世を風靡していたのだと思われます。
中島 『謎のアジア納豆』を読んでいると、自分に染み付いた常識ってなんだろうって、疑いたくなりますね。とにかく、壮大な探検記であり、納豆の起源を探るミステリーであり、さらには食の文化史でもある、融通無碍な作品だと思います。あまり本の内容を深く語ってしまってもよくないので、この続きはぜひ読んで驚いて頂きたい、ということにしましょう(笑)。
辺境民族と出会って、最初に覚える言葉とは
中島 高野さんは、辺境取材をする上でもっとも重要なのが言葉と食事だとおっしゃっています。とくに辺境民族の言葉なんて、日本で習っていくこともできませんよね。『恋するソマリア』の巻末には、日本の商船を襲って捕獲されたソマリ人の海賊の通訳をすることになったという仰天エピソードも紹介されています。

中島 「こんにちは」とか「はじめまして」のような挨拶の言葉か、「ありがとう」のような感謝を表す言葉でしょうか。
高野 普通はそう思いますよね。数え方によって違うのですが、世界中には四千五百から六千ほどの言語があると言われてますけど、「こんにちは」や「ありがとう」がある言語のほうが少ないんじゃないかって思うんですよ。
中島 そうなんですか。まったく知りませんでした。でも、挨拶の言葉がないと、人間関係がギクシャクしてくる気がします。
高野 英語を始めとするメジャーな言葉は、すべて文明化されている地域で使われている言葉なんです。街に住んでいると、知っている人ばかりじゃない。知らない人とも出会うから、初対面同士ギクシャクしないように挨拶する必要があります。でも小さな村に住んでいると、みんな年がら年中顔合わせているから「こんにちは」なんて言わなくてもいいんですね。
中島 そうか。毎日会っているから、改めて「こんにちは」なんて言われると気持ち悪い(笑)。
高野 「ありがとう」も使わないところが多いですね。言葉としては、一応あるけど誰も使わないとか。布教に来た宣教師が、聖書のなかにある「ありがとう」を現地の言葉に翻訳するときに、新しく言葉を作るということもよくあります。
中島 たしかに、中国語も「你好(こんにちは)」よりも「吃饭了吗?(ご飯食べたか?)」のほうが、親しい人の間で交わされる挨拶ですね。「こんにちは」じゃないとしたら、どんな言葉を最初に覚えるのですか?
高野 いろんな民族のなかで暮らしてきましたが、まず最初に「おいしい」を習うことが多いですね。一緒に食事をして「おいしい」と言うと、すごく喜ばれるんです。
中島 そうか。同じところで暮らして同じものを食べるのだから、「おいしい」は大切ですよね。私たちだって、外国のお客さまをお招きしたときに日本語で「おいしい」と言われたら嬉しくなりますね。
高野 世界的に、家庭料理は女性が作ることが多いでしょう。どんな民族でも、女性は一歩下がっているところがほとんど。しかも共通語である英語やフランス語、中国語をしゃべれる人は、男性だけの場合が非常に多い。必然的に男の人たちとばかり話をすることになるわけです。でも、男同士だと、建前っぽいやり取りが続いて、なかなか懐を開いてくれないんですね。ところが、女性が作った家庭料理を食べて現地の言葉で「おいしい」とお礼を言う。すると、女性たちも会話に参加してきて、一気に場が和むんです。
中島 出されたものはゴリラの肉だろうが何だろうが、現地の人と同じものを一緒に食べるんですね。すごい。でも、お母さんがにこやかになると、家族が和気あいあいとしてくるのは、世界中一緒ですね。高野さんの本を読んでいると、これが本当の意味で世界の人と友達になるってことなんだなぁと実感します。
高野氏、中島作品の創作の秘密に迫る
高野 僕はずっとノンフィクションを書いてきたのですが、小説を書いてみようと何度かチャレンジしたこともあるんです。たとえばアフリカの内戦や難民の悲惨な状況を伝えたいと思ったら、フィクションを織り交ぜたほうが伝わりやすい。日本の感覚からはあまりに遠い話なので、実話だけでは理解してもらうことが難しいんです。でも、うまくいかない。脳の使っている部分が全然違う気がします。ノンフィクションは自分が調査した手持ちのカードを組み合わせて戦うしか手段はないのですが、小説だとジョーカーでも何でも使えちゃうでしょう? たとえば、突然天から悪魔が降りてきてもかまわない。まったく別種のゲームに参加している感じで、混乱してしまうんです。そういう意味では、中島さんは、どういうふうにして小説を書いているんでしょう?

高野 そういえば直木賞を受賞された『小さいおうち』は、リアルかつおもしろいエピソードが満載で、ノンフィクションっぽい香りのする作品でした。昔の新聞や雑誌などの資料をたくさん読まれたのでしょう。
中島 あの作品は昭和初期から終戦までを描いたものですが、当時の日本は戦争という暗闇のなかで暮らしていた重苦しい印象があるでしょう。でも、資料を当たっていくと決してそんなことはない。普通の家庭にもお手伝いさんがいて、ハイカラな生活をしていた人もいたんです。一九四〇年に開催予定だった東京オリンピックや万国博覧会のことなど資料に基づいたエピソードがおもしろくつながるようにストーリーを紡いでいきました。
高野 取材して入手したいろんな事実を組み合わせていく手法は、まさにノンフィクション方式ですね。
中島 でも、ノンフィクションはやっぱり、ノンフィクション作家に任せたい(笑)。さっき、私は悪魔が出てきちゃうようなものは書けないと言いましたが、小説の武器はあくまでもフィクションにあると思っています。嘘をできるだけ効果的に使うのが、小説を構成する上での技術なのですが、それが、高野さんのおっしゃるジョーカーなのかもしれません。
高野 技術的といえば、『謎のアジア納豆』は十年前の自分には絶対書けない作品です。五年前でも無理だったかもしれない。納豆菌という微生物学の要素から、日本とアジアの歴史や民族の話など、様々な内容が複雑に入り組んでいるので、構成するのが技術的に難しい。どんなに内容の深い本でも、おもしろくないと読者の方々は読んでくれませんから。内容がよければおもしろい本になるかというと、それはまた全然違うでしょう。取材には四年ぐらいかけたのですが、二十年以上世界を旅して本を書いてきたいろんな経験が、納豆を通してぎゅーっと凝縮されている作品だと思います。自分としては、行くところまで行きついた感じなので、次は何をテーマに書いていいのかわからないんです。本当に(笑)。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立、1996年にインターシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で第143回直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で第42回泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で第3回河合隼雄物語賞、第4回歴史時代作家クラブ作品賞、第28回柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で第10回中央公論文芸賞を受賞。
高野秀行(たかの・ひでゆき)
1966年、東京都八王子市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学第一文学部仏文科卒。1989年、同大探検部の活動を記した『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。2013年、『謎の独立国家ソマリランド そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア』で第35回講談社ノンフィクション賞、第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。他の著書に『アヘン王国潜入記』『未来国家ブータン』『移民の宴』『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』など多数。
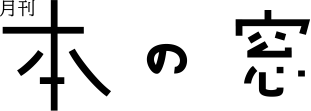
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2016/12/20)






