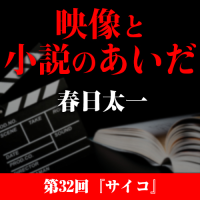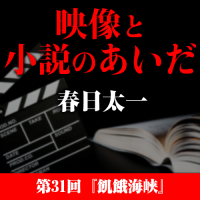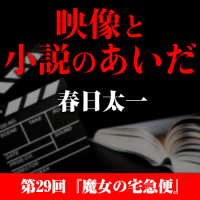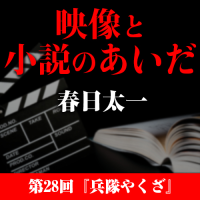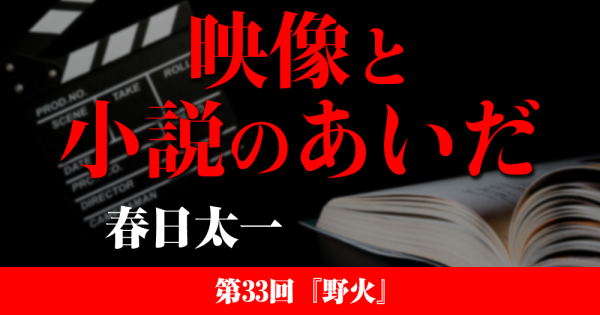連載第33回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
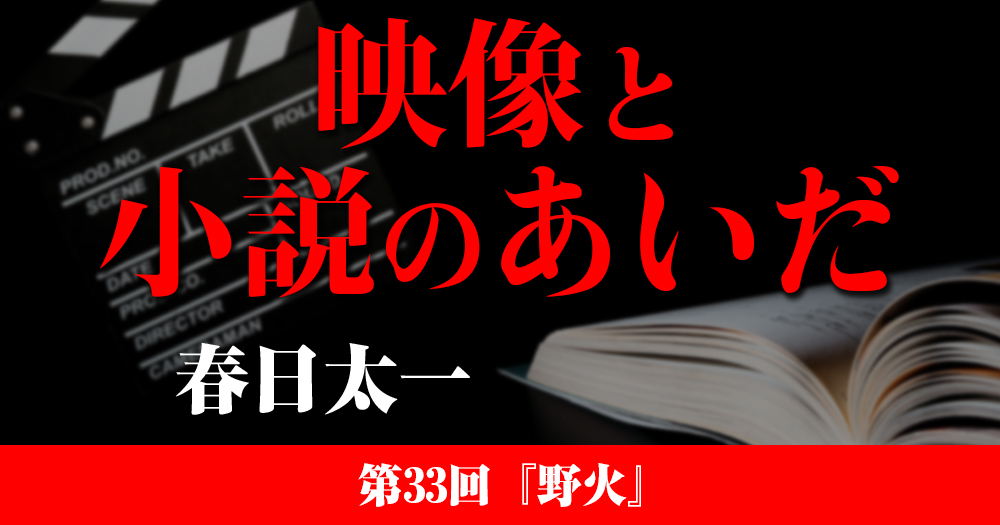
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『野火』
(1959年/原作:大岡昇平/脚色:和田夏十/監督:市川崑/制作:大映東京撮影所)
「歯が治ったら、すまねえがわけてもらうよ」
舞台は太平洋戦争末期、一九四五年二月のレイテ島。戦線が崩壊した中で飢餓に苦しむ日本兵の彷徨を描いた大岡昇平の小説『野火』は二度映画化されており、ここでは市川崑監督による最初の作品を取り上げる。
本作は、物語の展開や登場人物のキャラクター設定やセリフの中身など、細かいところまで原作と違いはない。が、それでも大きく脚色された点が二つある。
一つは主人公の田村(船越英二)の内面描写だ。小説と映画の表現手段の最大の違い、それは小説が人間の心情や脳内での思考といった抽象的な要素を文字でどこまでも掘り下げられるのに対し、映画は目に見えるものしか表現できないため、そうした要素を表現するには限界があるという点だ。
本作がまさにそう。原作の主人公は灼熱と飢餓の極限状況下で当て所なく歩き回るにつれ、自身の運命=「神」との対峙を強く意識するようになり、そうした内面の記述に多くを割いている。一方、原作ではそうした要素を丸々カット。田村の絶望的ともいえる生き地獄の様子を、淡々と具体的な映像として追いかけている。
つまり、原作は田村自身の主観的な視点から田村を描いているのに対し、映画はどこまでも客観的な視点から田村を捉えているのである。その結果、レイテの日本兵たちの惨状が田村を通してひたすら生々しく映し出されることになった。
そして、この脚色が二つ目の大きな脚色にも繋がる。それは、終盤の改変だ。
部隊とはぐれた田村は長いこと一人で彷徨い続けた。その果てに、はぐれていた同僚の安田(滝沢修)と永松(ミッキー・カーティス)に遭遇する。驚くことに、彼らは飢えていなかった。というのも、永松が鉄砲で狩った「猿」と称する肉を干したり焼いたりして食い繋いでいたからだ。また、田村の所持する手りゅう弾が安田に渡ることを、永松はとても恐れていた。
飢えて倒れ込んだ田村にも、永松は「猿」の肉を食べさせようとする。ここでのリアクションが、原作と映画では大きく異なっているのである。原作の田村は、言われるがまま肉を食べ続けた。一方、映画の田村は歯がボロボロで噛むことができず、肉を吐き出していた。その後で田村が永松に言ったのが、冒頭のセリフだ。
そこからしばらくは、原作と映画は同じ展開をたどる。
田村は狩りに出た永松を目撃。彼が標的に捕らえていたのは、人間だった。つまり「猿」と称していたのは人間の肉だったのだ。ただ、田村は永松を咎めることはなかった。むしろ問題は安田だった。田村は安田の計略に嵌り、自身の手りゅう弾を彼に渡していたのだ。武器を手に入れれば、安田ならそれを使って二人を殺害し、「猿」にしかねない。田村は永松に協力して、安田を討つことにした。
そして永松の作戦は成功、安田を射殺してのける。永松はすかさず安田の死体に刃を突き立て、「猿」として使えるように解体していく。これを見た田村は永松の銃を奪い、彼を射殺した――。
ここからが、原作と映画は大きく異なる。映画の田村は、遠くに見える煙を農夫たちの燃やす野火だと思い込む。そして、危険だとわかっていても「俺は普通の暮らしをしている人間に会いたい」と飛び出していく。だが、それは現地のゲリラの狼煙だった。激しい銃弾の中、倒れ込むところで物語は終焉する。
一方、原作は違う。田村は米軍の捕虜となり帰還。真っ当な生活が送れなくなり、精神病院に入る。そして、病院で書いた日記が、実はこの小説だった。
つまり、原作小説は「正常な精神状態にない人間の記述」という体裁で表現されているのだ。そのため、読者とすればここまでの内面描写もまた、どこまでが正気で書かれたのか、狂気で書かれたのか、わからなくなる。映画がそうした要素を全てカットした理由は、そこもあった。あくまで悲惨な戦況を客観的に映すことが目的であるため、こうした虚実の曖昧な境界線はノイズでしかなくなるのである。
また、このことはもう一つ大きな意味合いをもたらしている。
原作の田村がそれだけの狂気に入り込んだ理由。それは、「猿」を食べたこと、そして食べた上でその正体を知ったからに他ならない。一方、映画の田村は「猿」を食べなかったことで――それでもギリギリの最小限ではあるが――正気を保つことができた。あの分岐点は、ラストを正気で終えるか狂気で終えるかのターニングポイントでもあったのだ。
ただ皮肉なことに、原作の田村は「猿」を食べたことで栄養が足り、生き延びることができた。映画の田村は食べられなかったために飢餓が悪化、意識が朦朧として判断力を失い、遠い異郷で果てることになる。
つまり、双方のラストは正反対の結末となっているということだ。だが重要なのは、いずれにしても「まともに生き残ることはできていない」に変わりはないということだ。正反対のラストでありながら、同じメッセージ性を与える結果となった、稀有な脚色といえる。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。