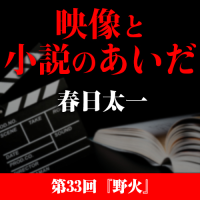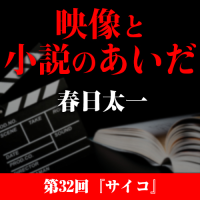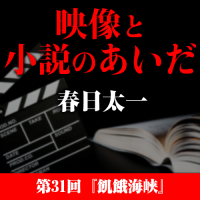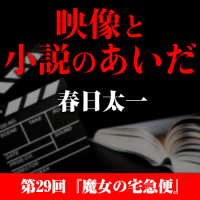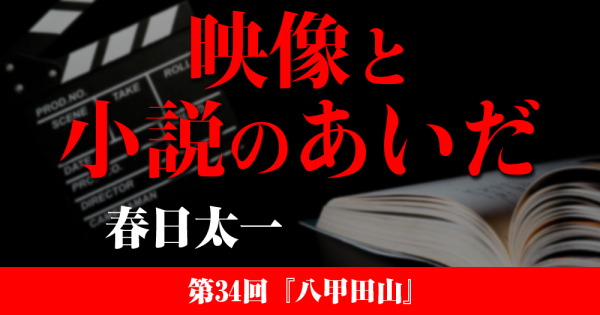連載第34回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
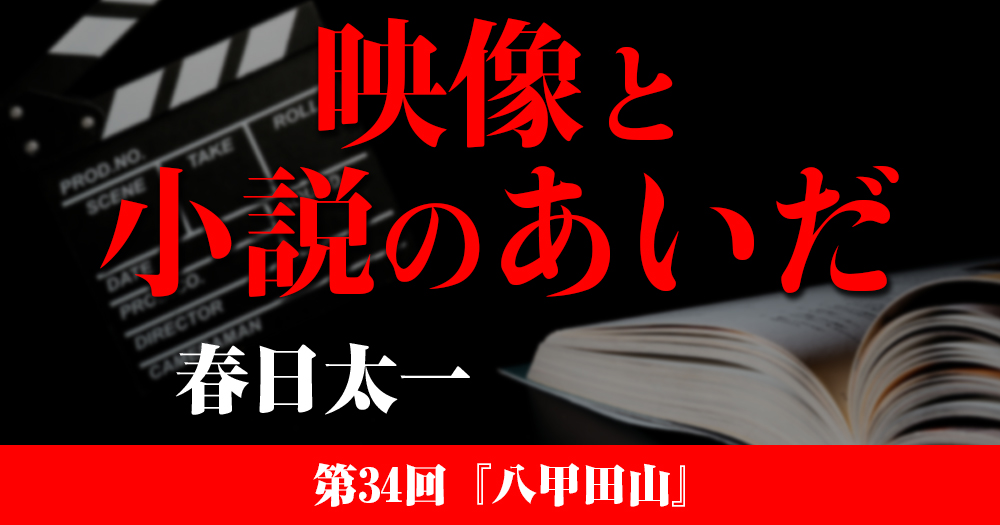
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『八甲田山』
(1977年/原作:新田次郎/監督:森谷司朗/制作:橋本プロダクション、東宝映画、シナノ企画)
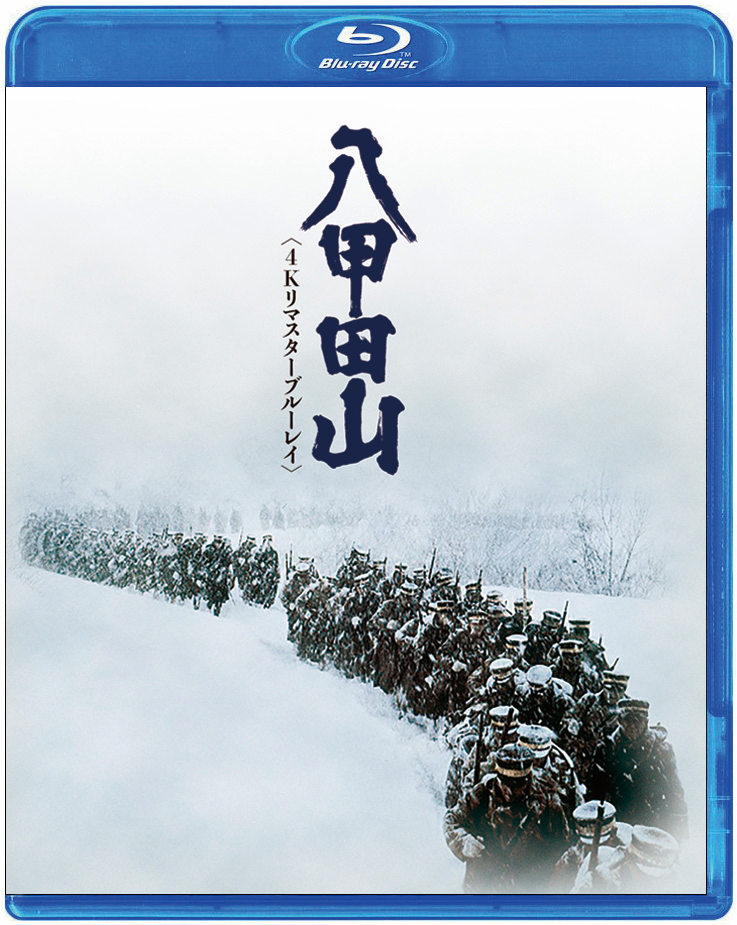
「八甲田山 <4Kリマスターブルーレイ>」
発売中
5,280円(税抜価格 4,800円)
発売・販売元:東宝
©1977 橋本プロダクション・東宝・シナノ企画
「案内人殿に対し、頭(かしら)、右!」
日露開戦が間近に迫る、1902年2月23日。陸軍第八師団は青森県の八甲田山系で雪中行軍を実施する。だが、折からの大雪と不十分な装備もあり、青森歩兵第五連隊は猛吹雪の中で遭難してしまう。そして、最終的には参加210名のうち199名が死亡した。
この山岳遭難事故の大惨事は、新田次郎が『八甲田山死の彷徨』として小説化してベストセラーに。その後、『八甲田山』として映画化された。
小説も映画も、強調しているのはもう一つの部隊との対比だ。青森連隊と同時期に八甲田で雪中行軍をしていた弘前歩兵第31連隊は一人も犠牲者を出さずに踏破してのけた。二つの部隊には、どこに違いがあったのか。小説も映画も、そこを浮き彫りにしながら話を進めている。
まず挙げられているのは、その編成だ。200名を超す大所帯の青森連隊に対し、弘前は少数精鋭。そのため、食糧などの兵站は最小限で済むし、移動もスムーズにできる。そして、何より大きいのは指揮系統だ。弘前は隊長の徳島大尉(高倉健)に指揮権が一元化されている。雪山に慣れた徳島の的確な判断により、困難な気象状況を突破できた――としている。
一方の青森連隊は、神田大尉(北大路欣也)が指揮することになったのだが、それとは別に連隊本部から神田の上官たちも行軍に参加している。そして、山田少佐(三國連太郎)が神田を飛び越えて判断を下すようになり、神田もその指示に従うしかなくなっていく中で、被害が拡大する。
そうした両部隊の相違点の象徴として扱われているのが、案内人の存在だ。
青森連隊は当初、麓の集落で地元民に案内を頼むものの、あまりの無謀な計画のために断られてしまう。だが、当日になって通りがかった際、思った以上の天候悪化を懸念した地元民は自ら案内人を買って出るのだ。だが、神田の判断を仰ぐ前に山田が独断でこれを断ってしまう。そのため、後に猛吹雪でホワイトアウトした際に道を完全に失ってしまうことになったのだ。それに対して弘前隊は行く先々の村落で案内人を頼み、その先導で間違いなく次の目的地へたどり着くことができている。
こうした対比の構図は、小説も映画も同じだ。が、弘前隊による案内人の扱いに関して、映画は脚色を施している。
隊は宇樽部という小さな村落に着く。次の目的地・戸来村へは、雪の峠を越える難所が待ち受けていた。そこで、戸来村から宇樽部に嫁いできた「さわ」(秋吉久美子)という女性が案内を買って出る。村長は徳島に対し、必ずさわの指示に従うよう釘を刺し徳島もそれを承諾した。
そして、さわの見事な先導の結果、部隊は無事に難所を踏破した。
ここまでは、小説も映画も同じだ。が、集落が見えてきたところから、正反対の展開になっていく。
原作の徳島は、さわに「五十銭を一個」与えると「案内人は最後尾につけ」と「大きな声で怒鳴った」のだ。案内人、しかも女性に先導されて村に入ったのでは、軍人としての示しがつかない――と徳島は考えたのだ。
これに対してさわは「もう用はねえってわけかね」と、徳島の冷徹な判断に抗議をするも、従うしかない。隊員たちのリアクションは「心の中ですまないと思った」と記されており、隊長の命令にどこか理不尽さを覚えている。そして、以降さわがどう行動したのかに関しての記述はない。なんとも後味の悪い別れとなっているのだ。
それが、映画は全く異なる。
村落が近づいてきた際に、隊員から「案内人を最後尾に」と提案されるも、徳島は「いや、このままでいい」と断っているのだ。小説と正反対の関係である。そして、さわを先頭に隊は村落に入っていく。
小説では描かれることはなかった別れ際も、映画では描き込まれている。
「兵隊さん、みんな元気で」
さわは、そう言って帰路についた。そのさわの背中に向けて徳島が叫んだのが、冒頭のセリフだ。徳島以下、隊員たちはさわに敬礼を捧げ、さわは何度も振り返りお辞儀をしながら去っていく――。
あくまで「軍人と案内人」という職務上の関係性でしかなかった小説とは全く異なる、人間同士としての心温まる触れ合いが、映画には描かれている。
この脚色は、男たちがひたすら雪の中を歩き続け、そして斃れていく殺伐とした内容に、せめてもの救いといえる安らぎを観る側に与える結果となった。
それだけではない。
青森隊の山田少佐は、村人から案内人の申し出を断る際、次のセリフを吐き捨てている。
「お前たちは案内料が欲しくて、そんなことを言ってるのだろう」
まるで、タカリのような蔑んだ扱いである。徳島の案内人への敬意ある向き合い方と、あまりに違う。重要なのは、このやり取りが出てくるタイミングだ。
小説では、さわのエピソードの後に山田少佐と村人のやり取りが出てくるが、映画では、さわのエピソードの前に変更されている。その結果、小説では弘前隊が峠越えを終えた後で青森隊の入山という順になっていたのが、映画では、弘前隊の峠越えと青森隊の彷徨とが同時進行となっている。
さわに先導されながら峠を越えていく弘前隊。案内人の不在のために彷徨い続ける青森隊。双方のカットバックは、案内人に対する敬意の違いが招いたものだと言わんばかりの、残酷な因果応報を訴えかけていた。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。