連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第32話 林京子さんの短篇連作
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第32話 林京子さんの短篇連作](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/07/secret-story_32_banar.png)
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第32回目です。今回は、読み応えのある骨太な作品を遺した女性作家、林京子さんにまつわるエピソード。受賞歴も華々しく文壇に登場した林さん。作品に向きあうその視点や姿勢は独自性に満ちていました。担当編集者として関わった日々を振り返ります。
東京新聞の夕刊の文化欄に、毎週土曜日、共同通信の編集委員をしている田村文さんが、『女たちの戦争文学』と題して、連載をしている。戦争体験を小説化した女性作家の作品を取り上げて、読み応えのある連載になっている。
田村さんは、私が現役の時、担当した作品の文芸時評などでお世話になっていて、顔見知りの文芸記者だ。
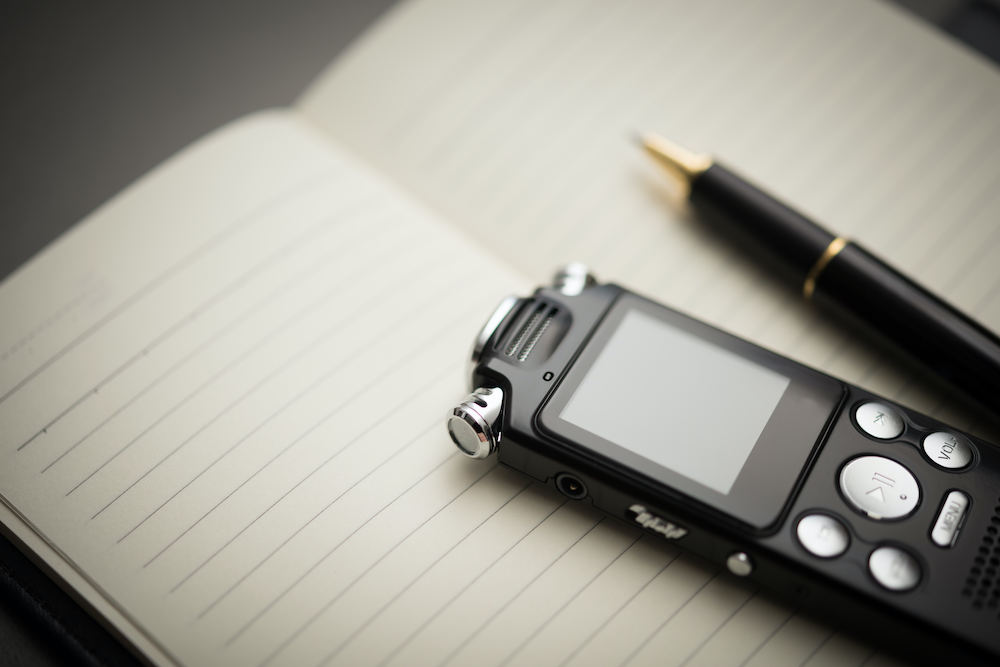
『女たちの戦争文学』の9回目から、林京子さんを取り上げている。
田村さんは、林京子さんを「1975(昭和50)年、長崎での被爆体験を基に書いた小説『祭りの場』で、群像新人文学賞と芥川賞をダブル受賞してデビュー」と紹介している。
この新人賞と芥川賞を受賞することになった経緯が、ちょっと変わったものなので、林京子全集(全8巻 2005年6月日本図書センター刊)の第一巻の、林さん自身の「あとがき」や、当時の編集者だった橋中雄二さんの「解説」を参考にして紹介してみたい。
「あとがき」によると、林さんは、『祭りの場』を新しい人生のスタートラインにするつもりのようだった。二十三年間続けた結婚生活を解消し、この作品を書き上げたら食べるために勤めに出よう、そう決めていたのである。
『祭りの場』を書き上げたあと、林さんがとった行動はとても奇妙なものだった。
原稿を茶封筒に入れると何冊かの文芸誌をひろげて、私は編集長の名前をみた。「群像」編集長の、大村彦次郎氏の名が目に入った。この人なら読んでくれるかもしれない、怖いもの知らずの素人、編集長へ名指して原稿を送った。
「なぜか暖かい人柄を感じた」とは、林さん独特の第六感が働いたのだろう。
大村彦次郎は長く上司だったから、私などは、とてもオソロしくて、自分が書いた生の原稿を送るなんて大胆不敵なことはできない。
そして、大村編集長宛てに送られた原稿は、その後、もっと数奇な動きをする。
橋中雄二さんの「解説」によると、
一月、「群像」新人賞の部内選考会議が始まり、作品にもう一つ恵まれないという経過だったので、大村は、下読みから上がってきた作品の再度の洗い直しを要請した。しかし、次の会議で、大村自身が、おそらく下読みを通していない、所謂ご投稿原稿の中から、この『祭りの場』を探し出してきた。
大村さんから、次に読むように手渡された橋中さんは、この作品を一読し、文学的に破格である上、作者がどうしても書かねばならないという必然もはっきり読みとれて、深く感動するのである。
こうして、『祭りの場』は、群像新人賞の最終候補に残り、選考委員会でほぼ満場一致で受賞作となった。
ちなみに、このときの選考委員は、井上光晴さん、遠藤周作さん、小島信夫さん、埴谷雄高さん、それに福永武彦さんの5人であり、翌1976年、村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』を受賞作に選出したのも、この委員会なのである。
私事になるが、私は、1975年に、大村さんが「群像」編集部を去り、橋中さんが編集長となった年に、その大村さんとすれ違うようにして、大衆小説誌「小説現代」編集部から、純文学雑誌「群像」に異動した。
橋中さんが、「解説」で、大村さんのことを、
一九七三(昭和四八)年九月号から一九七五(昭和五〇)年九月号まで二年余、彼の編集者生活の中でもつらい二年だったろうと思う。
と書いている通り、大村さんが、「小説現代」編集長から、「群像」編集長として異動したときの、反響はまことに酷いものだった。
東京新聞の、辛口で有名だった名物コラム「大波小波」の中で、大衆小説の大物編集長を、純文学の老舗「群像」編集長に据えたところを見ると、講談社は「群像」を大衆小説化するつもりなのであろう、というようなことを書かれたことでも明らかなように、大村さんは特に「文壇」と言われた世界に棲む人たちに、いわく言い難い形の抵抗を受けた。
その余震がいまだ冷めない時期に、私も慣れ親しんだ大衆小説の編集部から、異動したのである。なんとはなしに疑いのこもった眼差しで見てくる作家もいた。ただ、大村さんが編集長だった2年間で耕した新しい純文学への再生が受け入れられつつあることもあって、あまり気に掛けないようにして過ごした純文学の世界は、やっぱり面白いもので、私は、ついつい7年も過ごすことになる。
さて、私のことはともかく、林さんの『祭りの場』は、続けて、その年の芥川賞の候補になった。
田村さんは、連載の中で、原爆をテーマにして書く林さんに対する、中上健次さんの反応を書いている。
1982(昭和57)年2月発行の文芸誌「群像」に掲載された「創作合評」での、中上さんの発言を引いて、「原爆を書けば文学になると思っている『精神の緊張を欠いた状態』だとおとしめ、林を『文学の場における原爆ファシスト』であると決めつけた」と書いている。
なるほど、中上さんの批判は厳しいものがあるが、芥川賞の選考委員だった安岡章太郎さんの『祭りの場』受賞反対の論も厳しいものだった。
その時の、芥川賞の選考委員は9人だった。選評の表題を拾って、それぞれも選考委員の『祭りの場』に対する選評を読んでみる。井上靖さんは、「『祭りの場』をとる」、大岡昇平「人を打つ力」、瀧井孝作「冴えた筆」、中村光夫「肉筆の味」、永井龍男「激しく迫る主題」、舟橋聖一「林京子の力作」とあり、丹羽文雄は「読後感」とあって、『祭りの場』には一行「当選作を別にして」とだけ触れていて、安岡章太郎さんは「該当作見当たらず」、吉行淳之介さんは「感想いろいろ」と表題している。
舟橋聖一は、選評の中で『祭りの場』が、「九選考委員のうち七・五票も得たのも当然だ」と書いている。
では、反対票の1.5票は、誰の票だろう。
吉行さんは、「しっかりした文章で感心したが、各節のおわりに必ずすてゼリフのような数行があり、そこに三十年の時の流れを感じさせて面白いのだが、その部分の発想が不統一で、戦争体験に十分モトデをかけたかどうか疑わしくなるところがある」と、やや否定的な感じである。
安岡章太郎さんの評が一番アタリがきつく、「該当作見当たらず」と題して、『祭りの場』に関しては、「私には、事実としての感動は重く大きかったが、それが文学の感動にはならなかった。とくに《学徒動員したのは》というような名詞を勝手に動詞につくりかえる言い方には、私は非常に抵抗をおぼえた。」と評している。
後日、中上さんが指摘しているように、被爆という事実としての重い感動が、果たして文学的感動になっているかという疑問を持って、安岡さんも評価しなかったのであろう。
ところで、私は林さんが、『祭りの場』で、新人賞と芥川賞を受賞したその年に、「群像」編集部に異動したのであるが、時期が少しずれていたせいもあるのか、『祭りの場』が起こした喧騒とは無縁だった。ただ、すぐに『祭りの場』を読んで、私は、被爆から三十年経って、その年月をかけた人生が、林さんの生々しい被曝の体験から、深化させたものや削ぎ落としたものがあり、その結果、見事に文学的な表現に昇華されていると思った。
橋中さんが、林さんを担当するよう私に言ったのは、異動から、少し経ってのことだった。
初めて林さんに会ったのはどういうシチュエーションだったか記憶にない。ただ、ひと言でいうと、勁い作品の印象とはかけ離れた、たおやかで、初々しい感じがする新人作家だという印象を持った。『祭りの場』の中にしばしば表れる、勁い表現に驚かされていたから、それとは正反対の印象を受けて、ショックに近いものを感じたのだ。
『祭りの場』の勁い表現には、ちょっと拾い上げただけで、こんなものがある。傍点は私が打った。
「きらびやかなガラス窓のために全身がガラスまみれの針ねずみになった」
「ほぼ同数の七万四九九人が真夏の日照りの中に皮をはがれて放り出された。いなばの白兎と同じだ」
「被爆者は肉のつららを全身にたれさげて、原っぱに立っていた」
「老女の体は肉がぼろぼろにはがれて、モップ状になっていて」
「新じゃがいもの薄皮状の皮を両腕にフリルのように垂れさげている火傷もあった」
私は、林さんに、短篇連作を描いてみないかと持ちかけた。林さんが言うように、受賞後、はじめての作品である。私は、担当編集者として、原爆という事実の重さを、成熟した文学表現で表したと言われるようにしたい、中上健次さんや安岡章太郎さんにぐうの音を吐かせてみたいと思ったのだ。それには、一片一語の無駄な表現をも許さない短篇小説を描いてほしい。
私のそういう要求に、まず、林さんは、書けるだろうかと不安を漏らした。
林さんも、新人賞をとったばかりの新人作家だ。そして、私も純文学分野では、異動になったばかりの新人編集者だ。
「ねえ、林さん。新人作家と新人編集者が二人三脚で取り組むにはうってつけの仕事です。やりましょう」
私はそう言って、林さんを鼓舞した。
しばらくして、林さんは、コクヨの深緑色の罫の、ごく普通の原稿用紙に、最初の作品を書いてきた。
『空罐』と題してあった。短篇らしいいい題だと思った。
赤く、炎でただれた蓋のない空き缶に、被爆で死んだ両親のお骨を入れて、教室の机に置いている女の子の話を含む、多重層の作品であった。いくつもの素材が織りなす、とても重い作品であった。私はこの重いテーマの作品を前に、技術的なことの何が言えるだろうと思った。
しかし、二人三脚で短篇連作をやろうと持ちかけたのは私である。そして、『空罐』には、短篇小説として、キズがあった。それが何だったか今となっては思い出せないのであるが、いくつか直してくれるように頼んだ。
林さんは、いかにも新人作家らしく、私が出す指摘のいちいちを頷いて聞いていた。
そうして、指摘した原稿を持って帰って、直すことにした。
その作業の間、私は緊張しっぱなしだった。
芥川賞の選考委員である安岡章太郎さんが、選評で指摘した《学徒動員したのは》のことに関して、林さんは、「しかし、『学徒動員した』の使い方は、その頃私たちが使っていた、時代についた言葉として、そのまま残していきたい」と抵抗しているのである。そのことがチラチラしたのである。強い意志の持ち主である。
次に会った時、林さんから、直しを入れた原稿を手渡された。
私は驚いた。その直しは完璧だったのである。
その旨を伝えると、林さんの顔に、心底、ホッとした表情が浮かんだ。
それが、いま出版されている『ギヤマン ビードロ』のはじめの短篇『空罐』である。
今読んでも隙のない、見事な短篇小説に仕上がっているから、ぜひ読んでいただきたい。
私が、その経験から学んだことは、編集者が新人作家に書き直しを頼んだ際、80点で書き直してくる作家は、まあ、食べていける作家になる。しかし、林さんのように、編集者がこう直してくれば100点だなと思っている上を行き、120点で返してくる新人作家がいたら、それは多くの賞を総なめにするような凄い作家になるということである。
短編集『ギヤマン ビードロ』の短編を12回続ける中で、林さんも文章的な修行をしたと思うが、私も編集者として貴重な修行をしたと思っている。この作品に、文部大臣芸術選奨を授章するという内示があったとき、林さんは、「被爆者としては国からの栄誉を受けるわけにはいかない」と言って、この賞を拒否した。
私は、林さんがとった、この態度に、同志として、敬服するのみである。
今、日本の社会の中で、怪しげな論拠で原発を持ち続けようとか、原爆の傘のおかげで平和だとか、もっと極端には、もう原爆を持とうという論がはびこるようになっている気がする。そのような論を唱えている人は、どうか林さんの『祭りの場』か、もっと短い『空罐』を読んでほしいと思う。そして、林さんの目の前で、その貧しく怪しげな持論を披露できるかどうか考えてほしいと思う。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第31話 村松友視さんの作家の佇まい連載](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/06/secret-story_31_banar_t-e1749620592694.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第30話 中島らもさんの小説](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/05/secret-story_30_banar_t-e1747214926119.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第29話 桐野夏生さんとEdgar Award](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/04/secret-story_29_banar_t_-e1744880639489.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第28話 阿部牧郎さんと直木賞](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/03/secret-story_28_banar_t.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第27話 色川さんと那須の土地](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/02/secret-story_27_banar_t.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第32話 林京子さんの短篇連作](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/07/secret-story_32_banar-600x315.png)