【直木賞・真藤順丈『宝島』が受賞!】第160回候補作を徹底解説

2019年1月16日に発表された、第160回直木賞。文芸評論家の末國善己氏が、今回も予想! 結果は、真藤順丈氏の『宝島』でしたが、当初の予想はどうだったのでしょうか? 候補作5作品のあらすじと、その評価ポイントをじっくり解説した記事を、ぜひ振り返ってみてください!
前回の直木賞(第159回)を振り返り!
今回の直木賞予想も、前回の答え合わせから始めたい。
第159回の直木賞は、窪美澄『じっと手を見る』を本命、上田早夕里『破滅の王』を対抗、穴を受賞作なしと予想した。結果は島本理生『ファーストラヴ』だったので、またも外れとなった。これで予想は、2勝2敗である。
選考委員の北方謙三が行った会見によると、まず本城雅人『傍流の記者』、湊かなえ『未来』、木下昌輝『宇喜多の楽土』が落ちたという。初回投票では窪美澄『じっと手を見る』が最も得票を集めたが、議論を重ねるうちに『ファーストラヴ』が逆転し、受賞作なしもあり得たほどギリギリで当落が決まったようだ。前回の予想では、『傍流の記者』『未来』『宇喜多の楽土』は議論にもならないこと、作品のクオリティでは『じっと手を見る』が上なこと、小粒な作品が並んだので功労賞的に受賞作が決まる可能性が高く、その場合は『じっと手を見る』と『ファーストラヴ』のどちらかになるところまでは読み通りであり、最後の二者択一で判断を誤っただけなので悔いはない(試合には負けたが、勝負には勝った感じである)。
前回、前々回(門井慶喜『銀河鉄道の父』)は新鋭、中堅の作品が候補作になった直木賞だが、その傾向は今回も続いている。2017年に初の単著を出し、初の直木賞候補になった今村翔吾『童の神』、2000年にデビューし、2回目の直木賞候補になった垣根涼介『信長の原理』、2008年にデビューし、初の直木賞候補となった真藤順丈『宝島』、2013年に初の単著を出し、2回目の直木賞候補となった深緑野分『ベルリンは晴れているか』、2003年にデビューし、3回目の直木賞候補となった森見登美彦『熱帯』が争う今回も、まさに若手の戦い。しかも小粒な作品ばかりだった前回とは異なり、各作家の代表作になり得る大作、傑作が並んでいるので、前回とは逆の意味で予想は難しいが、これは嬉しい悲鳴といえる。
第160回の節目となる直木賞候補作の概観は以上。これらも踏まえて、候補作を作家名の50音順で紹介していきたい。
選考委員は前回と変わらず、浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆきの9名である。
候補作品別・「ココが読みどころ!」「ココがもう少し!」
今村翔吾『童の神』

https://www.amazon.co.jp/dp/4758413290
今村翔吾は、第19回伊豆文学賞小説・随筆・紀行文部門最優秀賞を受賞した「蹴れ、彦五郎」、第23回九州さが大衆文学賞大賞・笹沢左保賞を受賞した「狐の城」を経て、2017年3月に文庫書き下ろし時代小説『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビューした。
「火喰鳥」の異名を持つ凄腕の定火消・松永源吾が、出羽新庄藩の火消組を再建していく物語は、すぐにシリーズ化され現在まで7巻が刊行されている。今村の初の単行本で、第10回角川春樹小説賞の受賞したのが伝奇小説『童の神』である。
文庫書き下ろし時代小説は、書評などで取り上げられる機会が少ないだけに、初めて今村の名を聞く方も少なくないだろう。ただ〈羽州ぼろ鳶組〉シリーズは、競争が激しい文庫書き下ろし時代小説の中でも近年稀に見るほどのヒット作であり、第7回歴史時代作家クラブ賞・文庫書き下ろし新人賞も受賞しているので、今村が人気と実力を兼ね備えることが実感できるはずだ。
『童の神』の舞台は平安時代。貴顕の世話をする奴、東国や山奥で暮らす異民族などは、「童」の蔑称で呼ばれていた。醍醐天皇の子ながら「童」が差別されない社会を目指す源高明は、土蜘蛛、鬼、夷といった恐ろしい名を付けられた「童」たちと決起する。だが同志だったはずの源満仲の裏切りで決起は失敗し、高明は失脚した。それから約二十年後。生き残った土蜘蛛の蓮茂から武術と学問を学んだ桜暁丸は、全国から集まった「童」たちと大江山に籠り、自由と平等を勝ち取るための戦いを始める。一方、朝廷は、満仲の子・頼光と四天王に、「童」たちの鎮圧を命じる。
今村は、高明の謀叛が満仲の密告で失敗した安和の変が、実は平等な社会を作る改革運動だったとして歴史を読み替えたり、桜暁丸ら「童」の宿敵を、鬼や土蜘蛛を退治した伝説で有名な頼光と四天王にしたりと、史実と巷説を自在に織り交ぜながら迫力ある物語を紡いでいくので、最後までスリリングな展開が続く。
「童」を搾取し差別している平安時代の朝廷は、明らかに、格差が広がり多様性を認めない風潮が強まる現代日本に重ねられている。高いエンターテインメント性の中に、重厚なテーマを織り込んだところは十分に評価できるが、ほかにも現代の社会問題を取り上げた候補作はあるので、それらとの比較になると寓話性が高い『童の神』はメッセージ性が弱いと判断される危険がある。また時代考証を細かくチェックする選考委員は少なくないので、登場人物の価値観や台詞まわしが現代的過ぎるところは、批判される可能性が高い。
垣根涼介『信長の原理』
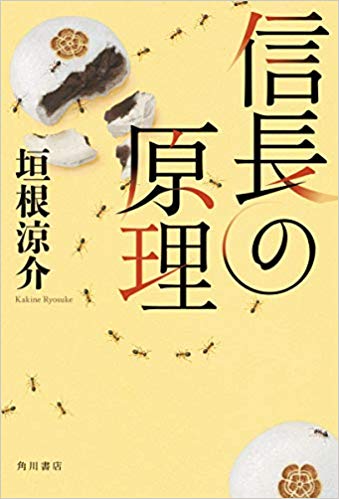
https://www.amazon.co.jp/dp/4041028388
2000年に、『午前三時のルースター』で第17回サントリーミステリー大賞の大賞と読者賞をダブル受賞してデビューした垣根涼介は、『ワイルド・ソウル』で第6回大藪春彦賞、第25回吉川英治文学新人賞、第57回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門をトリプル受賞。『君たちに明日はない』では第18回山本周五郎賞を受賞するなど、現代ミステリーで数々の賞を受賞している。ただ直木賞の候補になったのは歴史時代小説ばかりで、今回の『信長の原理』は、第156回の候補になった『室町無頼』に続く2回目のノミネートである。
織田信長が、組織全体の二割の人員が大部分の利益を生み出しているという「パレートの法則」を知っていたとする『信長の原理』は、確率論のモンティ・ホール問題を使い、明智光秀が織田信長に叛いた理由に迫った『光秀の定理』の姉妹編的な作品だ。
歴史小説で描かれる信長は、家臣を家柄や情実ではなく、実力だけで評価する冷徹な武将とされることが多い。垣根もこのラインを踏襲しているが、信長が完全実力主義の人事を行うことができたのは、孤独だった幼い頃に蟻を観察するうち、働き蟻がよく働く二割、普通の六割、働かない二割の比率になっている事実に気付いたからとしている。
信長は、直属部隊を鍛える一方で、滝川一益、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)、明智光秀らを外部から登用し、家臣を競わせることで組織を強化していく。こうした経営方針は、労働力が流動化し、成果主義が導入された現代の企業を彷彿させる。それだけに、宮仕えをしていると、軍事の専門家に徹する一益、本来の性格を隠しムードメーカーになる藤吉郎、名家出身の立場を利用し発言権を維持する柴田勝家など、それぞれの戦略で上を目指す武将たち中に、必ず共感できる人物が見つかるのではないか。
家臣に過大な要求をする信長、主君の期待に応えようと奮闘する家臣たちの葛藤を、日本社会の重要課題となった“働き方改革”になぞらえた着眼点は見事だった。ただパレートの法則を使って信長を描くと聞けば、どのような展開になるかは比較的簡単に想像できるが、その範囲を超えていないのは残念だった。また垣根が創出した信長は、司馬遼太郎『国盗り物語』に出てきた家臣を使い捨てにする信長の正統的な発展系であり、垣根オリジナルの部分があまり見えてこなかった。終盤になると、信長が働き蟻の法則を援用しながら誰が謀叛を起こすか推理する場面もあるが、組織の中で働く人間と働かない人間が出るという話と、誰が裏切るかはレベルが違うはずなのに、それを強引にまとめるなど無理筋な展開が散見されるのも気になった。
真藤順丈『宝島』
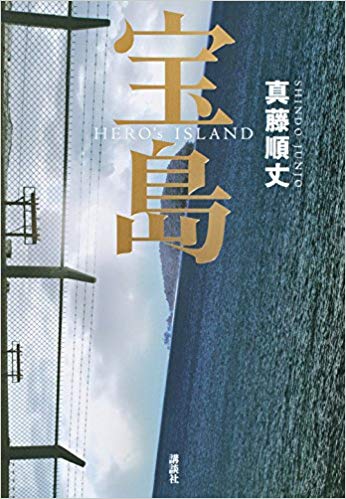
https://www.amazon.co.jp/dp/4065118638
真藤順丈は、『地図男』で第3回ダ・ヴィンチ文学賞の大賞を、『庵堂三兄弟の聖職』で第15回日本ホラー小説大賞の大賞を、『東京ヴァンパイア・ファイナンス』で第15回電撃小説大賞の銀賞を、『RANK』で第3回ポプラ社小説大賞の特別賞を立て続けに受賞する鮮烈なデビューを飾った。沖縄県の戦後史を題材にした『宝島』は、真藤の初の直木賞候補作である。
『宝島』は、2018年10月に第9回山田風太郎賞を受賞した。この時の候補作には垣根涼介『信長の原理』もあったので、『宝島』が二冠を達成するか、『信長の原理』がリベンジを果たすかも注目である。
戦後の沖縄では、米軍基地から物資を盗む「戦果アギヤー」たちが活躍し、庶民の人気を集めていた。少年時代に沖縄戦を経験し生き延びた「戦果アギヤー」のオンちゃんは、米軍から盗み出した食料や医薬品を惜しげもなく貧しい人たちに与え、英雄視されていた。1952年、オンちゃんのグループは、周到に計画を立て嘉手納基地に潜入した。だが米兵に発見され追われる身になり、その混乱でオンちゃんが姿を消す。ここから物語は、オンちゃんの仲間で警察官になるグスク、オンちゃんの弟でヤクザになるレイ、長身美少女で教師になるヤマコの3人を軸に、沖縄の本土復帰までの20年の歴史をたどっていく。
嘉手納基地という巨大な密室からオンちゃんが消えた本格ミステリー的な謎から始まる物語は、米兵の犯罪が頻発しているのに、捜査が制限されることに不満を募らせるグスクを主人公にした警察小説、裏ビジネスに従事するレイがからむクライムノベル、米軍機の墜落事故で教え子を亡くしたヤマコが始める政治運動、さらに沖縄の信仰や風俗を使った幻想小説的な要素も加わるので、どのジャンルが好きでも満足できるはずだ。
真藤は、実際に起きた事件を意外な形で読み替えたり、瀬長亀次郎、屋良朝苗、ポール・W・キャラウェイといった実在の人物を登場させたりすることで、沖縄の民意を無視し、アメリカと日本が頭ごなしに沖縄の方針を決めてきた戦後のあり方を徹底して暴いていく。これは現在の日本政府と沖縄の対立まで続いているので、『宝島』はなぜ沖縄と本土の考え方はズレるのかを知る上でも示唆に富む。ただ真藤は、沖縄の“怨念”を掘り起こすダークな物語にするのではなく、ある時はしたたかに、ある時は南国的な陽気さで危機に対処する沖縄人のパワーをクローズアップしているので、読後感は悪くない。特に、オンちゃん消失の謎をロジカルに解明しつつ、「宝島」の意味を明らかにするラストは、胸を熱くしてくれる。
不安材料としては、沖縄はアクチュアルな問題だけに、一家言持った選考委員がいるかもしれず、掘り下げが足りない、時代考証が甘い、小説の題材にするには時期尚早などの批判がでるかもしれない。
深緑野分『ベルリンは晴れているか』

https://www.amazon.co.jp/dp/448080482X
深緑野分は、2010年に「オーブランの少女」が第7回ミステリーズ!新人賞の佳作となり、2013年に同作を含む連作集『オーブランの少女』を上梓してデビューした。寡作の深緑だが、アメリカ軍の兵士兼コックが、第二次大戦末期のヨーロッパで起きた奇妙な事件に挑む『戦場のコックたち』が第154回直木賞の候補になり、その続編的な『ベルリンは晴れているか』で2回目の直木賞候補になっており、直木賞に関しては打率が高い。
物語の舞台は、ナチス・ドイツが敗北し、アメリカ、ソ連、イギリス、フランスに共同統治されたベルリン。米軍の兵員食堂で働くドイツ人の少女アウグステは、米軍憲兵隊に連行され、ソ連のNKVD(内務人民委員部)のドブリギン大尉に引き渡される。ドブリギンによると、音楽家のクリストフがアメリカ製の歯磨き粉に仕込まれた毒で殺されたという。クリストフと妻のフレデリカは、戦時中に両親を亡くしナチスに追われていたアウグステを匿ってくれた恩人だった。首脳会談を目前に控えたポツダムへ行き、クリストフ殺しの容疑者とされるフレデリカの甥エーリヒを捜せと命じられたアウグステは、ドブリギンが用意した泥棒でユダヤ人だというカフカを相棒に旅立つ。
物語は、アウグステがクリストフ殺しの謎とエーリヒの居場所を調べる現在のパートと、ナチスがワイマール体制下のリベラルな空気を一掃した歴史をカットバックしながら進む。世界恐慌を背景にナチスが台頭し始めた頃に生まれたアウグステは、子供を狙った猟奇的な連続殺人犯がユダヤ人とされたり、障害を持つ近所の子供がナチスに連れて行かれたまま帰ってこなかったりした現実を見て育った。祖国の純粋性を守るため、マイノリティ排斥したナチスの思想は、現代の日本を始め全世界的に広がりつつある。そのため、灰燼に帰した祖国を前に、政府の暴走を許した過去を悔いるドイツ人の姿は、とても過去の物語とは思えない生々しさがある。
事件とは無関係そうな記述が重要な手掛かりだと判明したり、だまし絵のように見ていた構図が反転したりする『ベルリンは晴れているか』は、耳に心地よい美辞麗句を疑い、情報の裏を読むことの大切さに気付かせてくれるだけに、トリックとテーマが密接に結び付いている。ただ、ヨーロッパを舞台に、日本人が誰一人登場しなかった『戦場のコックたち』は、「どうしてアメリカ軍の兵士の物語を書かなければならないのか」「現代の日本人がいくら勉強してそれを書いたとしても、根底にあるものはやはり借りものであり、本当のことを描ききっていないと思う」(林真理子)、「この種の小説には必要不可欠な、戦争観や哲学性には不足しているとも思え、あえて強く推す根拠を見出せなかった」(浅田次郎)など、選考委員の厳しい意見にさらされたので、同じ方法論を使っている『ベルリンは晴れているか』も、改善が見られないとして同じ批判を受ける危険性がある。
森見登美彦『熱帯』

https://www.amazon.co.jp/dp/4163907572
2003年に『太陽の塔』で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞してデビューした森見登美彦は、『夜は短し歩けよ乙女』で第20回山本周五郎賞と第3回大学読書人大賞を受賞。『ペンギン・ハイウェイ』で第31回日本SF大賞を受賞するなど、順調に作家としてのキャリアを積み上げている。『熱帯』は、第137回の候補となった『夜は短し歩けよ乙女』、第156回の候補となった『夜行』に続く3回目のノミネート作である。
森見自身と思われる作家の「私」は、小説が書けず読書に逃避していた。ある日『千夜一夜物語』を読み始めた「私」は、大学時代に古書店で佐山尚一の『熱帯』なる小説を買ったことを思い出す。「私」は『熱帯』を面白く読み進めていたが、結末を読む前に忽然と消えてしまった。「私」は『熱帯』を探したが、結局見付けることはできなかった。
仕事で上京した「私」は、かつての同僚に誘われ「沈黙読書会」なる会合に参加する。そこで「私」は、白石さんという女性が『熱帯』を持っていることに気付く。白石さんも『熱帯』を読んでいたが、途中で消えてしまったという。いつか『熱帯』を読み終えたいと考えていた白石さんは、『熱帯』を読んだ経験のある池内さんと出合う。池内さんによると、『熱帯』に接した人たちは「学団」なる組織を作り、それぞれの記憶を持ち寄って『熱帯』を再構築しているという。
池内さんに誘われ、「学団」の会合に参加した白石さんは、メンバーの一人の千夜さんに小石川の自宅に招待される。千夜さんは『熱帯』の謎が京都にあると確信し一人で現地に向かうが、音信不通になる。どうも千夜さんは、『熱帯』の作者・佐山尚一と知り合いだったらしい。そして白石さんも、千夜さんを追って京都へ向かった池内さんと連絡が取れなくなる。
本好きなら、読んでいる途中で持ち主の前から消える奇書という魅惑的な設定だけで、作品世界に引き込まれてしまうのではないだろうか。物語は『千夜一夜物語』のように、「学団」のメンバーが、『熱帯』をめぐって経験した冒険譚を語ることで進むのだが、次第に現実と幻想の境が曖昧になり、「学団」のメンバーが、『熱帯』の登場人物のようになるなど迷路のように入り組んでいく。
『熱帯』がどんな物語かを調べる展開は、欲しい本を探す、楽しみながら本を読み続きを予想する、読んだ本を誰かと語り合うといった読書の醍醐味を再現したといえる。その意味で『熱帯』は、なぜ人は物語を欲し、小説を書いたり、読書に勤しんだりするのか、その本質を突き詰めた作品なのである。小説家が、小説とは何かに挑んだだけに、このテーマには選考委員も興味を持つように思えるが、同業者ゆえに納得できるとなるか、反対に甘い議論と突き放されるか、判断がわかれるかもしれない。
ズバリ予想!本命は?対抗は?
各候補作の読みどころを踏まえ、第160回直木賞を予想してみたい。
本命は森見登美彦『熱帯』。他の4作が、それぞれに現代日本が直面している問題を描いているだけに、社会的なテーマが遠景に置かれている『熱帯』がどのように評価されるのか微妙なところもあるが、作家として小説とは何かという根源的な問題に切り込んだ心意気は、同業者にこそ評価されると信じたい。今回の候補作のうち、文藝春秋刊は『熱帯』だけなので、そこもプラス材料になるはずだ。
対抗は、真藤順丈『宝島』。沖縄問題は、辺野古の埋め立ても含め、日本人なら真剣に向き合わなければならない課題である。そこに正面から切り込み、一級のエンターテインメントに仕立てた手腕は、直木賞に相応しいと考える。
穴は、垣根涼介『信長の原理』。前回は候補作が小粒で功労賞的に決まったように思えるが、今回はハイレベルな戦い過ぎて、やはり功労賞的に落ち着く可能性がある。その場合は、キャリアが長い垣根が有利になるだろう。
直木賞の選考会は、2019年1月16日、築地の新喜楽で開かれる。結果を楽しみに待ちたい。
筆者・末國善己 プロフィール

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』などがある。
初出:P+D MAGAZINE(2019/01/11)





