SM作家・美咲凌介による「SMを描いた純文学」10選

「俺ってドMかも」「あたしって少しSなの」
テレビに出てくる美男美女がこんなセリフを吐いても、「ああ、そうなの?」としか思われなくなった今日この頃、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。SM小説家の美咲凌介です。
冒頭述べたように、今ではSMというものもすっかり市民権を得たかのように感じられます。けれども、一口にSMと言っても、その実態は多様性に満ちています。ここでは、SM(的な何か)を描いた10の文学作品を通じて、一筋縄ではいかぬこの世界の多様性をご紹介したいと思います。
1 サディストの語源となった男の「反キリスト」的思想
『新ジュスチーヌ』 マルキ・ド・サド
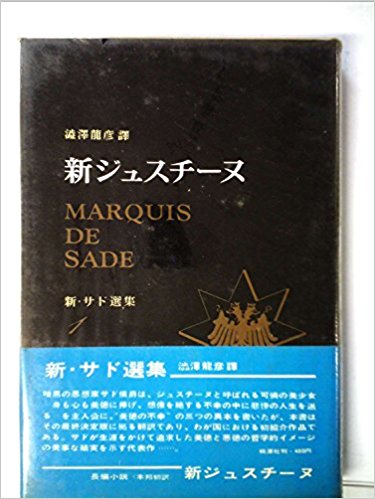
https://www.amazon.co.jp/dp/B000JB28LO
「他人の生命を奪うのか!」と言うなりジェルナンドは、どっと吹き出した、「ああ、そいつはすばらしい! わかるわかる、その楽しさは、わしにもよく理解できるよ。いやもう、想像しただけでも大へんなことじゃ! 殺す、盗む、毒殺する、火をつける……これくらい自然なことは世にもあるまいな。……略……」(『新ジュスチーヌ』澁澤龍彦 訳)
ご存知の通りサディズムという言葉は、マルキ・ド・サドの名から生まれました。サドは、ジュスチーヌという名の心優しく善良で美しい女が数々のサディストにいたぶられていく物語を長年に渡って書き続けましたが、最後に書き上げたのがこの『新ジュスチーヌ』(1797年)です。この作品で、サドの思想は完成に至ったと言ってよいでしょう。その思想とは、強者の力の行使こそを崇高なものとする、というものでした。そして、それは一貫して強い「反道徳」「反キリスト」的態度を保持しています。
「いや、それは逆ですよ」とブレサックが答えた。「宗教の観念が生まれたのは、恐怖と希望の結果でした。その宗教という観念を養い育てるために、人間はその愚劣な神の慈愛という、ありもしないものの上に道徳を築き上げたのです」
「どっちが原因でどっちが結果であれ、とにかくわしは」とジェルナンドは、シャンパンを一気に飲み干して言った、「間違いのないところ、その二つに対して、この上ない嫌悪の情をいだいているよ。わしの不道徳は、わしの無神論に基礎を置いているのでな、わしは宗教を破壊するのと同じ魅力、同じエネルギーをもって、もっぱら社会の絆を愚弄しているのじゃ」(『新ジュスチーヌ』 澁澤龍彦 訳)
サディズムは、キリスト教的道徳に対する反抗あるいは批判から始まった。このことは、心に留めておくべき点でしょう。
2 サディストを調教・育成するマゾヒスト
『毛皮を着たヴィーナス』 L・ザッヘル=マゾッホ
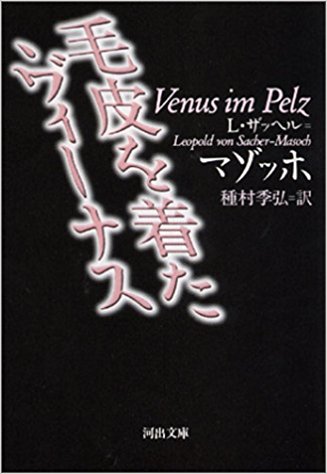
https://www.amazon.co.jp/dp/4309462448
「いいえ、ワンダ」と私は言った、「私は自分自身よりあなたの方を愛しているのです。生かすなり殺すなりあなたのお好きなようになさって下さい。あなたのお気に召すように、いや、あなたの高慢のほんの一時のなぐさみでもいいから、本気で私を相手にしてくれていいのです」
「ゼヴェリーン!」
「私を足で踏んづけて下さい!」そう叫ぶと、私は顔面を地につけて彼女の前にひれ伏した。
「道化芝居は大嫌い」ワンダがしびれをきらしたように言った。
「さあ、本気で私を痛めつけて下さい」(『毛皮を着たヴィーナス』 種村季弘 訳)
サディズムという言葉がサドという名から生まれたように、マゾヒズムという言葉は、『毛皮を着たヴィーナス』(1871年)を著したL・ザッヘル=マゾッホという小説家の名から生まれました。
ゼヴェリーンという青年は、自分を苦悩の中に快楽を見出す「超官能的な人間」と認識しています。彼は、ワンダという若い未亡人に理想の女性像を見出し、その奴隷となることを熱烈に望むのですが、ワンダは当惑を隠せません。そうしたワンダを、ゼヴェリーンが一人のサディストへと育て上げようとしているのが、上の引用部分です。
SMにおける「調教」と言えば、多くの人が「サディストがマゾヒストを調教する」というものを思い浮かべるでしょう。しかし、ここではそれが全く逆になっていて、マゾヒストがサディストを調教・育成していることに驚かされます。
しかし、それ以上に驚かされるのは、作者マゾッホの実生活でしょう。マゾッホは、ワンダを単なる文学上の存在としてだけではなく、現実の生身の存在として作り上げたのです。
いうまでもなくワンダという名のこの女性は実在しない。いや、それまでは実在しなかった、というべきだろう。というのは、驚くべきことに、この小説を発刊した一八七一年に、後にワンダ・フォン・マゾッホの名で半生の伴侶となるはずの女性が忽然として彼の前に立ち現れるのである。実の名はアウローラ・リューメリンというグラーツの貧民街に住むお針娘だった。ザッへル=マゾッホはこのアウローラを巧みに調教して貴婦人ワンダに仕立てた。小説の女主人公とそっくりにである。(種村季弘 『毛皮を着たヴィーナス』河出文庫 訳者あとがき)
マゾッホにとっては、小説と同じように、現実生活もまた一つの芸術作品だったのかもしれません。
3 乾いた笑いの中に横たわる幾つもの死体
『一万一千本の鞭』 ギヨーム・アポリネール
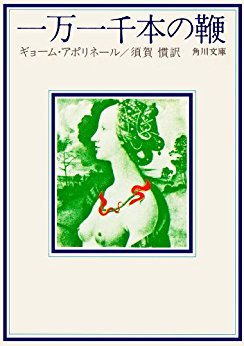
https://www.amazon.co.jp/dp/B009TPQRO0
「わたしは、自分の財産も愛情も、あなたの足許に投げ出しますよ。もしわたしがあなたをベッドにお連れしたら、続けて二十回も情熱を証明して見せられるんですがねえ。もしこれが噓だったら、一万一千人の処女の罰を受け、いや、一万一千本の鞭でたたかれてもかまいませんよ!」
……略……
「わたしはルーマニアのプリンスで、世襲の太守です」
「あたしは、キュルキュリーヌ・ダンコーヌ」と彼女が言った。「十九歳よ、今までにもう、色事でずば抜けた男の方十人ばかりのホーデンを空にし、十五人ほどの百万長者の懐を空にしてやったわ」(『一万一千本の鞭』 須賀慣 訳)
ギヨーム・アポリネールの書いた唯一の官能小説が、この『一万一千本の鞭』(1906年)です。引用部分は、ルーマニアの太守の家柄に生まれた若者モニイ・ヴィベスクが、プリンス・ヴィベスクと名乗ってパリに出向き、憧れのパリジェンヌに誘いをかける部分です。引用部を一読すればすぐに分かるように、この小説は軽い、乾いた、そして滑稽味あふれる文体でつづられています。トゥッサン・メトサン=モリニエによる「一九七〇年版のあとがき」(須賀慣 訳)では、この『一万一千本の鞭』の特徴として「真面目さの欠如」と「パロディ風な性格」が挙げられているほどです。
このどことなく朗らかな文体で、アポリネールはレイプ、同性愛、近親相姦、小児性愛、スカトロジーなど、ほとんどありとあらゆる異常性愛を描いていきます。そして、そこには常にサディズムとマゾヒズムの強烈な光が射しているのです。
物語の中盤からは、登場人物たちは(主人公であるモニイとその仲間を除くと)ほぼ決まったように死に至ります。以下は、プリンス・モニイがサディスティックな趣味を持つポーランド人の看護婦と一緒になって、マゾヒストであるロシアの負傷兵を痛めつけ、その挙句に看護婦を殺してしまう場面です。(このときモニイは、日露戦争中の日本軍の捕虜になっています。)
プリンスと看護婦は不幸な負傷兵の上に殺到すると、彼の着ているものをひんむいて、最後の戦闘で奪われ、地面に散らばっていたロシア軍の軍旗の柄をとるや、不幸な男を撲り始めた。彼の尻はひと打ちごとに飛び上り、うわ言を言い続けた。
「アア、愛するフロランス、きみの清らかな手はまだぼくを打つのかい?……略……」
娼婦のような看護婦は、いままでにないほど激しく叩きつけた。蒼白い、不幸な男の臀が持ち上り、あちこち色褪せた血痕をつけていた。モニイの心臓はキュッと緊る思いだった。そして改めて彼女の残忍さに気がつくと、彼の怒りはこの不届きな看護婦のほうに向かった。彼は女のスカートをまくり上げて、打ち始めた。……略……
彼は天才的なインスピレーションを感じ、看護婦が投げ捨てたもう一本の棒を手にすると、ポーランド女の裸の腹の上を太鼓のように叩き始めた。……略……
とうとう腹は裂けてしまった。モニイは相変わらず腹を叩き続けた。救護所の外には、これを戦闘開始の太鼓と聞きちがえた日本兵たちが集合していた。(『一万一千本の鞭』 須賀慣 訳)
モニイもまた、最後には死を迎えます。かつて自分の言った「一万一千本の鞭でたたかれてもかまいませんよ!」という言葉の通り、一万一千人の日本兵から鞭を受け、処刑されるのです。この作品には、サドに見られたキリスト教への反発などは存在しません。ただ、数々の異様な性愛の光景と、その結果である幾つもの死が、あっけらかんと存在しているのです。
4 精緻な支配と被支配の論理の中で輝くマゾヒストの欲望
『O嬢の物語』 ポーリーヌ・レア―ジュ

https://www.amazon.co.jp/dp/4309461050
……略……ぼくがきみを他人に与えたという事実は、ぼくにとって、きみがぼくのものであるということの一つの証拠であり、きみにとっても、そうでなければならないはずだ。自分のものでなければ、どうして他人に与えることができよう。(『O嬢の物語』 澁澤龍彦 訳)
『O嬢の物語』(1954年)は、ポーリーヌ・レア―ジュという女性名を名乗る謎の作者によって書かれました。その文体は、評論家ジャン・ポーランの「序 奴隷状態における幸福」において、「単なる心情の吐露というよりは、むしろ論文を思わせ」る、と評されています。
そして、その「論文」のような硬質な文体で繰り返し叙述されるのは、上の引用部にも見られる「自分の所有しているものだからこそ、他人に与えることができる」という論理です。
主人公のOは、恋人のルネによってロワッシーの城館へと送りこまれたのをきっかけに、ステファン卿というイギリス人、アンヌ・マリーという中年の女、そして最後には「司令官」と呼ばれる謎の人物へと、次々に引き渡されていきます。
ある人に対して自分をひらくという表現は、自分の秘密を打ち明け信頼する意味に使われるが、彼女にとっては、それが字義通りの肉体的な、しかも絶対的な唯一の意味しか持たなかった。なぜなら彼女は実際、ひらきうる身体じゅうのあらゆる部分をひらいていたからである。そして、それこそ彼女の存在理由であり、ルネと同じくステファン卿もまた、そのようなものとして彼女を理解しているようであった。だからサン・クルーでしたように、彼が友人のことを話す場合、もし自分が彼女を友人に紹介するとすれば、彼女は当然、友人の望みのままに自由にされることを覚悟しなければならない、ということを彼女に知らせるためでもあった。(『O嬢の物語』 澁澤龍彦 訳)
このように次から次へと引き渡されることで、Oは次第に一人のマゾヒストとして完成していくように見えます。つまり、「自分の所有しているものだからこそ、他人に与えることができる」という論理は、サディストの欲望のためというよりも、マゾヒストを磨き上げるために持ち出されたものだと思われるのです。
- 1
- 2



