連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:土井善晴(料理研究家)
料理研究家の土井善晴さんが家庭料理のことを考え続けてたどり着いたのが『一汁一菜でよいという提案』(グラフィック社)。そこには食卓が作るおいしい未来への優しい思いが込められていました。
第二十一回
料理が中心にあればみんなが幸せになる
ゲスト 土井善晴
(料理研究家)
Photograph:Hisaaki Mihara

土井善晴(左)、中島京子(右)
頑張っている女性を、応援したい
中島 今日、土井先生にお会いできるのを楽しみにしていたんです。私は、ずっと土井先生の大ファンで、献立に困ったらネットで先生の料理を検索しているんです。『一汁一菜でよいという提案』に出合ってからは、目から鱗がぽろぽろ落ちて、お料理をするのがすごく気楽に、そして面白くなりました。
土井 最高の褒め言葉をいただきました。ありがとうございます。
中島 これまで日本料理は「一汁三菜」が基本で、そこから「二汁五菜」「三汁七菜」など品数が増えていくものだと言われてきました。それが家庭料理とはいえ「一汁一菜」。ご飯とみそ汁と漬物だけでいいとおっしゃる。料理研究家としては、かなり思い切った提案ですが、どういう経緯でこの本をお書きになろうと思われたのですか。
土井 五、六年前から、「大人の食育」をテーマに勉強会を開いているんですね。参加者のなかには妊婦さんや若いご夫婦の方もいらして、みなさん毎日どんな料理を作ろうか、ずいぶん悩んでいるそうなんです。献立を考えるのが悩み。「ええ悩みや」と、最初は思っていたのですが(笑)。
中島 私の友だちにも、毎日子どものお弁当を作るのが大変だという人がいます。最近は〝インスタ映え〟とかで、何種類もおかずを作って、きれいに詰めないといけないような風潮もあるらしいんですね。
土井 そのお母さんの悩みも、根っこはいっしょですね。聞いてみると、自分にできないことまでやらないと駄目だと、思い込んでいるんです。家庭料理なんだから、そんなにちゃんとしなくてもいいでしょう。できることでいいんじゃないですか、と言うと、みなさんほっとして明るくなる。
中島 それぞれの家庭で事情も違いますからね。でも、つい、まめにやっている人を基準にしてしまうんですよね。そういう悩みをお聞きになって、土井先生のほうから、この本を出したいと企画されたんですか?
土井 はい。私が出演している「おかずのクッキング」(テレビ朝日系)でも、「一汁一菜」をテーマにした回の反響がすごく良かったんですね。これは、もう今やらないと駄目やと確信して、自分の責任で書き始めました。
中島 いろいろな料理の専門家の方々が言ってきたことと、全く逆の内容です。執筆にあたっては、かなりご苦労されたと思いますが。
土井 これまで、短いコラムやエッセイのようなものは書いたことがあったけれど、「一汁一菜」というひとつのテーマで一冊の本を書き上げるのは初めての経験。最初は自信がなかったのですが、書いているといろいろなことを考えるでしょう。これまで自分のやってきたことが、くるっと全部つながったみたいな気がしたんですね。

土井 中島さんに、そうおっしゃっていただけたら、うれしいですね。
中島 今日本のお母さんたちを悩ませている、食卓にたくさんおかずが並んでいないといけないというプレッシャーはいつごろから出始めたのでしょう。
土井 やっぱり高度経済成長期ですね。当時放送されていたアメリカのファミリードラマを観ると、大きな冷蔵庫に食べものがいっぱいに詰まっていて、食卓の上にはさまざまなお料理が並んでいる。まさに豊かさの象徴。みんなアメリカのライフスタイルに憧れましたものね。
中島 実際はアメリカの家庭では、そんなにすごい料理はしないんですけれどね(笑)。
土井 たしかにね(笑)。当時は、ほとんどの家庭の女性が専業主婦でした。いいお母さんになるためには、いろいろなお料理を作って食卓を飾る。それが母親の鑑のようなイメージになったのだと思います。
中島 時代が変わったのにもかかわらず、専業主婦時代のお母さん像を、いまだにひきずっているんですね。
土井 自縄自縛というか、自分たちが作った理想の主婦像みたいなものに苦しめられているんですね。それでも女の人のすごいところは、仕事を持っているお母さんが当たり前になってきても、家のことも外の仕事と同じくらいに責任感を持ってやっている。その姿を見た旦那さんに、そんなに頑張らなくてもいいんじゃないって言われたら……。
中島 しかも、手伝ってくれるわけではないし。
土井 そうでしょう。自分が大切に思っていることを頑張るなって言われたら、気持ちの持って行き場がなくなってしまう。男性は知ってか知らずか、結構ひどいことを言う。だから、私は、すごく女性を応援してしまうんです。
中島 もうこのまま、働いているお母さんたちに聞かせてあげたい。みんな、うんうん、そうなのって、絶対に言うと思う。
土井 日本では、お金を払って食べているからと、お客さんのほうが知らない間に偉くなっている。家のなかでも食べる側が、あれ食べたい、これ食べたいと、リクエストする。母親も含めて、料理を作る人を大切にしないですよね。
中島 きょうは何? ハンバーグじゃないの? お魚は嫌だななんて。家族はあまり罪の意識なく言ってしまいますね。
土井 そうでしょう。でも欧米では、料理店のシェフに限らず、家庭でも料理を作る人をとっても大切にします。
中島 一生にどれくらい食べることに時間を費やしているのか考えると、本当に重要なことですよね。
土井 そう、家では、台所が一番大事な場所なんです。
家庭料理にレシピなんていらない
中島 ふたをちょっとずらして、鍋が笑ってるくらいの火加減にしてくださいとか、お肉を入れて、お風呂に入ってるみたいな気持ちよさそうな温度で煮ますとか……。土井先生は言葉の感覚がすごく優しい。言葉を大事にしていらっしゃることがわかります。
土井 正しい使い方かどうかわからないですけどね。
中島 料理によりそって語っているからだと思うのですが、聞いている私たちにもその料理のおいしさがふわりと伝わってきます。

中島 私が先生の言葉で好きなのは「きれいな味」です。見て美しく、清潔感があって、雑じゃない旨さ。
土井 私たち日本人は、昔からそういう言い方を聞いて育っているんです。だから、脳みそで意識化された肉の味や寿司のおいしさだけじゃなく、みそ汁を飲んで、もう何ていうか、本当に幸せな気持ちになる。そういう心地よいおいしさって、いわゆる脳じゃないところで感じるおいしさなんです。
中島 哲学的なお話になってきましたね。
土井 何でもそうですけど、意識ばかり強くなって、感覚をみんな無視。捨てていってるような気がしませんか。だから料理もレシピみたいな意識の塊が必要とされる。でもね、特に和食には、本当はレシピってないんです。
中島 今朝、インターネットで検索したら、「一汁一菜のレシピ」っていうページが出てきたんです。まさか土井先生じゃないだろうなと思ったら、やっぱり違う人でした(笑)。
土井 みそ汁なんか好きなように作ったらいいと言ってる人が、レシピブックなんて出したらおかしいですよね。だけどもね、『一汁一菜でよいという提案』を出してから、このみそ汁の作り方のレシピ本を書いてほしいという依頼があったんです。
中島 土井先生のみそ汁のレシピ、興味があります(笑)。すごく独創的なので。
土井 みそ汁なんて、好きにしたらいいんですよって言っても、今の人たちの多くがその好きにするってことができなくなってるんですね。だからレシピがほしい。誰かに言われた通り作る。そこには、まったく自分の感性を使ってない。感性を使わないと心が動かないから、おいしいね、きれいだね、と、感動さえしないですよ。
中島 たしかに、そうですね。『一汁一菜でよいという提案』が面白いのは、まずとにかく、うちにあるもので作ってみていい。それをいただいておいしいと思ったら、そのときにそれまで閉ざされていた感覚が目覚めるのかもしれないですよね。
土井 そうです、そうです。料理は心を動かす力があるんです。
中島 この本のなかでは、土井先生が実際に食べているみそ汁が紹介されているんですけれど、こうやってお話を聞いていると、みそ汁のなかにチーズを入れちゃうなんていうことに、全く違和感がなくなりました。
土井 ありがとうございます。日本料理とは何かと考えると、根本のところに「一汁一菜」というようなスタイルをきちんと持っていたら、あとはもう自由でいいんです。具だくさんのみそ汁はそれだけでおかずになるんですから。
中島 毎日のみそ汁の写真も自分で撮っていらして。特別ではなく、お家にある材料で作っている。この写真を出すのは勇気が必要だったそうですね。
土井 これまでの料理本の常識では、きれいに着飾った、体裁を整えた料理写真があたりまえ。日常の食事の写真を出すことはあり得なかったですからね。それこそ天才写真家の荒木経惟さんが自分の生活を赤裸々に撮った写真と匹敵するのではないか。そう私は思っています(笑)。

土井 リアリティですよね。読者がどう受け取るか、わからないでしょう。一汁一菜でよいという提案そのものを。でも、これまで何十年もいろいろなおかずを作ってきて、逆のことを言ってきた時期もあったなかで、もうそんなんやめといて、ご飯とみそ汁だけでええんだ、ということを言ってるわけだから。少しは、みなさんに届いてくれれば、うれしいですね。
日本人は自由になると力を発揮する
中島 それにしても、先生のお料理は自由ですね。この自由さは、業界や組織などのヒエラルキーと無縁に生きてきたからだと、以前におっしゃっていましたね。
土井 日本料理界とか、京料理界とかいうようなもののなかには、普通の会社と同じように、完全なヒエラルキーがあるわけなんです。
中島 そうですね。面倒だけど、仕方ないものだと、みんな思っているんじゃないかな。
土井 そのなかでやろうと思ったら、たとえば書家なら先生と同じ字を書く努力をしないと駄目でしょう。料理だって、その枠からはみ出ることはできません。何も自由になれない。だからこそ外にいるということがすごく重要なんです。日本のマンガ家やファッションデザイナーなどヒエラルキーのないところからは、すごい才能が出てきている。
中島 でも、私たちは、きちんと並んで行進して歩くような教育をずっと受けてきています。
土井 だからこそ日本人は自由になると、本当に力を発揮するんです。かつては私も老舗の懐石料理屋にいましたが、ひとつの世界をつきつめていくと、何かをしっかりつかんだことがわかる瞬間がある。そこではじめて、ああ、ここから出てもいいんだと背中を押されている自分に気がつくんです。
中島 さっきの「きれい」もそうですが、「自由」も先生のキーワードなんだなと思います。ただ、何でもありというなかで、右往左往するということではなくて、何か芯のところにわかっているものがあることによって、自由さも生きてくる。
土井 そうなんですよね。だからなんかね、すごいものとか素晴らしいものが、なぜ、そこにできるか。これは、なぜきれいなんだろう。いま、そういうことにすごく興味あるんです。おむすびひとつでも体裁を整えるのは技術ですが、おいしくするのは技術じゃないですから。
中島 技術だけじゃ、おいしくならない。なにが、お料理をおいしくするんですか?
土井 自分で作るんじゃなくて、おのずからそこにできてくるものなんです。自分はそれに対して、少し手を加えるっていう感覚ですね。自分できれいにしようとか、おいしくしようなんて、とんでもない。そう思うのが日本人なんですね。このことがわかるまでには、ちょっと時間かかりましたけれど。
中島 うーん。むつかしい。でも、それがわかったから、先生の料理はさらに自由に、楽しくなったのかもしれませんね。

中島 日本人が画一的だと言われている割には、日本の食卓は、かなり自由ですね。和洋中なんでもあり。
土井 自由なんですよ、本来はね。でも今の若い人を見ていると、スパゲティにみそ汁がついてきたら、それ違うだろと文句を言ったりするでしょう。そんなん、別にいいじゃないですか。
中島 それを「いい」としてきたところに、日本文化の活力もあったような気がします。
土井 この自由さを取り戻したら、料理ってそんなにむつかしくない。落とし卵と油揚げとキャベツを炒めたのに煮干しがそのまま入っているみそ汁を食べたときには、まるでカニが入ってるみたいだね、と。もう想像もしなかった味ができたりするから、面白い。
中島 毎日自由自在に違うものを入れて、一期一会的な感じもいいですよね。
土井 料理屋さんじゃないので、家庭料理には再現性がある必要がないんですよ。同じ形である必要もないしね。野菜の大きさが違うと、煮え加減が違うから同じ大きさに切って……そんなんかまわないんです。煮え加減が違うということは、少し固いものとすごく柔らかいものができるわけで、ひとつの食材でもいろんな変化があって、食べていて飽きないでしょう。
中島 先生の話を聞いていると、なんでも楽しくおいしそうに思えてきちゃう。失敗ってないのね、と。
土井 私たちの命を養うところを「一汁一菜」に任せておけば、あとはなんでもいいですもん。お料理する楽しみが増えるでしょう。これ作ったら、子どもたちが喜ぶかなって思う気持ちがたいせつ。それが純粋な料理の在り方だと思うんです。
中島 そうですね。本当にそうですね。
土井 晩ごはんだって、おかずは一品でいい。ハンバーグならそれだけ作ったらいいんです。付け合わせを何にしようと考えるから大変になる。お野菜は、みそ汁のなかに入れたらいい。
中島 そうすると、作るのがすごく簡単になりますね。
土井 旦那さんが急に友だち連れて帰ってきても、慌てる必要なんてない。ハンバーグを食べながら、ゆっくりワインでも飲んで、奥さんも一緒にわいわい楽しい話をすればいいんです。締めは、ご飯とみそ汁。料理を中心に幸せになれる要素はたくさんあると思うんです。
中島 料理に対する考え方を変えるだけで、なんだか未来が明るくなる気がします。
土井 お金をたくさん手に入れたい。地位を手に入れたい。そんなことじゃなくて、毎日〝おいしい〟を楽しむこと。悩まずお料理を楽しくやって食べたら、もうそれだけでいい。それだけで、みんな幸せになるんです。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
土井善晴(どい・よしはる)
1957年に家庭料理の第一人者として知られる料理研究家土井勝の次男として大阪に生まれる。大学卒業後にスイス、フランスでフランス料理を学び、帰国後は大阪「味吉兆」で日本料理を学ぶ。土井勝料理学校講師を経て1992年に「土井善晴おいしいもの研究所」を設立。NHK「きょうの料理」ほかテレビにも多く出演し、テレビ朝日系「おかずのクッキング」レギュラー講師としても知られる。元早稲田大学非常勤講師、学習院女子大学講師。著書に『おいしいもののまわり』『一汁一菜でよいという提案』ほか多数。
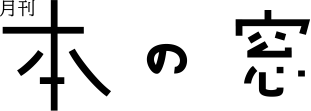
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2018/04/20)






