SM作家・美咲凌介による「SMを描いた純文学」10選
これまでは、西欧の文学作品を題材にしてSMの多様性を見てきました。翻って、わが日本文学には、どのような作品があるのでしょうか。
5 陰影に彩られたSとMの転換
『少年』 谷崎潤一郎
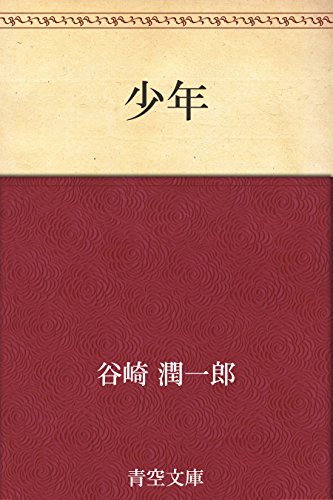
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J3F3YXC
「あれ仙吉、後生だから堪忍しておくれよう。譃じゃないんだってばさあ。」
光子は拝むような素振りをしたが、別段大声を揚げるでも逃げようとするでもなくなすがままに手を捻じられて身悶えしている。きゃしゃな腕の青白い肌が、頑丈な鉄のような指先にむずと掴まれて、二人の少年の血色の快い対照は、私の心を誘うようにするので、
「光ちゃん、白状しないと拷問にかけるよ」
こういって、私も片方を捻じ上げ、扱帯を解いて沼の側の樫の幹へ縛りつけ、
「さあこれでもか、これでもか」
と、二人は相変わらず抓ったり擽ぐったり、夢中になって折檻した。(『少年』 谷崎潤一郎)
語り手の「私」が、餓鬼大将の仙吉といっしょになって、光子という少女を「折檻」している場面です。光子は、「私」の友だちである信一の腹違いの姉です。信一は学校では意気地がなく大人しい子どもなのですが、家の中では暴君のように我儘で、「私」や仙吉を家来のように扱っています。
光子も初めのうちは勝ち気な様子だったのですが、あるとき「狐ごっこ」という遊びで狐の役をやらされたのをきっかけに、「かえっていじめられるのを喜ぶような素振り」さえ見せるようになっていきます。つまり、マゾヒスティックな振る舞いで、少年たちに媚びを売るようになったのです。
「私」と仙吉の折檻に降参した光子は、夜になったら、これまで入ることを許されなかった西洋館に二人を連れて行こう、と約束します。ところが、「私」はそこで、とんでもないものを見せつけられることになるのです。
「ほら仙吉はここにいるよ」
こういって、光子は蠟燭の下を指さした。見ると燭台だと思ったのは、仙吉が手足を縛られて両肌を脱ぎ、額へ蝋燭を載せて仰向いて坐っているのである。……略……
光子と私がその前に立ち止まると、仙吉は何と思ったか蠟で強張った顔の筋肉をもぐもぐと動かし、ようやく半眼を開いて怨めしそうにじっと私の方を睨んだ。そうして重苦しい切ない声で厳かに喋り出した。
「おい、お前もおれも不断あんまりお嬢様をいじめたものだから、今夜は仇を取られるんだよ。おれはもうすっかりお嬢様に降参してしまったんだよ。お前も早く詫ってしまわないと、非道い目に会わされる。……」(『少年』 谷崎潤一郎)
以前は自分が支配下に置いていた者から、今度は反対に自分が支配される。マゾヒストにとって最も興奮するのは、こうしたSとMの逆転が起きる瞬間なのかもしれません。
6 仮面としてのサディスト
『湖畔』 久生十蘭

https://www.amazon.co.jp/dp/4061984152
この夏、拠処ない事情があって、箱根蘆ノ湖畔三ツ石の別荘で貴様の母を手にかけ、即日、東京検事局に自訴して出た。
審理の結果、精神耗弱と鑑定、不論罪の判決で放免されたが、その後、一ヵ月も経たぬうちに、端無くもまた刑の適用を受けねばならぬことになった。これは普通に秩序罪と言われるもので、最悪の場合でも二年位の懲役ですむから、このたびも逸早く自首して刑の軽減を諮るのが至当であろうも、いまや自由に対する烈々たる執着があり、一日といえども囹圄の中で消日するに耐えられぬによッて、思い切って失踪することにした。(『湖畔』 久生十蘭)
久生十蘭の『湖畔』(1937年)は、このような謎めいた文章で始まります。語り手の「俺」は、華族の子として生まれ、海外留学を果たし、帰国後は文筆家として名を成しますが、心中では劣等感に苛まれています。そんな「俺」でしたが、別荘に滞在中に「陶」という名の美少女に一目ぼれし、妻に迎えることになるのでした。
俺は陶に溺愛し、ほんのちょっとの間も傍から離したくないほどに思っていたが、例の避けがたい猜疑心から、畢竟、この女も栄爵と権勢に憧憬れて嫁入ったのであろうという疑念を取り去ることが出来ず、さらに持前の卑屈な根性で、自分の愛情を露骨に示すことがなんとなく面映ゆく思われるもンだから、権柄に任せて粗暴放埓な振舞いをし、時には訳もなく手を挙げて打つようなところがあった。(『湖畔』 久生十蘭)
ここには、サド的な意味のサディストとは全く別の、新しいタイプのサディストが描かれています。「俺」のサディスティックな態度や行為は、彼の本心から出たものではありません。いわばサディストとしての顔は、自分の弱さを隠すための仮面にすぎないのです。
『湖畔』は推理小説なので、最終的な結末を具体的に説明するのはここでは慎みます。ただ、「俺」は物語の結末でついにサディストの仮面を脱ぐことになる、ということだけを述べておきます。
7 サディストのいないM小説
『家畜人ヤプー』 沼正三
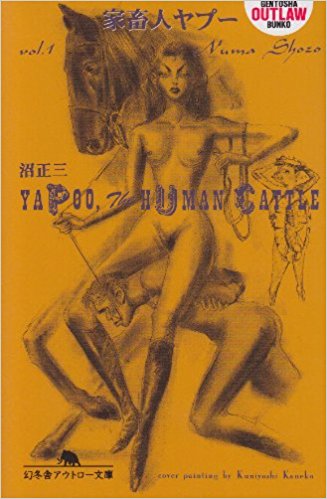
https://www.amazon.co.jp/dp/4877287817
吹き出したドリスが光幕の外へ河童を引きながら出て行く後ろ姿に、麟一郎は浴びせかけた。
「裸ダンサーめ!」
誇り高いイースの淑女として、こんな罵詈雑言がもし人間や半人間の口から出たら、唯おく彼女ではないが、今ドリスは少しも気を悪くしていなかった。九官鳥にバカと言われて怒る気になれないのと同じで、家畜のヤプーからいくら悪口や皮肉をいわれても、名誉感情は少しも傷つかず、全然怒る気になれないのだ。(『家畜人ヤプー』 沼正三)
日本人の瀬部麟一郎とドイツ人のクララ・フォン・コトヴィックは、婚約を交わした恋人同士です。あるとき二人は、未来人の乗る「航時遊歩艇」(一種のタイムマシン)の事故に巻き込まれ、未来世界に入り込みます。そこは白色人種のみが人間として認められる、差別に満ちた世界でした。黒色人種は「半人間」と見なされ、白色人種の奴隷とされています。そして、黄色人種の中で唯一生き残った日本人は、「ヤプー」と呼ばれ、家畜化されているのです。
『家畜人ヤプー』(1970年)の際立った特徴としてはまず、どこにもサディストが登場しない、ということが挙げられます。麟一郎や他のヤプーを調教・使役する白人種たちは、虐待や暴力によって快楽を得ているのではありません。ただ家畜や道具を使うように、ヤプーを使役しているだけです。
この奇怪な小説のもう一つの顕著な特徴は、徹頭徹尾人種差別的である点です。作者の沼正三は「あとがき」において、次のように語っています。
終戦の時、私は学徒兵として外地にいた。捕虜生活中、ある運命から白人女性に対して被虐的性感を抱くことを強制されるような境遇に置かれ、性的異常者として復員して来た。……略……
祖国が白人の軍隊に占領されているという事態が、そのまま捕虜時代の体験に短絡し、私は、白人による日本の屈辱という観念自体に昂奮を覚えるようになっていった。(『家畜人ヤプー』あとがき 沼正三)
「人種」とは「現実」であるというよりもむしろ「観念」である、とよく言われますが、この点でまさに『家畜人ヤプー』は「観念的」なマゾヒズム小説だと言えるでしょう。
(『家畜人ヤプー』は何度か版を変えて刊行され、その都度加筆や修正が施されています。ここでの引用は、昭和47年角川文庫版に基づいています。)
8 性風俗産業となったSM、その中で生きる女の子の純情
『トパーズ』 村上龍
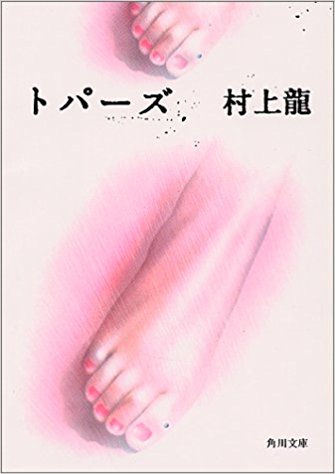
https://www.amazon.co.jp/dp/4041586038
その男が出てきたイタリア料理店の横に宝石店があってあたしは入っていって、ヒゲを生やしたスリーピースの店長が優しく微笑んでくれて何も言わないままあたしの指をじっと眺めて、これはトパーズが似合う指だ、と言った。
宝石屋に入ってからもあたしはずーっとその男のことを考えていて頭の中にはその男の顔や音楽や絵が詰まっていたので、トパーズと言われた時に、まるでその男があたしに話しかけてくれたような気がした。(『トパーズ』 村上龍)
『トパーズ』(1988年)は、性風俗産業に従事し、「SMセックス」の道具を持ち歩く若い女性を主人公にした短編です。引用部分中「その男」と呼ばれているのは、「作曲家で歌手で映画も作って時々は小説も書いたりしている」人物で、主人公の「あたし」は、その「芸術家」に一種の憧れめいたものを感じているようです。「トパーズと言われた時に、まるでその男があたしに話しかけてくれたような気がした」という表現からは、「あたし」のうぶで純な思いが伝わってきます。けれども、SMセックスの仕事の現場は苛酷で、彼女はそこでは「うぶで純」な存在ではいられません。
ヤマギシはあたしのおっぱいの先とあそこの肉をつまんでブルブル揺すって、あたしは痛くてオシッコを洩らしそうになったがまた叱られるのが恐かったので下を向いてすみませんすみませんと言いながら我慢した。
「だからお前はここと、ここだけで、ものを考えろ。わかったか? わかったら、ちゃんと挨拶して見ろ」(『トパーズ』 村上龍)
仕事のあと「あたし」は、トパーズの指輪を失くしたことに気づきます。どこかの謝恩会に出たらしい「あたしより若い女」たちから侮蔑の視線を向けられる、タクシーの運転手とけんかをする、バーで知り合った「青白い顔の男」から憧れの「芸術家」の声を留守番電話で聞かせてもらう……そんないくつかの小事件を経た後、トパーズはようやく「あたし」の手元に戻ってきます。
自分の部屋に帰って、まず青白い顔の男から貰った雑誌を出して、芸術家の写真を切り取り、壁に貼って、好きよ、と言いながらその小さな写真にキスをしたが、とても小さな人形に恋をしているようないい気分になって、高校時代の友だちに、声を聞いた、と、電話して、その後、あたしはトパーズの指輪を一時間近く、ずっと見つめていた。(『トパーズ』 村上龍)
「SMセックス」の場面の過激さが、性風俗産業の中で生きる一人の「女の子」の精神の清冽さを浮かび上がらせています。
9 SMの女王様が繰り広げる現代社会批判
『ひざまずいて足をお舐め』 山田詠美

https://www.amazon.co.jp/dp/4101036128
……略……あたしだって、最初、この世界に入った時は、あまりの男の醜態にげえっと来たもんね。だけど、数年やってりゃ職人と同じ。自分の技術だけが信じられるもんになってくるから、男が涎を流してすり寄って来ようが、目の前で大便をたれ流そうがどうってことない。私はプロフェッショナルなんだって、誇りすら持ち始めちまうもんなんだ。だから四つん這いになって私を見上げる男をいじらしいとすら思えて来るよ。そんな時、私は男の頼りないおちんちんをハイヒールの踵で思いきり踏みつけて苦痛に歪む男の顔を楽しみながら煙草をふかして平然としたまま言い切ることが出来るよ。ひざまずいて足をお舐めって、ね。(『ひざまずいて足をお舐め』 山田詠美)
『ひざまずいて足をお舐め』(1988年)には、語り手の「私」と、その妹分である「ちか」という二人の「SMの女王様」を中心に、周囲の男女のさまざまな人生の断面が描かれています。この作品は、山田詠美の「自伝的作品」と評されることも多いようですが、むろん一般の自伝とは異なります。それは、「私」も「ちか」も二人とも、ある意味で作者の分身と見ることができるからです。語る自己も語られる自己もここでは二重構造になっていて、時に共感し合い、時に反発し合うのです。
この作品のもう一つの特徴は、全体が一種の社会批判になっている、ということにあります。社会が「まっとう」と見なしている価値観に、「私」や「ちか」は「SMの女王様」という立場から、鋭く切り込んでいきます。
……略……たとえば、あのSMクラブ。そりゃあ、俗に言う変態のためのクラブだけど、さ。そういう人たちがあれ程、いるって事実を受け止めなきゃ。私たちって、必要とされてんだよね。その必要とされてるってことは、悪くないことだよ。それも、お金だとか地位だとか、そう言った外側のもので必要とされるんじゃなくてさ、そんなものを皆、とり払った部分で必要とされてるんだからね。私は、この仕事、悪くないと思う。(『ひざまずいて足をお舐め』 山田詠美)
こうした箇所は、ほかにも幾つも見つけられます。社会の良識と思われているものに対する反発と批判という点で、『ひざまずいて足をお舐め』は、サドの『新ジュスチーヌ』に一脈通じるところがあります。
10 SとMの美しい調和と、その破局
『ホテル・アイリス』 小川洋子
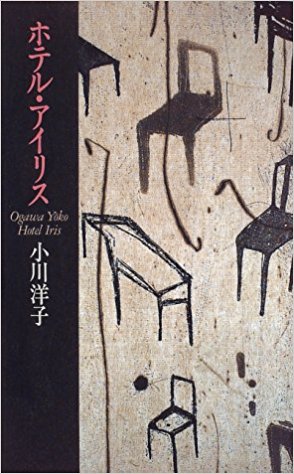
https://www.amazon.co.jp/dp/4054007740
「気持ちいいんだろ?」
男は四本の指を一気に口の中へ押し込んできた。わたしはむせて嘔吐しそうになった。
「さあ、どんな味がする?」
わたしは舌でそれを押し出そうとした。唾液が唇の端を伝って流れた。
「よだれが出るほどいいのか?」
わたしは懸命にうなずいた。
「淫乱」
男はもう一度叩いた。
「はい、いい気持ちです。お願いですから、もっとやって下さい。どうかお願いします」(『ホテル・アイリス』 小川洋子)
小川洋子は『ホテル・アイリス』(1996)で、サディスティックな欲望とマゾヒスティックな欲望との幸運な、そして危うい調和を、端正な文体で描きました。高校を中退し、母の経営する安ホテル、ホテル・アイリスを手伝っている十七歳の「わたし」は、ロシア語の翻訳家と称する初老の「男」と、性的な関係を結ぶようになります。「男」は、性行為のときだけ、ひどくサディスティックに振る舞います。そして、「わたし」もその「男」の行為に応え、マゾヒスティックな欲望を感じるようになっていくのです。
彼に触れているのは、唇だけだった。彼は背広姿でベッドに腰掛け、わたしは丸裸で四つばいだった。なのにしっかり抱き合っているような気持になれた。
わたしは足の隅々を愛撫した。彼が褒めてくれたとおり、わたしの唇はお利口によく働いた。(『ホテル・アイリス』 小川洋子)
しかし、この美しい調和は次第に危うさを増し、ついには思いがけない形で破局に向かいます。それは、物語というものに内在するある種の法則がもたらす、一つの必然なのでしょうか。それともSM関係というものが持っている、避けられない定めなのでしょうか。
番外編 重層的で変容し続けるSM関係
『剥奪遊戯』(仮題) 美咲凌介
「背が高いわね、亜樹」
真里奈の声がした。
「うらやましいわ。わたしも、もう少し背があったらいいのに。あなたを見ると、いつもそう思うの。考えてみれば、わたし、いつもあなたを見上げていたわね。そう……中学生のころから、ずっとそうだった。ねえ、亜樹。最初に口をきいたの、おぼえてる? 確か、中学二年のときだったわ」
「はい」
「あなた、すごく大きく見えた。でも、とてもかわいかったわ。わたし、何て素敵な人だろうって……そう思った。それからずっと、わたし、あなたの言いなりだったわ。あなたの言いなりに、あなたにキスされたし、あなたの言いなりに、この家の……あなたの奴隷にもなった。わたし、あなたが好きで好きで、仕方がなかったの。あなたの言うことなら、本当になんでもしてきたわ」
真里奈は、そこで言葉を切った。大きな二つの、まるい目を閉じる。小百合は、その真里奈の顔を、何かを思い出しているような表情だと感じた。真里奈は、亜樹と自分のこれまでの関係を反芻しているのかもしれなかった。それは、ひどく大人びた表情だった。
……略……
真里奈は目を開いた。
「でも、これからは違うわね。わたしがあなたを見上げるんじゃなくて、あなたがわたしを見上げるのよ。そうじゃない?」
「はい」
「どうするの」
「はい。亜樹は、真里奈様の前に、ひざまずきます」
亜樹はそう言うと、脚を折り、実際にひざまずいてみせた。
「それから?」
真里奈は、続けて言った。
「それから、どうするの」
「這いつくばります」
亜樹は再び、四つんばいになった。(『剥奪遊戯』(仮題) 美咲凌介)
これは今、わたし、美咲凌介が発表のあてもなく書いている――というよりは書き直している小説の一部です。
この小説でわたしの意図しているのは、SとMが絶えず変容しながら、それでも調和を保ち続ける世界の構築です。この小説の中では、絶対的な嗜虐者も、絶対的な被虐者も存在しません。全ては移りゆきながら、それでも一つの小宇宙を維持するのです。
この小説がいつの日にか、読者の皆さんの目に触れることを祈りながら、この稿を終えることにします。
プロフィール
美咲凌介(みさきりょうすけ)
1961年生まれ。福岡大学人文学部文化学科卒業。在学中、文芸部に所属し、小説や寓話の執筆を始める。1998年に「第四回フランス書院文庫新人賞」受賞。SMを題材とした代表作に『美少女とM奴隷女教師』『Sの放課後・Mの教室』(フランス書院)など。他に別名義で教育関連書、エッセイ集、寓話集など著書多数。
「SM小説家美咲凌介の名著・名作ねじれ読み」連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2018/04/19)
- 1
- 2



