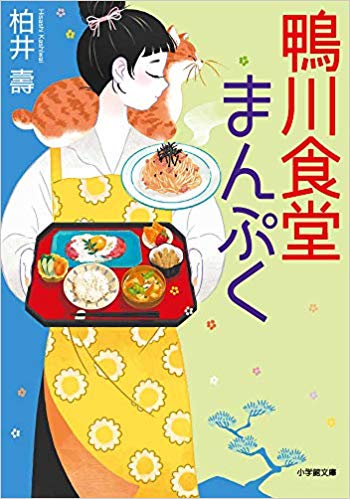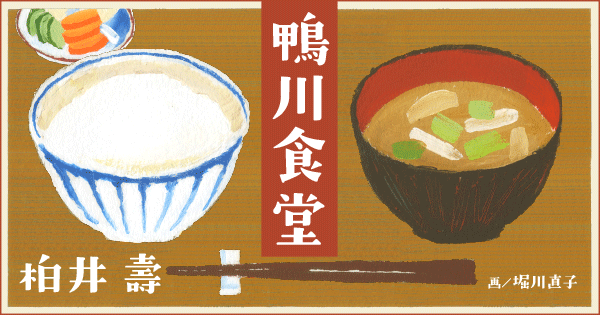「鴨川食堂」第38話 チキンライス 柏井 壽

つかれた体に、ほっと一息。どうぞ召し上がれ。
第38話 チキンライス
「ぜんぶが高いわけじゃなくて、そういう接待用の高いお店もあちこちにあるみたいです」
「ますます安心しはったでしょう」
「ええ。でも、それだけじゃないんです。帰り際に銀行の封筒を渡されて、中身を見てみると、帯封の付いた百万円の札束でした。これは? って訊いたら、少しでも早く返そうと思って、と彼が言いました。ご両親に迷惑を掛けているから、とも言ってくれました」
「えらい人ですやんか。いったん借りたらなかなか返せへんもんやのに」
「誰でもそう思いますよね。やっぱり彼は誠実な人だったんだ。そう確信したら、無性にあのおばちゃんに腹が立ってきて。きっと自分が不幸な人生を歩んできたから、やっかんでたんだ。わたしが彼としあわせになるのをねたんでいたんだ。そう思うようになりました」
「傍(はた)からみたら、それはちょっと言い過ぎなような気もしますけど、当の本人はそう思うかもしれませんね」
「わたしって思いこみの強い性質(たち)なので、そう決めつけて実行に移しました」
香織の目が鋭く光った。
「実行て? まさか殴り込みをかけたとか?」
「まだそのほうがよかったのでしょうね。わたしはもっと陰湿な、ひきょうな手段を使ってしまったんです」
「いやがらせ?」
「はい。口コミのグルメサイトに最悪のレビューを投稿したんです。店は不潔だし料理はまずいし、店の主人がおしゃべり好きで、落ち着いて食べられなかった、と」
「ほんまにそんなひどい投稿しはったんですか?」
こいしが顔をゆがめると、香織は両肩をちぢめて頭を下げた。
「後から思えば、本当にひどい投稿をしたと思います。でもそのときは、おばちゃんが悪いんだから、これぐらいのことは当然だと思っていましたし、ぎゃふんと言わせたかった」
「気持ちは分からんことないけど、やったらあかんことやったと思います。もしうちの店がそんなんされたら、と思うただけで胸が痛みますわ。お父ちゃんは気にもしはらへんやろけど」
「ずっともやもやしていて、夜の眠りも浅くなってしまって、一週間後にようやく決心して投稿を削除したんです。そしてその日の夜でした。彼からメールが来て、海外に出て勝負するから三か月ほど会えなくなるけど、心配しないでくれ、と。うまくいけば二倍にして返すのは三か月後になるかもしれない、とも書いてあったので、本当に良かったなと思ったんです」
香織の表情が曇っているのは、その後の展開が晴れやかなものでなかったことを表しているのだろう。
「そこまでは順風満帆ていうことやったんですね」
「寂しいけどがんばってね、と返事をしたのですが、彼からは何も返ってきませんでした。そしてそれを最後に連絡が途絶えてしまって、今に至る、です。長々とくだらない話をお聞かせしてすみませんでした」
香織は吹っ切れたような顔をこいしに向けた。
予想された結末ではあったが、香織への同情以上に、相手の男性への怒りがふつふつと湧き上がってきた。
「要するに九百万円だまし取られたていうことですやん。当然警察に被害届を出さはったんでしょ?」
「わたしは躊躇(ちゅうちょ)していたのですが、両親がすぐ警察に被害届を出しました」
「で、どうなったんです? お金は返ってきたんですか?」
こいしがペンを置いて身を乗りだすと、香織はゆっくりと首を横に振って、深いため息をついた。
「警察の人の話では、彼はプロの結婚詐欺師だということでした。彼が住んでいたマンションも偽名で借りたウィークリーマンションでしたし、メールのフリーアドレスからも身元を特定できないようになっていて、計画的な犯行だろうと言われました。彼からもらった名刺に書かれていた会社も、もちろん架空のものでした」
「香織さんに狙いを定めた犯行やったんですか。気の毒に」
「簡単に人を信じてしまったわたしが悪いんです。よくよく考えればお金持ちでイケメンの男性が、わたしに近寄ってくるわけないんですよね。そんなお金持ちだったら、わたしから借りなくても、もっとほかに融資してくれるところがあるはずだ、ってあとから冷静に考えればすぐ分かることなのに」
香織が悔しそうに唇を嚙んだ。
「ひょっとしたら、困ってはったおじいさんにお金をあげはったのも、仕組まれたお芝居やったかもしれませんね」
「警察の人にもそう言われました。信用させるための典型的な手口だって」
「ニュースでもよう聞く話やし、香織さんのお話聞いてても、なんでそこで気が付かへんのやろて思うことがいくつかありますけど、もしも自分がその立場に立ったら絶対だまされへん、てよう言い切れませんわ。自信ない」
こいしは偽らざる気持ちをそのまま口にした。
写真で見る限り、どこからどう見ても人をだますようなタイプには見えない。イケメンとは言っても、自信満々という感じではなく、どことなく頼りなげで、母性本能をくすぐられる男性だ。どことなく浩(ひろ)さんにも似ていることもあって、香織の恋人だった男性が、プロの結婚詐欺師だと聞かされても、まだこいしは半信半疑だ。
「それから三年、五年と経っても、まだわたしは、ひょっこり彼が戻ってくるんじゃないかと甘い夢を見ていました。でも七年経って詐欺罪は時効になったと警察のかたから聞かされて、やっと目が覚めたようなおろかなわたしです」
「お話はよう分かりました。辛いことやろうに、ようお話ししてくれはりました。けど、なんで今になってそのときのチキンライスを捜してはるんです?」
こいしが訊いた。
「両親には本当に申しわけないことをしたと思って、せめてだまし取られたお金を両親に返そうと必死で貯金をしてきました。十五年掛かりましたけど、なんとか九百万円貯めることができたので、両親が元気なうちに返そうと思っています。そして二度と恋はしないでおこうと決めていたのですが、先月になって恋人ができたんです」
「おめでとうございます。九百万円も貯めるてすごいですやんか。なかなかできひんことやわ」
「ありがとうございます。なんとしても親に恩返ししないとと思って、歯を食いしばってきましたが、どうにかこうにか親不孝なまま終わらずに済みそうです。十五年は長かったですが、すべては身から出たさび。二度と失敗を繰り返さないようにしなければと思ったときに、どうしてもあのときのチキンライスをもう一度食べたくなって。本当はおばちゃんに会って謝りたいんですが」
よくあることだ。
食を捜してほしいという依頼の本音が、人捜しにあるのは当然と言えば当然のことなのだ。
もう一度食べたい食、すなわちそれを作ってくれた人、あるいは一緒に食べた人ともう一度会いたい。そう願わない人なんかいない。
「おばちゃんの名前なんか覚えてはりませんよね」
「覚えていないどころか、聞いてもいなかったので知らないんです」
「そらそやわね。名前聞く必要がないもん。なんかそのおばちゃんに結び付くヒントがあったらええんやけど」
こいしが腕組みをして白紙のページに目を落とした。
「ヒントになるかどうか分かりませんけど、おばちゃんの口癖っていうか、しょっちゅうつぶやいていた言葉は、今もはっきり覚えています」
「どんな?」
前のめりになって、こいしがペンをかまえた。
「──腹の黒いのはなおりゃせぬ──。テレビのニュースやワイドショーを見ていて、おばちゃんはいつもそうつぶやいてました」
「どうかなぁ。ヒントになるような、ならへんような」
こいしが首をかしげた。
「おばちゃんのことで印象に残っているのは、それぐらいしかなくて」
香織が声を落とした。
「分かりました。お父ちゃんにがんばって捜してもらいます」
こいしがノートを閉じると、香織は立ち上がって一礼した。
ドアを開けた瞬間、美味しそうな匂いが廊下の向こうから漂ってきた。
「さあ、お父ちゃんはどんな料理を作って待ってはるやろ。愉しみにしててくださいね」
自然と早足になるこいしのあとを香織が追いかけた。
「あと先になってすんまへんでしたな。お腹空きましたやろ」
待ちきれないように、食堂との境に掛かる暖簾から鴨川流(ながれ)が顔を覗かせた。
「いえ、こっちこそ勝手を言って申しわけありませんでした。市橋香織と言います。どうぞよろしくお願いいたします」
立ちどまって、香織が深く腰を折った。
「すぐにご用意しまっさかい、ちょっとだけ待っとぉくれやっしゃ」
茶色い作務衣(さむえ)を着て、白い和帽子をかぶった流は小走りで厨房に戻っていった。
「このお出汁の匂いからすると、和食がメインみたいやな。お酒はどうしはります? よかったら日本酒をお出ししますけど」
「お酒はあまり強くありませんが、せっかくなので少しだけいただきます」
「こんな店やけどゆっくりしていってください」
こいしがパイプ椅子を奨めて、厨房に入っていった。
あらためて店のなかを見まわすと、どこか〈南海飯店〉に似ている。ビニールシートを貼ったパイプ椅子も、神棚のよこに置かれたテレビもおなじ。きれいな店とはいいがたいが、掃除は行き届いていて清潔感がある。
「ぼちぼち寒ぅなってきましたさかいに、あったかいもんを多めにしました」
大きな丸盆に載せて流が運んできた料理からは湯気が上がっている。
「なんだかすごいご馳走ですね。こんなの見たことありません」
「かんたんに料理の説明をさせてもらいます。この小さいふた付き土鍋に入っとるのは牛スジと聖護院蕪(しょうごいんかぶら)の煮込み、七味を振って食べてください。これは寒ブリの照り焼き、刻んだ大葉と一緒に召しあがってください。こっちがカニ脚の天ぷら、ショウガ塩で食べてもろたら美味しおす」
香織の前にひとつずつ並べながら、流が料理に説明を加える。そのたびに香織はうなずいている。
「この長皿に載ってるのは、左から焼鯖の小袖寿司、ウズラのつくね串、鰻巻(うま)き、フグの白子焼、蒸し豚の黒ゴマ和え、金時ニンジンとチーズのフライです。どれも味が付いてますさかい、そのまま食べてもろたらよろしおす。こっちの白磁の丸皿はグジの細造りと、中トロの平造りを盛り合わせてます。グジのほうは、もみじおろしをようけ混ぜてポン酢で、中トロはわさびを山盛り載せて、ウニ醬油で召し上がってください。お揚げさんの焼いたんは、大根おろしをようけ載せて、ちょこっと醬油をかけてもろたら美味しおす。あとでご飯とおつゆをお持ちしますさかい、ゆっくり食べてください」
丸盆を小脇にはさんで、流が厨房に戻ると、入れ替わりにこいしが出てきて、日本酒の四合瓶と小ぶりのグラスをテーブルに置いた。
「埼玉のお生まれやと聞いたんで、こんなんをご用意しました。『鏡山(かがみやま)』の純米酒です。ちょっと甘みがあって、けど香りが抑えてありますんで、飲み飽きしません。うちが今一番気に入ってるお酒です。お好きなだけグラスに注いで飲んでください」
「こんなの一本飲めませんよ」
「無理に飲んでもらわんでもええんですよ。一杯でも二杯でも。お好きなように」
言いおいて、こいしも厨房に入っていき、香織ひとりが食堂に残った。
何から箸を付ければいいのか迷ってしまう。香織はそうひとりごちた。
『鏡山』の酒瓶を両手で持って、静かにグラスに注ぐ。コクッコクッと音が鳴り、グラスからふわりと酒の香りが浮かび上がる。なめるようにひと口飲んでから、香織が最初に箸を付けたのはグジの細造りだった。
白身の魚なのだろうけど、赤みを帯びたピンク色をしていて、口に入れるとねっとりと舌にまとわりつく。もみじおろしの辛みとポン酢の酸味がからんで複雑な味わいを口のなかに広げる。
カニの脚の身だけを揚げた天ぷらはショウガ塩という聞きなれない塩を付けて食べる。カニは何度も食べてきたが、これまで感じたことのない風味だ。それは金時ニンジンのフライもおなじで、ニンジンなんて数えきれないほど食べてきたが、フライにして食べるのは初めてのこと。ましてやチーズと一緒に味わうなど考えたこともなかったが、なんの抵抗もなく喉を通っていく。
牛スジの煮込みが、どこか中華っぽい味がするのは、香辛料のせいなのだろうか。白ご飯といっしょに食べたいような気がする。
グラスの酒を飲みほした香織は、遠慮がちに二杯目を手酌した。
「どないです。お口に合うてますかいな」
流は大ぶりの土瓶と湯吞をテーブルの端に置いた。
「こんな美味しい料理をいただけるとは夢にも思っていませんでした。どれを食べても本当に美味しいです」
香織が晴れやかな笑顔で応えた。
「よろしおした。こいしからちらっと聞いたんやが、チキンライスを捜してはるそうですな」
流はほうじ茶を土瓶から湯吞に注いだ。
「はい。東京の中華屋さんでいただいたチキンライスなんです」
串に刺したウズラのつくねを食べながら香織が答えた。
「さいぜん、こいしが聞きそびれたみたいなんやが、その〈南海飯店〉のおばちゃんを捜しあてることができたら、あなたのことを話してもよろしいか? チキンライスをもういっぺん食べたいと思うてはることを」
「はい。もちろんです」
香織は躊躇なく即答した。
「こいしからざっと聞いたとこでは、どうやらそのおばちゃんのオリジナルメニューみたいですさかい、直接聞かんことには分からんように思いますんや。もしお会いしても最低限のことしか言いまへんさかい安心してください」
「今日お話ししたことをありのまま伝えていただいても大丈夫です。そうでないと、なぜわたしが今になってもう一度食べたいと思ったのか、お分かりにならないでしょうから」
「基本的にうちの探偵事務所は人捜しはしまへんのやけど、今回は特例ということで、まずはそのおばちゃん捜しからはじめることにしますわ」
「どうぞよろしくお願いいたします」
慌てて吞みこんだ香織は、むせながら中腰になって一礼した。
「お父ちゃん、食べてはる最中に余計な話したらあかんやん。ゆっくり食べてもらえへんでしょう」
「そやったな。えらい無粋なことしてすんまへんでした。つい気が急いてしもうたもんやさかい」
和帽子をとって、流が頭をかいている。