連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:はらだ有彩
昔話の中にいるたくさんのエキセントリックな女の子たちの姿を現代にも重ね合わせながら描いた『日本のヤバい女の子』(柏書房)。現代社会にも通じる、差別意識に抵抗する女性の姿を著者のはらだ有彩さんに伺いました。
連載対談 中島京子の「扉をあけたら」
第二十九回
いにしえの「ヤバい」女の子に現代を学ぶ。
ゲスト はらだ有彩
(テキストレーター)
Photograph:Hisaaki Mihara

はらだ有彩(左)、中島京子(右)
きっかけは、セクハラだった
中島 はじめまして。『日本のヤバい女の子』は、はらださんにとってのデビュー作なんですね。これまで読んだことのないようなユニークな視点の本で、しかも文章だけじゃなく、まんがやイラストまで手がけられている。マルチな才能の方が現れたなと驚いて、ぜひお会いしたいと思っていたんです。
はらだ ありがとうございます。私、会社員なんですけれど、会社に黙ってこっそり書いていたものが、本になってしまいました(笑)。テキスタイルとテキストとイラストレーションを混ぜたダジャレで、テキストレーターという肩書きを勝手に名乗っています。
中島 会社に内緒で作家をやっているなんて。大丈夫ですか、顔出ししちゃっても。おかめのお面でもかぶってもらったほうがいいのかしら(笑)。
はらだ 全然ばれていないんです(笑)。
中島 もともとインターネットで連載していたものを編集者の方に見出されたのだと伺いました。
はらだ はい。有志の方が無償でやっていらっしゃるサイトに自由に書いていいよと言われて、何の気なしに始めたのがきっかけです。
中島 そもそも、どうして昔話の中の「ヤバい」女の子の話を書こうと思ったんですか。
はらだ たぶん、私の家庭環境にも遠因があると思うんです。母は、ゴリゴリのフェミニストなんです。テレビで女性が洗濯をする洗剤のCMをやっていると、必ず母がキレるんです。弟や父がうっかり女性蔑視的な失言をすると、彼らはこんこんと母に詰められる。
中島 男性にとっては厳しい家庭ですね(笑)。
はらだ しかも中高は女子高で、大学は美大だったので、女性ならではのイヤな目に遭う機会がほとんどなく育ったんですね。ところが、社会人になって初めて、セクハラを受けて……。
中島 大ショックだったでしょう。
はらだ それまで信頼していた取引先の人に、ある日突然「ホテルに行こうよ」と言われたんです。こんなのんきなことを言っていたら怒られるかもしれないのですが、「おおっ! これがセクハラというやつだ。セクハラってまんがの中の話じゃないんだ」と、驚きました。ところが周囲を見渡すとセクハラまがいのことが、日常茶飯事のように行われている。二十一世紀の現代ですら、女性はこんなに生きづらい。昔はもっとひどかったんじゃないかと思いさかのぼって昔話を調べ始めたら、いろんな女性がいるわ、いるわで。これはもう書くしかないなと思いました。

はらだ そうですね(笑)。タイトルにつけた「ヤバい」にもいろんな意味があります。ひどい目に遭って「ヤバい」人もいれば、好き勝手やり返して「ヤバい」人もいる。いろんな「ヤバい」パターンがあるんですね。
中島 『堤中納言物語』の「虫愛づる姫君」の話を取り上げているでしょう。このお話は私も現代語訳を手がけたことがあって、彼女にはとても親しみを持ってるんです。
はらだ 私のほうは自己流の解釈なので、ちょっと恥ずかしいです。
中島 小学校のときにミカちゃんという友だちがいたのですが、彼女は虫が大好きでいつも『ファーブル昆虫記』を読んでいた。訳しているうちに、虫愛づる姫君がミカちゃんの姿となって立ち現れてきたんです。人間一人一人嗜好も違うのが当たり前。そんなに変わったお姫様とは思えなくなってきたんですよ。ああ、こういう人、いるわって。
はらだ 現代社会では、それが役割分担みたいになっちゃって、虫担当だと思われると、虫のことには何も動じませんみたいなキャラでいかないといけなくなるじゃないですか。例えば、蛇に驚いたら爬虫類好きを名乗れないのか。脱毛したらもうフェミニストを名乗れないのか。
中島 「この人はこういう人」とレッテル貼りして、はみだしを禁止する! みたいな。
はらだ 虫愛づる姫君に関しては、破綻を指摘する声も多くあるんです。成虫じゃなくて、毛虫だけを愛でるのは成長したくない気持ちの表れだとか、蛇が出てくると驚くところに矛盾があるとか、いろんな考察がされている。もちろん歴史的な資料に基づいたちゃんとしたものなのですが、彼女の単なる嗜好をそんなふうに考察されるのはめちゃくちゃ悲しいなと思いました。
中島 そりゃそうですよね。彼女はただ毛虫が好きだっただけ。アカデミックに研究している先生方には申し訳ないけど、重箱の隅をつつくような指摘ですね、それ。文学研究ってものにはしばしばそういう悲しさがあって、「どうしてそこをつつくかな」という気にさせられるところはあります。
おかめは、なぜ自死を選んだのか
はらだ 中島さんは、どの女性にいちばん興味を持たれましたか。
中島 みんなそれぞれにインパクトがあって、いろいろと考えさせられましたが、読後に消化しきれない不思議な感情が残ったのが、最初に登場する「おかめ」の民話です。ひょっとこと対になったお面でおかめという名前は知っていたけれど、そもそもおかめさんが昔話の登場人物だということは知りませんでした。
はらだ ベテランの大工である長井飛騨守高次が大報恩寺の本堂の工事を任された。ところが、柱の寸法を間違えて短く切ってしまったんですね。妻であるおかめの機転によって危機一髪の状況を脱することができるのですが、その結果おかめは自死を選びます。それが、すごくショックでした。
中島 女である自分が助言したことがバレると、夫の名誉に傷がつくと考えたんですね。私もおかめが死を選んだことには違和感を持ちましたが、一方でおかめの気持ちがどこかわかるような気がしなくもなかったんですね。確かに内助の功ではあるけれど、このまま自分と一緒にいたら夫は息苦しくなる。その後の二人の関係はあまりよくなくなるんじゃないか。
はらだ そうなんです。現実でも、起こりそうな話ですよね。
中島 酉の市に行けば、おかめは熊手の中で笑っているでしょう。そこには、福を呼ぶ女性の原型があるものだと思っていたから、さあっと血の気の引くような怖さを感じました。
はらだ 関西では、お好み焼きといえば、「オタフクソース」なんですね。おかめのことを調べてから、私はお好み焼きを食べるたびにオタフクソースを見てすごく暗い気持ちになるんです。
中島 実際に舞台となったお寺も見に行かれたそうですね。

中島 ほんの一寸、二寸の失敗じゃなかったんだ。
はらだ その柱の前に立って、もし自分が大工でこれだけの寸法を切り間違えたと想像したら、脂汗が出てきちゃって。確かに死んで詫びるしかないほどの致命的なミスだなと。それをもし自分のパートナーが助けてくれたら、感謝することはあれ非難することはない。本にも書きましたが、おかめが夫と一緒に建築家として成功するという結末がなかったのがほんとうに残念。
中島 今となってはその本心はわからないけれど、高次だっておかめに死んでほしくはなかったと思います。
はらだ 大報恩寺には、おかめの人形が奉納されている部屋があるのですが、その中にはおかめが男根を模したものを持っている人形がたくさんあるんです。全体の十分の一ぐらいは男根バージョンでした。
中島 おかめと男根? それは、どう解釈すればいいんでしょうね。
はらだ きっと、おかめの顔のふくよかなフォルムから夫婦の営みを連想したのではないかと思います。
中島 それは、おかめの顔も男性器の一部っていうイメージですか。
はらだ それを見て、動揺しました。連想するのはわかるのですが、それをカタチにしてしまうのは、どうかと。人が一人、死んでるんだけどなと思うと、複雑な気持ちになってしまいます。昔々のキャラクターとして見たら面白いかもしれないけど、もし高次やおかめが自分の友だちだったらと考えると……。
中島 それは嫌ですね。友だちもだけど、自分の顔がそうなっていることを考えると、ちょっと耐え難いものがありますね。
はらだ もちろん悪意があって作ったわけじゃなくて、内助の功の物語を夫婦円満や子宝につなげて、純粋な気持ちで奉納しているのでしょうが。
蛇になるか、石になるか
中島 巻末についているまんがは、お友だちと一緒に「清姫」の舞台となった道成寺(和歌山県)を訪れたときのことを描かれていましたね。
はらだ 実は、いちばん最初に書いたのが清姫の話だったんです。
中島 なるほど。はらださんにとって、清姫は作家になるきっかけとなったテーマだったんですね。清姫は、安珍という旅の僧に恋するのだけれど、騙されてふられてしまい、怒り狂って蛇になってしまいます。
はらだ 伝承の中で清姫は、自分の思いを抑えきれずやらかしちゃった女性のように語られてきたと思うんです。でも私は、めっちゃ便利じゃんと思ったんですね。蛇は、強いし、速いし、かっこいい。だから蛇になるのは、あながち悪いことじゃないかもしれない。だって蛇にならなかったら、ただ男に捨てられて、この先の人生をつらいまま生きていかなければならない。それが幸せかというと、別に幸せじゃない。怒り狂って安珍を追いかけていって殺してしまうのは良くないけれど、その後、蛇として楽しく暮らしましたとさ、となっていればよかったのに。
中島 安珍を殺した後、蛇になった清姫はどうなるんですか。
はらだ 海に身を投げたという説や山に向かっていったっていう説、安珍と一緒に炎に包まれて焼けてしまったという説もあるらしいんです。いずれにしても、清姫は死んでしまう。清姫が蛇になることは、実はなにかの働きかけなのではないかと思うんです。今どき言わないかもしれないですが、女の人は男の後を三歩下がってついていくものだというように、受動的なものとして扱われることが多いでしょう。

はらだ そうなんです。ヤバい女の子のお話を通して日本文化の中に脈々と流れるステレオタイプな女性像を転換していけたらなと思っています。
中島 もう亡くなったのですが、私には、大正生まれのおばがいました。夫は明治生まれで、お酒が大好き。大声で怒鳴るし、若い頃は浮気もちょっと(笑)。従姉たちはよく「昔は怒るとゲンコツが出た」って言ってました。でも、私が知る限りでは、とても仲のいい夫婦だったんです。私が二十歳くらいのときに三歳年上の姉と一緒に呼ばれて、おばが「あんたたちもこれから嫁に行く年齢になる。だから私は話しておきたいことがある」と語り始めたんです。
「結婚して何年も、自分はずっと夫の横暴を我慢していた。でも、もう耐えられないと思い、怒りをあらわに反撃に出た。そうしたら、意外と簡単に夫が折れた。それから夫婦の関係が変わった。だからあなたたちは、嫁に行ったら我慢するな」と。
はらだ 示唆に富みまくった話ですね。
中島 明治生まれという世代のせいもあったのでしょう。女房に対しては、横暴だった。でも、おばが自己主張したら、受け入れたわけですね。はらださんの話を聞いていたら、おばは清姫じゃないけれど、蛇になったんだなと思った。
もちろん殺しちゃまずいけれど、でも人間やっぱり蛇や鬼になる瞬間みたいなものがある。そして相手も自分の知ってるおとなしいだけの女性ではないんだと気付く。人間関係において、そういうことがすごく重要なんじゃないかと思いました。
はらだ 同感です! だから私は、普段からなるべくすぐ蛇になるようにしています(笑)。
中島 フェミニストのお母さまみたいに。
はらだ はい。ちょっと母の影響も受けて(笑)。私が勤務している会社は、田舎にあって駅からも遠いんですね。その道を歩いて通勤していたら、私の横に車が止まって、おじいさんが卑猥な言葉を投げかけてきたんです。
中島 気持ち悪い! まあ、普通だったら、そそくさ逃げると思いますが、はらださん、違った?

するとそのおじいさんは、ビビって逃げるように車を走らせたんです。ところがその先に赤信号があって、止まっちゃった。もちろん、追いかけていってもう一回キレました(笑)。
中島 学びましたよ、きっと彼は。おじいさんになるまで蛇を見たことがなかったんですね。
はらだ もうしないですよね。彼にとっても社会にとっても、いい事したなと思って。
中島 だからやっぱり、蛇になる瞬間をちゃんと見せるということも大事だなっていうふうに思いますよね。
はらだ 必ずしもキレなくてもいいのですが、なにかアクションができたらいいですよね。
中島 ほんとう。言動で示さないと、伝わらないものは多いですから。
はらだ 女性に対してだけじゃなく、他人に対してそういういびつな感情を持っている人に、何か働きかけることができたらいいなと思っているんです。この本には載っていないのですが、佐賀県の民話で「松浦佐用姫」というお話があるんです。佐用姫には好きになった人がいた。想いを寄せた人がどうしても逆らえない事情で出征することになった。彼はきっと死んでしまうのだと悲しみ、佐用姫は七日七晩泣き続けて石になってしまうんです。
中島 恋人が自分から離れて戦争に行っちゃうから、石になる。
はらだ 一見、すごく消極的な選択なのかなと思えるのですが、石って永遠に残るでしょう。だから悲しみを込めたままずっとここに存在し続けてやるという意思表示にもとらえられる。
中島 清姫が動なら、佐用姫は静。いずれにしても、そこには強い意思があります。
はらだ 調べれば調べるほど、まだまだ感情の表明の仕方はいろいろあるのかもしれないなと思っているところです。
中島 面白いですね。民話や伝承の中にこれだけの話が隠れている。きっと、長い歴史の中で、女の人たちは怒りや悲しみ、不当なことに対する反論みたいなものを、蛇になったり、石になったり、いろんなかたちで表明してきたのかもしれませんね。この本を読んで、みんなが「私はこの話のこの女だ」というようなことを言い始めたら、世の中面白くなるかもしれません。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
はらだ有彩(はらだ・ありさ)
11月16日生まれ、関西出身。テキストレーター(テキスト/テキスタイル/イラストレーション)。2014年から、テキストとイラストレーションをテキスタイルにして身につけるブランド《mon.you.moyo》を開始。これまでに、ウェブマガジン「アパートメント」「リノスタ」「She is」などにエッセイを寄稿。現在「アパートメント」「She is」「wezzy」に連載中。
twitter:@hurry1116
http://arisaharada.com/
Instagram:@arisa_harada
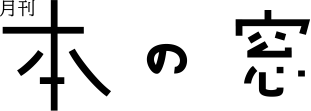
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2019/01/20)






