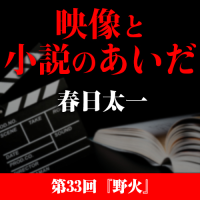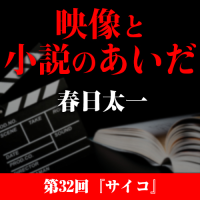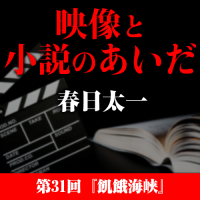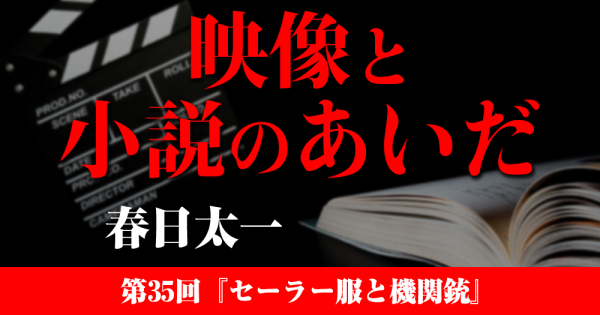連載第35回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
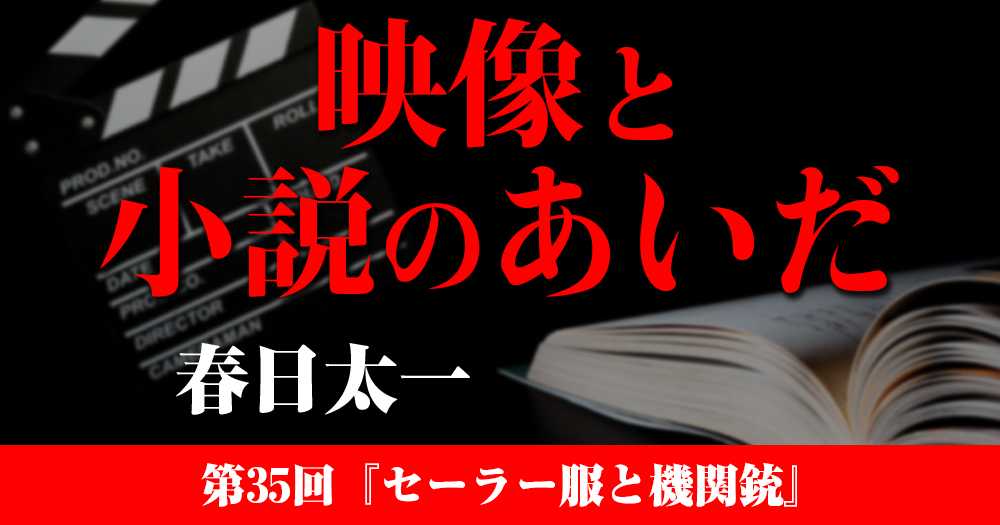
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『セーラー服と機関銃』
(1981 年/原作:赤川次郎/脚色:田中陽造/監督:相米慎二/制作:キティ・フィルム 、角川春樹事務所)
「カ・イ・カ・ン」
普通に暮らしていた女子高生・星泉は父親の事故死を契機に、親戚の親分をしていた弱小ヤクザ組織・目高組の跡を継ぐことになる。そして、父の死とも関連の強いヘロイン密輸を巡る抗争に巻き込まれていった――。赤川次郎の小説は、過去に何度か映画化されているが、特に最初の映画化作品は名作と名高い。
物語の大枠は原作とほとんど同じなのだが、その中身はかなり改変されている。
まず、泉(薬師丸ひろ子)のキャラクターだ。泉は父親の葬儀をすることになるのだが、原作では口うるさい叔母の他、参列者がいる。それに対して映画では、「誰にも知らせなかった。私一人の手で天国に送ってあげたかったから」と――最終的には泉の同級生男子三人組が参列しているものの――1人で全てを行おうとしている。
また、父親に対する認識の違いも垣間見える。映画では「私はパパの娘であり、妻であり、母親であったわけですから、いちおうは。最後の面倒まで、しっかり見ておきたかったわけ」と言っているのに対し、原作は「兄弟もない泉にとって、父は、親友であり、教師であり、恋人だった」となっている。つまり、原作では父親に頼り切りなのに対し、映画は「母親」「面倒を見る」という表現があるように、泉は自分の方が世話を焼いているという認識でいるということだ。そのため、原作はより「等身大の女子高生」に近い一方、映画は孤独と母性が強まっており、凛とした印象を与えている。
それが如実に表れているのが、若頭の佐久間(渡瀬恒彦)ら組員たちが泉を組長として迎えるために高校の校門で待ち構える場面だ。教員も含めて大半の人間がパニックに陥り、生徒は裏門から帰るように促される。ここは、映画も原作も変わらない。ただ、原作はわずか四人しかいない組員のみが参加しているのに対し、映画は佐久間が大勢のサクラの黒服を雇っており、原作とは比べものにならない威容を放つ。その結果、そこに物おじせずに毅然と対峙する泉の姿が、より凛々しく伝わることになった。
ここからの展開も、大筋は同じながらも印象は全く異なるものになっている。原作は、泉の父親が海外から持ち込んだとされるヘロインの包みの行方や父の死の真相、その秘密を握るとされる父親の愛人「マユミ」の消息や正体など、ミステリーの要素が強い。それに加えて、泉のさまざまな危機を同級生三人組が助けようと関わってくることで生じる賑やかさもあって、基本的にはカラッと明るい青春コメディ小説という色合いが強い。
映画は、包みの話は前半はあまり出てこず、マユミ(風祭ゆき)も原作のように「誰が本物のマユミか」といった謎はなく、序盤に登場したマユミが終盤まで出続ける。また、三人組も早い段階で登場しなくなる。原作の序盤~中盤を構成した大きな要素が、バッサリ消えているのだ。
その一方で、原作から追加された要素がある。
たとえば家が荒らされた後、泉は三人組&若手組員たちと寺の大仏の前で夜中に宴会をする、映画オリジナルの場面。先に帰ろうとする三人組に対して、泉は組員たちと残る。そして、「もう少し賑やかな気分でいたいの。一人になりたくないわけ」「ムシャクシャした気分を吹っ飛ばしたいの!」と、組員のヒコ(林家しん平)の運転するオートバイの後部座席に乗り、暴走族を従えて夜の新宿通りを疾走している。
また、マユミからの電話に「あんまり元気じゃありません。世の中いやなことばっかりで」と愚痴ったり、高校生でありながら登場時から哀愁漂う歌謡曲「カスバの女」を口ずさんだり――。
つまり、泉が鬱屈を抱えていることが映画では強調されているのだ。そのため、原作よりも重い空気が全編を覆っている。泉は父が死んだ際に「一人になっちゃった。でも大丈夫」と必死に前を向いた。そんな彼女にとっての新たな家族が目高組であることを、映画はより明確に描いている。
それは、組員たちも同じだ。彼らも、それぞれに抱えているものがある。ここで、泉のキャラクターが脚色されていることが効いてくる。
たとえば、悪徳刑事の黒木(柄本明)に刺された組員・メイ(酒井敏也)を泉が介抱する際、メイは懐に顔を埋めて「いい匂いがします。オフクロのニオイがします」と安らぐ。
また、マユミとの情事を泉に見られた佐久間のセリフも印象深い。
「ヤクザってもんがよくわかったでしょう。口じゃあ偉そうなこと言っても、腹の中はドロドロに腐っちまってるんです。テメエでテメエのいやなニオイにやりきれなくて、もっと汚えもの、テメエより腐ったものにのめっていく。そうしねえと、一日の終わりが切なくて、遠吠えでもしてみたくなるんすよ! オオカミみたいに!」
この時の泉は、最初は嫌悪感を示していたものの、やがてその魂の咆哮を受け止めている。その姿は、罪人の告解を聞く神父のよう。序盤で原作以上に強調された泉の凛々しさは、ここに至って神聖ともいえるカリスマ性を帯びる。
つまり、腐った中で生き続けたヤクザたちが初めて出会った、清い安らぎ――。まさにその名前のように「泉」のような存在なのだ。こうしたシーンは、いずれも原作にはない。
後半の展開も、大筋は変わらないながらも全く異なる印象を与えている。
ヘロインの密輸は大組織を率いる「ふとっちょ」こと三大寺(三國連太郎)が仕組んだものだった。三大寺は自身の秘密のアジトに泉を拉致、その口を割らせるべく拷問にかける。三大寺がかなりの残虐非道のサイコパスであることには違いはないのだが、映画には一つの設定が加わっている。
それは、地雷だ。映画の三大寺はかつて自ら地雷の上に立ったことがあった。地雷は踏むだけでは爆発しない。足を放した時に初めて爆発する。そのため、地雷の上にいる三大寺は、少しでも動けば爆発させてしまう。やがて足がしびれ、その感覚が全身に広がる。そして訪れる生と死のギリギリの感覚。それを三大寺は「快感」と呼んだ。
「快感とは死と隣り合ってるものなんだ」と言う三大寺に対し、「わかりません」と返す泉。三大寺は「わからせてあげたいねえ」と笑う。サイコパスの悪役とヒロインとのありがちなやりとりに思えるこの応酬が、実は終盤に効いてくる。
佐久間により三大寺の元から泉は救出された。だが、ヘロインは目高組も世話になっていた大親分・浜口(北村和夫)に渡っていた。全てのケリをつけるべく、泉は佐久間――映画では組員の政(大門正明)もいる――とともに浜口の事務所へ乗り込む。
そして、浜口に向かって機関銃をぶっ放した際に泉が言ったのが、冒頭のセリフだ。これは原作にはない。そして、この映画を象徴するセリフの裏側には、二つの心境が考えられる。
一つは、これまで抱えてきた鬱屈からの解放だ。最もムカつく対象に思いきり機関銃を放ったことで、スッキリしたということ。
ただ、それだけではない。そう、先に挙げた三大寺の「快感」についてのセリフだ。つまり、これまで暴力や死を否定してきた泉もまた、三大寺と同じく一線を超えたのである。
そして、物語の終わりも少しだけ異なっている。
目高組は解散し、泉は復学した一方、佐久間にはカタギになるよう諭していた。しばらくして、泉を刑事が訪ねる。新宿でヤクザ同士のケンカがあり、その間に入って止めようとした男が命を落としたという。そして男は、泉の名前と住所を記したメモを所持していた。その身元確認のため、刑事は泉を訪ねたのだ。
遺体安置所で泉が目にしたのは、佐久間の遺体だった。ここからが、映画と原作で全く異なる展開になる。
原作は、まだヤクザを続けていたと思い込んだ泉が佐久間に呆れ、誰だかわからないと刑事に告げる。だが、家に帰ると佐久間の名刺が郵便受けにあり、佐久間が札幌で真っ当な仕事に就いており、東京出張のついでに泉を訪ねたのだと知る。泉が刑事に電話を掛けるところで、物語は終わる。
一方、映画では佐久間は泉に家を訪ねるも名刺は置いていかず、所持したままだった。そのため、泉は佐久間の近況を安置所で知ることができている。
「放っておけば、どちらかがムダな血を流さなきゃならない。それを承知で、背を向けるわけにいかなかったんです」
そう佐久間の想いを代弁すると、佐久間に口づけをした。それは永遠の別れを意味するものであり、泉にとって初めてのキスだった(原作では浜口に強引に唇を奪われている)。そして、西新宿の歩道橋で佐久間の名刺をちぎって、空に放った。それはまるで散骨のようであり、二人が命を燃やした西新宿の空は、最高の埋葬の場といえた。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。