連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:長坂道子(ジャーナリスト、作家)
ヨーロッパを揺らす難民問題。その草の根を丁寧に取材し続けてきた長坂道子さんに、難民問題の現実から見えてきた世界の、そして日本の未来への希望をお聞きしました。
第十六回
武器を置いて、箸を取りましょう。
ゲスト 長坂道子
(ジャーナリスト、作家)
Photograph:Hisaaki Mihara

長坂道子(左)、中島京子(右)
難民問題に関しては、まったくの新参者です
中島 長坂さんがお書きになった 『難民と生きる』(新日本出版社)を読んで、本当に驚きました。ヨーロッパに押し寄せる難民問題は日本でも報じられていますが、個人にスポットを当てた市民生活レベルでの難民問題に触れたルポに衝撃を受けました。どういう経緯で、難民を取材されようと思ったのですか?
長坂 私はいまスイスに住んでいるのですが、ヨーロッパには中東やアフリカから多くの難民が流れ込んでいます。とくに二〇一五年の夏以降は私たち市民レベルでも日常的な課題のひとつとして目の前に突きつけられるようになりました。
中島 もともとそういった社会問題に興味を持っていらしたのですか?
長坂 いえいえ、まったく。何しろバブル時代の日本育ちですから。ヨーロッパに渡るまでは、政治や社会問題に対してほとんど関心はありませんでした(笑)。
中島 日本では大学卒業後、女性誌の編集者をされていたんですよね。
長坂 婦人画報社のファッション誌『25ans』の編集部に勤めていました。一九八〇年代のことです。当時は、バブルの真っ直中。雑誌も元気だったので、自分たちのつくる企画が世の中に響いている実感があって、毎日が楽しかったですね。
中島 おしゃれな『25ans』から、難民取材へ。とんでもないギャップです。
長坂 一九八八年に日本を離れたので、もう三十年ちかくになります。縁があってパリ在住時代に現在の夫と知りあい、ヨーロッパ数か国をめぐりながら暮らしてきました。そのなかでヨーロッパ的な市民意識や社会意識、政治意識が私のなかにも育てられたのでしょう。
中島 ご主人のご家族との出会いが大きかったと『「モザイク一家」の国境なき人生』(光文社新書)にも書かれていました。
長坂 もう亡くなりましたが、義父はユダヤ系のイラク人で義母はモルモン教徒のアメリカ人。一緒に生活するなかで、いやでも民族や宗教の違いを感じずにはいられませんでした。

長坂 私たちアジア人が、ヨーロッパで白人から差別されるのは、気持ちのいいことではありませんが、まぁ理解できる。ところがイラク人の義父から差別的な視線を向けられたのには驚きました。でも、時間をかけ、お互いの人となりがわかってくると、差別感情もいつのまにか薄れていく。晩年の義父は「俺たちオリエンタル系だからわかるよね」と、白人然とした自分の息子よりもむしろ私に対してシンパシーを感じていたようです。
中島 実の息子より! オリエンタル系だから仲間、という感覚は、興味深いですね。
長坂 義父は商人で、高い教育も受けていませんでした。だから考え方がシンプルなんですね。愛情を持ち、仲間を守るという、それ自体は素朴で善良な意識からも、人を差別したり、排除したりする気持ちが育っていくんだなということを実感しました。
中島 ご主人のご家族と過ごされた時間が、長坂さんにとって大きな転換期だったんですね。難民問題は、人種間の問題ともつながっていますし。
長坂 そして、やはり二〇一一年三月十一日の東日本大震災です。いままで普通にあったものが一瞬にしてなくなる。自然災害に対する怖さはもちろんですが、その後の政治的混乱や東電の隠蔽体質など人災が災害に拍車をかけたでしょう。しかもそれが祖国の出来事ですから。
中島 離れているからこその衝撃や不安、動揺もあったでしょう。
長坂 3・11後にドイツやスイスをはじめ、ヨーロッパ各国で津波や原発の安全性についていろいろな議論が行われ、新しい法整備の動きが次々と起こるのを目の当たりにしました。かたや当事国の日本を見ると、いったん原発はやめようという動きがあったけれど、民主党政権の最後の頃には再稼働に舵を切った。
中島 政治家や日本政府の言うことが信じられなくなった、決定的な出来事でした。
長坂 原発事故によって破滅的な危機を感じた日本がなぜそんなことを、と素朴な疑問が生まれ、少しずつ国際問題や政治問題を勉強しはじめたんです。そしていま、その先にある難民問題にようやくたどり着いたところです。だから、難民問題に関しては、まったくの新参者なんですね。
中島 難民問題は、宗教や政治、国際情勢が複雑に絡み合っているから、専門家の方の話を聞いていても、ついていけないところが多い。でも、わからないから、わかりたいという長坂さんの気持ちが取材の随所にあらわれている。それが私たち読者と近い目線になっていて、ともすれば難しくなりがちな難民問題がすっと頭のなかに入ってくるのだと思います。
長坂 担当してくれた編集者も「それでいいんだ」と背中を押してくれました。だから、私も難民問題の勉強をしながら、何も知らない人に読んでもらうという前提で取材を始めました。
いまはまさに歴史の教科書に太字で記される時代
中島 難民のなかに飛び込んで、ナマの話を聞く。言葉で言うのは簡単ですが、それを実践したところがすごいなと思います。取材対象として地元のスイスではなく、ドイツを選ばれたのはなぜですか?
長坂 いま、もっとも多くの難民が出ているのはシリアです。ヨーロッパへと向かうには、トルコからギリシャなどを経由するバルカン半島ルートを選ぶ人が多い。スイスにくる難民の数は今回はそれほど多くないんです。
中島 それで、難民問題を取材するなら、最も多くの難民を受け入れているドイツだと。

中島 ドイツは、二〇一五年だけでも九十万人近くの難民を受け入れたそうですね。その数字が実際にどんなものなのか。日本では報道も限られていて、私たちには実感がありませんでした。
長坂 当初、彼らが一時的に暮らすことのできる難民ハイムを作って受け入れ体制を整えるところから始まったのですが、全然間にあわない。あちこちの路上で人が寝ているような状態でした。
中島 路上で! まるで第二次世界大戦の東京大空襲の後みたいですね。そんなことが、現代のドイツで実際に起こっていたなんて。
長坂 その様子を見たドイツの人たちのなかから、言葉も通じない、宗教も生活習慣もちがう、見ず知らずの難民を自宅に滞在させる人がどんどん出てきました。
中島 まったく知らない人を自宅に泊めるというのに、不安はなかったんでしょうか。
長坂 とにかく路上に人が溢れている光景に、度肝を抜かれたのだと思うんです。ドイツ人も日本人のように生真面目なところがあるので、良くも悪くも「助けなくちゃ」という一種の熱狂がひろがっていったんでしょうね。
中島 たとえば、シリアからの若者を受け入れてくれないかと頼まれたご夫婦。若者は英語もドイツ語もわからない。しかも「心理的な混乱があり、同性愛者です」という依頼者側の補足説明にも「もちろん、どうぞ」と答えて、彼を受け入れます。
長坂 マルティナさんですね。
中島 同性愛者の人と親しく知り合った経験がないととまどいながらも、一緒に暮らしているうちに彼のことを自分の息子のように感じるようになるんですね。自分にできるだろうかと考えながら読み進みました。
長坂 取材したひとりひとりを難民や支援者といった「カテゴリー」ではなく「顔の見える個人」として描き出したかったので、そう言っていただけるとうれしいです。
中島 一方ハンガリーでは、難民に対し排斥的な動きが起こったりするなど、EUの国のなかでも温度差がありましたよね。
長坂 それまで民主主義や人権主義は、EUのトレードマークだと思っていました。でも難民危機という試練が踏み絵のように襲来したときに、各国共有していると思っていたはずの価値観がじつは違っていた。ポーランドでも、キリスト教の価値観に反する人たちを受け入れるわけにはいかないという動きも起こりました。
中島 キリスト教の難民はいいけどイスラム教は困る。
長坂 本音はそうでも、建前としては口にしないのが、それまでのEUでした。しかし難民問題はEU各国の本音が発露し、歯車がくるいはじめた契機でもありました。
中島 戦争をなくすためにひとつになろうというEUの理想は確かに素晴らしい。でも考え方の違う国をひとつにまとめて、仲良くやっていくのは並大抵のことではないんですね。
長坂 なかでも大きな出来事がBREXIT(ブレグジット)。EUの難民受け入れ政策などに対する国民の不満が大きくなったイギリスのEU離脱決定です。
中島 国民投票前日までは、まさか離脱することはないだろうと世界中が高をくくっていたと思います。
長坂 投票結果が出たときには、EU崩壊かと大激震が走りました。その後に、オランダの総選挙とフランスの大統領選挙が行われましたが、取りあえず最も恐れていた自国第一主義、そしてEU離脱の方向には動かなかった。次はドイツの総選挙が控えていますが、極右が勢力を持つ可能性は少ないと思います(※九月二十四日の総選挙で極右政党AfDは大幅に得票率を伸ばし、十三パーセント強を獲得した)。

長坂 そう思います。これからも、まだまだ不安定な時代は続きそうですが。
中島 お話を聞いていると、EUのなかでもほぼ無条件で難民を受け入れているドイツが特殊かなと思います。
長坂 まずひとつには、ドイツ経済が好調だということが挙げられます。たとえば、自国内に失業者を山のように抱えている状況でさらなる難民を何十万人も受け入れることは、たとえ為政者にそのような意思があったとしても、国民からの反発が強く、簡単ではありません。
中島 旧東側諸国などは経済的にも大変そうですものね。
長坂 そして、もうひとつ。ドイツの戦後教育です。第二次世界大戦でナチスが何を行ったのか。歴史の授業で徹底的に教えます。ナチスを生み出した反省が、戦後ドイツの出発点になっているのです。
中島 ナチス政権は、当時世界で最も民主的だと言われたワイマール憲法下で、国民の選挙によって選ばれたわけですからね。
長坂 ドイツ人は民主主義がいかにもろいものか身をもって知っている。だから、市民ひとりひとりが不断の努力で、勝ち取り、守り続けていかなければいけないものなのだという意識があるんですね。
中島 日本とは、残念ながら、ずいぶん違いますね。日本はあの戦争、敗戦から学んでいない。そう思うと、失敗したという気持ちになりますね。
長坂 日本には、原爆投下があったでしょう。戦争を引き起こした加害国としての責任より、その被害者としての意識がどうしても前面に出てきてしまう。ドイツの場合は言い訳できない。日本でも、唯一の被爆国としてはもちろん、それに加えて加害国としての平和運動をもう少し強調していけたらとは、思いますね。
中島 まず、あの戦争をきちんと整理して、学び直すことから始めないと。
長坂 さらに戦後ドイツ人自身も難民になった経験があるんですね。ロシアや東欧にいたドイツ人たちは帰る場所を失った。そのときに周辺諸国が受け入れてくれたそうです。戦後、近隣諸国との良い関係を何とか築いてこられたのも、あれだけひどいことをやったドイツに、イギリスやフランスがまた一緒にやっていこうと手を差し伸べてくれた。それに対する感謝の気持ちがあるように見受けられるんですね。みんなに助けられてドイツはここまで来た。次は自分たちが難民を助ける番だ。そういう集団心理もあると思います。
武器を置いて、箸を取ろう
中島 今回長坂さんが取材された方々を見ていると、自宅に難民を受け入れているのは子育てが終わった五十代くらいのご家庭が多いように思いました。えっ、私と同世代、と驚いたのですが。
長坂 五十代というのは、残りの人生どうしようかと初めて逆算的に考え始める年代だと思うんですね。それは多分、先進国どこも共通。平均寿命が長くなっているから、退職後二十年は元気にすごせる。もう一仕事なにかをやってみたい、と考える年代なのでしょう。
中島 なんかいいですね。私たちも含め、この年代の人たちがもう少し社会参加を考え始めると、日本もかわるかもしれないですね。
長坂 私たちの世代が過ごした社会は、戦争はもう遠い過去のことだし、経済も好調でした。まれに見るいい時代を過ごしているんです。でも、これは普通じゃなくて、稀有なケースなんだと痛感するようになりました。たまたま歴史上のある地点に、ある場所に生まれ落ちた偶然で、いい時代を生きさせてもらったのだから、せめてちょっとお返しをという気持ちが芽生えてきています。もしいま身近に助けを求める人が現れたとしたら、子どもも大学に行って部屋も空いているからどうぞ、と素直な気持ちで言えるんじゃないかな。
中島 二十一世紀的な、新しい文化かもしれない。

中島 困っている人がいるから、ちょっと手を差し伸べるくらいの感覚なんですね。
長坂 そうですね。普通に親切な人なら、もうちょっとだけ親切になれば、案外できることじゃないかな。
中島 長坂さんのお話を聞いていると、この世界に対する希望が生まれてくるような感じがします。
長坂 一緒に暮らすとは、腹を割って話そうとか、食卓をともにしようということでしょう。
中島 食卓を囲めば、そこからコミュニケーションが生まれますよね。私も、作家が集まるプログラムでアメリカに行ったとき、肉じゃがを食べさせて「イラクのお母さんの手料理にそっくり」と言われたことがあるんですよ(笑)。食行動が近い東アジアの人たちとは、とくにすごく仲良くなったんです。
長坂 そうなんです。アジアも反目しあっている場合じゃない。食で仲良くなればいいんですよ。これからは、武器を置いて、箸を取りましょう。
中島 いい言葉ですね!
長坂 日本には憂うべき問題はたくさんありますが、いいこともいっぱいある。まず食事がおいしいでしょう。あと、心根がね、優しいんですよ、日本人は。帰国するたびに思います。その優しさをいい感じに生かしていくと、アジアの人たちとも仲良くやっていける。国によって歴史に対する理解の違いはあっても、おなじ職場で働いたり、おなじ学校で学んだり、おなじ食卓を囲んでいるうちに案外ほぐれていくものではないかと思います。
中島 長坂さんの義理のお父さんとの関係のように。
長坂 そう、だいじょうぶですよ。EUのようにひとつのアジアになって仲良くできたらいいなと思います。
中島 日本はおいしくて優しい国として、アジアの扉を次々ノックしていくといいですね。勇気が出てきました!
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
長坂道子(ながさか・みちこ)
1961年愛知県生まれ。ジャーナリスト、エッセイスト、作家。京都大学文学部哲学科卒業後、雑誌『25ans』(婦人画報社=現ハースト婦人画報社)の編集部を経て、88年渡仏。その後ペンシルヴァニア、ロンドン、チューリッヒ、ジュネーヴなどに移住。現在はチューリッヒ在住。著書に『フランス女』『裸足のコスモポリタン』『世界一ぜいたくな子育て』『「モザイク一家」の国境なき人生』『旅に出たナツメヤシ』など。
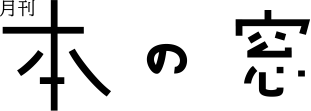
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2017/10/20)






