日本の文豪たちの泥沼エピソードまとめ【不倫・盗作・殺人など】

恋愛事件から盗作、さらには殺人に至るまで……明治から昭和にかけての、時代を代表する作家たちのスキャンダル報道を通じて見えてくるのは「ゲスの極み」の文学史!
2016年に入ってからというもの、週刊誌やテレビでは、「ゲスの極み」なスキャンダルが次々に報道されています。若手バンドのボーカルと好感度ナンバーワン女性タレントの不倫、超人気アイドルグループの謝罪生放送、元プロ野球選手の薬物騒動などの事件が、日々世間を騒がせています。
このような報道が注目を集めるということは、それだけ多くの人が、スキャンダルに関心があるということなのでしょう。これらのスキャンダルに共通しているのは、背後にドロドロした複雑な事情があることを読者や視聴者に想像させることです。
どれだけ下世話な好奇心といわれようが、有名人の泥沼エピソードはいつも気になるもの。そこで今回は、過去に巷を騒がせた文豪たちの泥沼エピソードについて見ていきたいと思います。
小説家と恋愛スキャンダル
「文豪」といえば、どこか権威のある立派な人だというイメージがつきものではないでしょうか。一方で、日本の有名な小説家の多くが自殺したり、自分の恥部を私小説としてさらけ出してきたりしたのもまた事実。一番わかりやすいスキャンダルは、なんといっても異性関係でしょう。
日本における最初の私小説ともいわれる田山花袋の『蒲団』(1907)は、世間に「女弟子に欲情していました」という中年作家の告白として受け取られ、女弟子の布団の匂いを嗅ぐ場面などが文壇に衝撃を与えました。
暫(しばらく)して立上って襖を明けてみた。大きな柳行李(やなぎごうり)が三箇細引で送るばかりに絡(から)げてあって、その向うに、芳子が常に用いていた蒲団――萌黄唐草(もえぎからくさ)の敷蒲団と、線の厚く入った同じ模様の夜着とが重ねられてあった。時雄はそれを引出した。女のなつかしい油の匂いと汗のにおいとが言いも知らず時雄の胸をときめかした。夜着の襟の天鵞絨(びろうど)の際立って汚れているのに顔を押附けて、心のゆくばかりなつかしい女の匂いを嗅かいだ。
この小説は花袋の弟子にあたる岡田美知代と岡田の恋人、永代静雄との間の実際の三角関係をモデルにしており、1910年には岡田が「ある女の手紙」というアンサー小説を返すなど、その生々しさが世間の耳目を集めました。
さらに、夏目漱石の弟子である森田草平と、平塚明子(平塚らいてう)の心中未遂事件も、恋愛沙汰として世間を騒がせました。のちにこの事件は森田自身によって、小説『煤煙』として書かれることになります。異性関係は文学にとって重要な題材でもあり、泥沼の恋愛関係を描いた小説は、不倫を扱った辻仁成の『サヨナライツカ』、江國香織の『東京タワー』など現代でも数知れずあります。

谷崎潤一郎の泥沼三角関係
文豪同士の恋愛スキャンダルとして特筆されるのは、谷崎潤一郎の「細君譲渡事件」として知られているものでしょう。1930年、谷崎潤一郎の夫人である千代は、谷崎と離婚し、佐藤春夫と結婚します。谷崎と佐藤の間で、千代を佐藤に譲ることを、三人の連署により公言した挨拶状が新聞報道され、大問題となりました。
この背景には、1921年の「小田原事件」と呼ばれる、千代夫人をめぐって谷崎潤一郎と佐藤春夫が絶交に至った出来事がありました。現在では、佐藤春夫による単純な略奪愛だったいうよりも、千代の妹、セイ子と懇意になった谷崎が佐藤に妻を譲る約束をしたものの、後年になってその約束を反古にしようとしたことが「小田原事件」の真相であったということが明らかになっており、さらには千代夫人をとりまく第三の男として和田六郎という青年、のちの推理作家・大坪砂男の存在があったことが瀬戸内寂聴の「つれなかりせばなかなかに」という本の中で明かされるなど、そのドロドロの人間関係にまつわる多くの事実が明るみになっています。
なお、「細君譲渡事件」をもとに、谷崎潤一郎は『神と人間の間』や『蓼喰ふ虫』、佐藤春夫も『秋刀魚の歌』という小説をそれぞれ執筆しています。小説家は、自分の泥沼エピソードもまた、ネタにしてしまうのですね。
泥沼化?した盗作騒動
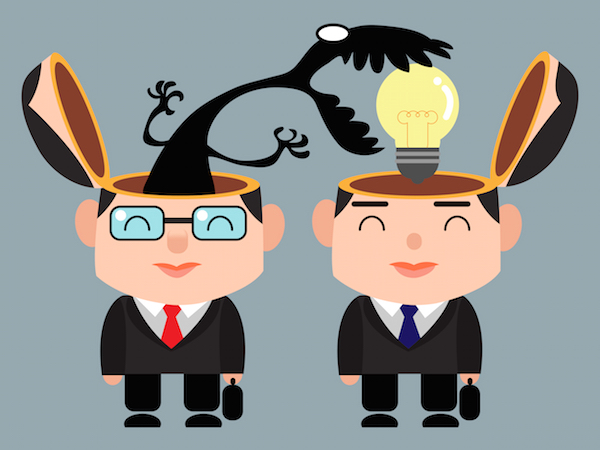
近年も、五輪エンブレム問題など騒ぎになっている盗作問題ですが、文豪による盗作騒動も繰り返し起こっています。ここでは立松和平の件について紹介したいと思います。
立松和平は連合赤軍をテーマとして、『光の雨』という小説を1993年から雑誌『すばる』に連載していました。ところが、これが、坂口弘の著書『あさま山荘1972』の盗作ではないかという騒動に発展。こうなると当然、泥沼化が予想される展開です。
さて、どうなったかと言いますと、立松はすぐに盗作を認めて謝罪するとともに、『すばる』への連載を打ち切りました。その後、坂口弘と連合赤軍メンバーの永田洋子に謝罪の手紙を送り、それを『すばる』誌上に載せるなど関係者へのやりとりを済ませると、1998年に『新潮』に全面的に改稿を施した作品を発表、新潮社から単行本化しました。そのあと、2001年には映画の題材にもなっています。というわけで、盗作騒動は当初の騒ぎよりもすんなりと決着を迎えることとなりました。
ところが、立松の盗作問題は、一度では終わりませんでした。2008年、立松は同じく新潮社より『二荒』(ふたら)という小説を出版します。これがまた、福田和美の小説『日光鱒釣紳士物語』の盗作ではないかということになり結果、小説は絶版になります。しかしその同年、立松は『二荒』を抜本的に改稿したものを、『日光』という小説として、勉誠出版から出版します。
さて、これらを泥沼化といっていいのか、すっきりした対応であったというべきか。五輪エンブレムの事件でもわかるように、盗作問題は諸説が挙がって混迷状態に陥りやすいものです。立松の態度はいたって冷静で、なんとも不思議な静謐さに包まれたスキャンダルでした。
(次ページに続く)
- 1
- 2





