連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:いとうせいこう(文筆家)
七十数か国で医療活動を展開する国際NGO「国境なき医師団」。その現場を取材し、世界の過酷な現実を肌で感じてきたいとうせいこう氏とともに、私たちが向かうべき明日を考える。
第二十回
お金以外の価値を持ちたい
ゲスト いとうせいこう
(文筆家)
Photograph:Hisaaki Mihara

いとうせいこう(左)、中島京子(右)
僕は、おせっかいな広報記者
中島 『「国境なき医師団」を見に行く』(講談社)は、Yahoo! での連載を本にまとめたものだということですが、そもそも、なぜ「国境なき医師団」を見に行くことになったんですか?
いとう きっかけは「国境なき医師団」(MEDECINS SANS FRONTIERES/以下MSF)側からの取材を受けたことなんです。ある傘屋さんと「男日傘」という商品を企画して、そのパテントをMSFに寄付していたんですね。それを知ったMSFの広報の谷口さんという方が、僕に興味を持って取材に来てくれたんです。ところが、MSFの現場の活動の話を聞いてみると、あまりに知らないことばかりだと驚いて。これは、もっとちゃんと伝えなきゃいけない。僕ならMSFの活動をうまく書けるんじゃないかと。そこから逆取材が始まったんです。
中島 私も、この本を読むまでは、MSFのメンバーは、全員お医者さんだと思っていました。特別なお医者さんが、医療の足りない地域でボランティアのような活動をしている組織。恥ずかしながら、その程度の認識でした。
いとう 僕も、同じです。いや、きっと日本のほとんどの人がそう思っているんじゃないかな。だから、もう、MSFの活動の現場をこの目で見て、そこで起こっていることをちゃんと伝えなくてはという、おせっかい精神がむくむくと顔を出して(笑)。
中島 MSFの活動費のすべてが寄付によってまかなわれていることも知らなかったし、世界中からさまざまな年代の人たちがいろんな役割で参加していることにも驚きました。
いとう これまで、MSFの活動を紹介した写真集などはありましたが、作家が活動地に入って、スタッフのプライベートヒストリーを聞き書きするのははじめての試みらしいのです。
中島 そう聞くと、まるでせいこうさんがMSFの広報記者みたい。
いとう 気持ちとしては、そうです。だから、僕の視点は中立ではなくて、思い切りMSF寄り。この本がきっかけで、もっともっと寄付が増えればいい。もっと多くの人が関わるようになればいいという思いで書きました。
中島 今回は、ハイチ、ギリシャ、フィリピン、ウガンダの四つの地域を取材されていますよね。これは、せいこうさん側からここに行きたいと希望を出されたんですか?
いとう いやいや、まったく。僕のスケジュールの空いているところを押さえて、その期間に取材を受け入れてくれる場所を探してもらいました。最初に行ったハイチのときも、直前までどこにいくか決まっていなかったんです。

いとう 受け入れてくれる場所ならどこにでも行きますよ、というのが僕のスタンスなんです。しかも連載をはじめたら、取材したMSFの人たちがみんな読んでくれていると聞いて、うれしくなっちゃって……。
中島 誰かが英語やフランス語に訳してくれているんですか?
いとう webの自動翻訳システムが適当に翻訳してくれるから、それを読んでいると言っていました。
中島 なるほど! 自分のことが書かれているし、読みたいですよね、絶対。
いとう 悪口、書いてあるかもしれないけれどね(笑)。
中島 最初に取材に出かけたハイチでは、出発前に秘密の質問を決めたでしょう。不謹慎かもしれないけれど「スパイ映画みたい。おもしろいな」と思いました。
いとう MSFが活動している場所は、基本的には紛争などで治安が悪化している地域が多いんです。だから、MSFのメンバーといえども安全が保証されているわけではない。誘拐されたときに、本人を確認するための「プルーフ・オブ・ライフ」と呼ばれる暗号をあらかじめ決めておくんです。ハイチのときには、たしかいちばん好きだった猫の名前にしたんじゃなかったかな。
中島 せいこうさんがもし誘拐されたら、銃を突きつけられながら「猫の名前は何だ?」と聞かれるんだ。
いとう ちょっとまぬけな感じでしょう。でも、それが命をつなぐ鍵になるんですから。たぶんビジネスでそういう国に入っている人たちも、同じように暗号を決めていると思います。
中島 この本は、「俺」という一人称で書かれているのも、すごくいいですよね。ルポルタージュとしては、珍しいスタイルです。
いとう 勝海舟のお父さんの勝小吉が書いた『夢酔独言』。最高に好きなんですよね。日本最高のエッセイだと思う。それが「俺」なんです。「俺のようになっちゃ駄目だぞ」とか言いながら、喧嘩が強かったと自慢している。駄目なおやじなのに、なんか憎めないユーモアが感じられるんです。で、今回は、勝小吉流の「俺」で行こうと。「俺」は、主観押し出し型ではないでしょう。だから、絶妙だなと思って。
中島 悲惨なエピソードもたくさん出てくるので、「俺」にはそれを和らげる効果もある。こういう言い方はふさわしくないかもしれないけれど、楽しく読ませていただきました。
いとう MSFが活動している場所は、戦場や難民キャンプ、極貧地区などでしょう。やっぱりユーモアがベースにないと、描いている自分自身がきつ過ぎるんです。ユーモアはすごく重要なファクターでしたね。
武器では百万人を救えない
中島 特に考えさせられたのが、赤ちゃんの命ですね。
いとう ハイチのCRUO(産科救急センター)の話ですね。医療スタッフたちも、自分たちに救う赤ちゃんと救わない赤ちゃんを選ぶ権利がないことをわかっている。でも、生まれてきた赤ちゃんが感染症にかかっていることもあるし、お母さんが子どもを捨てていなくなったりすることもある。
中島 この赤ちゃんはこれからどうやって育っていくのか。自分では解決できないとわかっていても考えてしまいますよね。

中島 日本にいると想像もできない世界ですね。医療とはというよりも生命とは何かという問いを突き付けられながら、現場ではいつも、ぎりぎりの決断を迫られているんですね。
いとう 僕も短い時間ながら、その現場に立ち会って、やはりここではそうすべきなんだと理解するようになりました。それは自分にとって、大きな体験でしたね。
中島 毎日何千人単位で運び込まれてくるわけでしょう。終わりのない医療というのは、MSFのスタッフにとっても心身ともに苛烈なものでしょうね。
いとう やはりメンタルケアの問題は、最重要課題だと思います。だから彼らは、ウイークエンドにはきちんと遊ぶんですね。
中島 オン・オフをスパッと切り替えないと続けられない。
いとう そうです。それがPTSD(心的外傷後ストレス障害)の問題にもつながっていく。南スーダンなどに派遣された自衛官が帰国後、何人も自殺しているのを正視しないといけない。彼らがPTSDだったかどうかを議論している場合じゃないんです。戦地に行った人は、間違いなくPTSDのメンタルケアをしなきゃいけない。それが世界的な常識なんです。それをいまだに「あいつら、根性が足りん」とか言いかねないわけでしょう、日本では。
中島 相変わらず、精神論が大手を振って歩いていますから。悲しくなりますよね。そこにある事実を見ないふりしているだけです。
いとう 上に立つ人間がこういう考え方のままだと、この国は必ず立ち行かなくなるでしょうね。
中島 確かに、そう思います。せいこうさんが取材に入った、ウガンダはすごいですよね。内戦状態にある隣国の南スーダン難民を百万人も受け入れているなんて! 日本では、ヨーロッパへ渡るシリア難民のことは報道されても、南スーダンのことは報道されないから、まったく知りませんでした。
いとう 僕は百万人の難民を受け入れて、彼らに畑を与え、生活の基盤を築く機会をも与えているウガンダに対して敬意すら感じています。
中島 百万人もの人が逃げなくてはならない南スーダンの国内がどうなっているのか。想像しただけでもおそろしくなります。
いとう 南スーダン難民には、身内が殺されて自分も命からがらウガンダに逃げてきた人も多い。彼らは、自国で起こっていることをはっきりと「war」だと言っていました。
中島 そんな戦地に日本の自衛隊は派遣されていたんですね。
いとう それが、この国の国会では、戦争ではない武力衝突だと。
中島 本当にね。言葉遊びしている場合じゃない。
いとう 自衛隊も相当おっかない目に遭っていると思うんですよね。敵対する勢力が衝突したら、必ず撃ち合いになり、殺し合いになる。そういう現場を、見ていないはずはないんです。

いとう そのとおり。いくら武器を持っていても、百万人の難民は救えない。
中島 この本の中で書かれている、もう一つの大きな問題が、性暴力被害です。
いとう 戦争や紛争があれば、必ず性暴力は起こる。シリア難民の女性の九割は性暴力被害に遭っているそうです。一番先に傷つけられて、放置される。そういう人たちをどういうふうにケアしていくのか。いま世界では、解決すべき主要なテーマになっています。
中島 戦争という狂気が、異常な性欲を掻き立てるということ?
いとう 肉体的な欲望だけではないんです。特にボコハラムなどの過激派組織は、相手のプライドをズタズタに折ってしまうことで、精神的に屈服させて自分たちの支配下に置きます。女性だけではなく、男性に対しても同じです。
中島 ああそうか。性暴力の問題は、性欲ではなくて支配欲なんですね。
いとう 「女は世界の奴隷か!」と歌ったジョン・レノンの『Woman is the Nigger of the World』の時代から約半世紀がたとうというのに、この状態はまったく、改善されてない。
中島 世界の認識では、従軍慰安婦は性暴力の被害者と捉えられていますね。
いとう そうです。どういう形であれ、性暴力があったことは事実なわけだから。そこにいたる手続きがどうかなんてことは関係ない。
中島 性暴力は戦争や大災害と並列して語られるほど重要なトピックだと、私自身も初めてはっきり意識しました。世界が性暴力に向ける目を、きちんと理解している日本の政治家は少ないように思います。
いとう 世界から日本がどう見えているか。この本を読むとよくわかると思います。慰安婦は昔の問題で、歴史的には解決している。そう思っているのは日本だけです。それは世界の常識からしたら、あり得ないことです。
中島 せいこうさんが見てきた、MSFの現場というフィルターを通すと、世界のいろんなことがつながって見えてくるような気がします。
「愛」より「敬意」を
中島 MSFのサポートスタッフには、五十代や六十代の参加者も多いことも印象的でした。
いとう 体力的にハードな戦地は無理かもしれませんが、難民キャンプなど精神的に過酷な現場で一番大切なのは、人生の経験知なんですね。
中島 毎日大勢の患者さんが飛び込んでくるとはいえ、みんなひとりの人間ですものね。
いとう ひとりひとりの人間に対して、どう敬意を持って接するべきか。一方で、どこを厳しく律するべきか。人生経験が豊富な人たちは、そういうことをわかっている。だから、僕も含めて、リタイアする年齢になったらみんなMSFへ行けばいいのにと、勝手に思っています。そのとき、自分は何ができるかわからないけれど。
中島 いま、先進国では寿命が延びて人生が長い。子どもが手を離れ、仕事も一段落して自分の時間ができたら、他人のために使うという発想がいいなあと。

中島 ないですよね。
いとう いまはどうしても、すべての価値が貨幣に置き換えられてしまうでしょう。僕は、お金以外の価値として、敬意に価値を置き「リスペクト」という単位を作るべきだと、思っていたんです。今回MSFを取材して、ここの現場がまさにそうだと思いました。
中島 素晴らしい! せいこうさんに、百リスペクト(笑)。なんかいいですね。
いとう 「敬意」って何か。あなたがそこにいてくれて、ありがとうという気持ちでしょう。僕の師匠でもある能楽師の安田登さんが内田樹さんと対談したときに、内田さんが面白いことを言っていた。「愛」は、その場にあなたがいることに充実を与えてくれるものじゃない。そういう効果としては、むしろ「敬意」のほうが上だと。「敬意」は与えられると、「ああ、ここにいて良かった」と思う。僕らはついつい、「愛」で充実させようとしてしまうけれど、「愛」は、ひび割れたり、壊れたり、いろいろありますから。
中島 私は、認知症になった父を介護した経験があるんですね。そのときに「敬意」の大切さをすごく感じました。切ないくらいお父さんのことを愛していても、お父さんはわかってくれない。でもどんなに壊れちゃっていても、私はお父さんを尊敬している。その気持ちが伝わると、父はうれしそうにするんです。人間にとって、自分が人間である尊厳というか、誇らしさのようなものを与えられることは、すごく大事なんだなと思いました。
いとう たぶんいま日本の社会でいちばん欠けているのは、この「敬意」なんじゃないかな。
中島 そうかもしれない。
いとう 「愛しなさい、もっと愛しなさい」と言われるけれど、愛は水平軸の力なんです。人を上に持ち上げることはできない。「敬意」は、垂直軸。自分の価値を上に上げてくれるシステムなんですよね。
中島 それはすごく重要ですね。どちらかというと、下げよう、下げようという力に対して同調することの多い時代ですから。
いとう ネットを見ても、ディスり合いや、足の引っ張り合いばかり。でもね、敬意を払うことなんて簡単なこと。お金を使わなくても、誰でも気持ち良くなれるんです。
中島 お金ではなく「敬意」の価値を高めること。日本の閉塞感をきりひらくキーワードかもしれません。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
いとうせいこう(いとう・せいこう)
1961年東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業後、講談社で編集者として勤務。その後作家、クリエーターとして、活字・映像・音楽・舞台など広い分野で活躍する。『ボタニカル・ライフ』で第15回講談社エッセイ賞受賞。『想像ラジオ』で三島賞、芥川賞候補となり第35回野間文芸新人賞受賞。主な著書に『ノーライフキング』『存在しない小説』『鼻に挟み撃ち』『「国境なき医師団」を見に行く』『雑談藝』(共著みうらじゅん)『小説禁止令に賛同する』などがある。
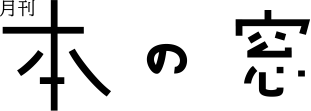
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2018/02/20)






