連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:林家たい平
現在、首都圏で行われる落語会は月千件を数え、落語協会に所属する真打はこの秋にも209人に達するという。その落語ブーム牽引役のお一人が、昨年度の浅草芸能大賞奨励賞を受賞された林家たい平師匠です。落語の人気と魅力を伺ううちに、今失われつつある大切なものが見えてきました。
連載対談 中島京子の「扉をあけたら」
第三十二回
ようこそ、落語国へ。
ゲスト 林家たい平
(噺家)
Photograph:Hisaaki Mihara

林家たい平(左)、中島京子(右)
落語には弱い者いじめがない
中島 以前、師匠の高座を拝見したことがあるのですが、そのときは『芝浜』という古典落語でした。驚いたのは、酒好きの魚屋の勝を演じているときと奥さんを演じているとき、声色だけじゃなくお顔もまったく違って見えた。まるでその人が憑依しているように感じました。
たい平 ありがとうございます。一番嬉しいほめ言葉ですね。僕は、落語家はイタコのようなものだと思っているんです。覚えた噺をそのとおりにやるのではなく、その時々に登場人物が僕の体を使って、今話したいこと、伝えたいことをしゃべっているのが理想なんです。だから同じ噺でも毎回同じようにはできません。
中島 一期一会なんですね。そう言われると、何度も観たくなります。最近は、若い世代のお客さんも増えているそうですね。古典落語の世界を伝えるのは難しくありませんか。
たい平 「古典落語」という言葉は、たぶん評論家が作った言葉だと思うんです。評論しやすいように新作と古典を分けた。しかし落語はどれもすべて今を生きている人間を語っているので、新作も古典もないと思うんです。
中島 なるほど。ただ舞台である江戸時代と現代とでは、人の考え方や生活環境もぜんぜん違うから、聞き手の方にも知識や想像力が要求されますよね。
たい平 まさにそうなんです。中島さんがご覧になった『芝浜』でも、飲んだくれの亭主を働きに行かせるときに、奥さんが「おまえさん、釜のふたが開かないよ」と言うんです。あんたの稼ぎがないから米も買えず、ご飯が炊けないよという意味です。でも今の人は、お釜がご飯を炊くものだとはわからない。そもそも酒に溺れて働きに行かないようなダメな男とは早く別れてしまえばいいのにと思われたら、お客さんはもうその後のお噺の世界に入ってきてくれません。
中島 本なら、わからない言葉が出てきたら辞書を引けるし、お話がわからなくなったら前のページに戻って読みなおすことができるけれど、落語はライブだからこその難しさがあるんですね……。ところで、師匠は、落語には弱い者いじめがないと、おっしゃっていました。確かに、ちょっぴり愚かな与太郎が出てくるお噺も多いけれど、みんなで散々いじめたあげく与太郎が自殺してしまいました、というような結末のものはないですものね。
たい平 どんなにダメなやつでも、遊びにいくときには一緒に行くし、何かあると、おい与太郎も呼ぼう、と声をかける。仲間外れはひとつもない。それがとても素晴らしいなと思うんですね。
中島 そういう世界を「落語国」って、師匠はおっしゃってましたね。人情があっていい世界。ほんとあったかい。落語国に住みたくなる(笑)。
たい平 みんな違っていていい。落語国の人たちはそう思ってるんだと思います。

たい平 芸術かどうかはわからないんですが、そういう世界だと思います。『芝浜』だと、二日酔いで仕事に出かけた亭主が大金の入った財布を拾うのですが、亭主に酒をやめてちゃんと働いてもらいたい奥さんは、それはあんたが酔っ払って見た夢だ、と嘘をついて騙すでしょう。
中島 それで、亭主は酒を断って真面目に働き始めるんですよね。
たい平 毎日一生懸命働いている勝の姿を見て、奥さんは財布を拾ったのは本当だったと告白して、お酒を付ける。僕が教えてもらった“下げ(オチ)”は「よそう。また夢になるといけねえ」と言って、出された酒に手をつけないでいい男を気取るところで終わる。でも近ごろは、最後の最後、飲んでもいいかなって思うようになったんですよ。だって、飲んであげなかったら、奥さんが救われないじゃないですか。
中島 奥さんのために“下げ”まで変えようと悩むなんて、師匠はやさしいですね。
たい平 飲んだら奥さん喜ぶのに、と思って先輩方に聞いたんです。そうしたら、やっぱり『芝浜』にはあの“下げ”がとても重要だから、それを打ち消すのはどうなんだろうって言われて。だから「よそう。また夢になるといけねえ」と笑いながら、さぁこれから飲むよっていうしぐさをするところでやめることにしたんです。飲んだかどうかは、お客さんに委ねるという。落語は伝承芸なので、あのせりふが言いたくてこの噺をやりたいという人もいるだろうし、あの“下げ”が聞きたくて足を運んでくれているお客さんも絶対いるはずですしね。
落語界全体で次の世代を支える
中島 師匠は、爆笑王と呼ばれた初代林家三平師匠の孫弟子でいらっしゃいますよね。『芝浜』のような古典は、林家一門の落語とはちょっとイメージが違う気がします。やろうと思われたのにはなにかきっかけがあったんですか。
たい平 そう思われるでしょうね(笑)。僕だって林家こん平の弟子なんだから、生涯古典はしないだろう、爆笑路線を進むんだろうと思っていました。ところが立川談志師匠の『芝浜』を聞いて、こんなに鬼気迫る落語があるんだと胸が震えたんです。そこから、僕も『芝浜』をやりたいと思うようになったんです。
中島 私のおぼろげな記憶をたどっても、こん平師匠や三平師匠がじっくり古典を聞かせていた印象はありませんもの。
たい平 だから『芝浜』は、談志師匠のお弟子さんの立川談春兄さんに稽古をつけてもらいました。
中島 林家一門のお弟子さんなのに、立川一門の方に稽古をつけてもらえるんですね。
たい平 はい。これが本当に落語界の素晴らしいところで、どんな師匠でもお願いに上がると、たいがい稽古してくださいます。
中島 下世話な質問で申し訳ないのですが、他の一門に習いに行くときのお月謝とかは……。
たい平 基本、無償ですね。心ばかりの菓子折りを持ってお願いに行く。お金がないから大したものじゃないんですが、断られることはほとんどないです。その先輩もそのまた先輩から稽古をつけてもらっているでしょう。だから自分のところに稽古をつけてもらいたいと後輩がやってくるのは、すごく嬉しいことなんですね。
中島 順繰りなんですね。落語界全体で次の世代を支えている。いいなぁ。
たい平 稽古のあとには、じゃ一杯飲みに行くかと誘ってくれて、二軒ぐらいはしごをして、帰りに電車賃までくださって。頑張れよと背中を押してくれるんです。
中島 先ほど、『芝浜』でも今の人にわかるよう内容を変えることがあるとおっしゃいましたが、古典と呼ばれるお噺を変えちゃっても叱られないんですか。

中島 師匠たちの努力があって、そのお噺が今の時代のものになって、また未来へとつながっていくんですね。ご著書を拝読していると、談志師匠や志ん朝師匠(三代目古今亭志ん朝)など、一時代を築いたきら星のごとき先輩方とのエピソードがたくさん。
たい平 本当にいい時代に落語家になったなと思います。五代目の小さん師匠(柳家小さん)や志ん朝師匠には、旅公演にたくさん連れて行ってもらいました。
中島 うらやましいけれど、緊張しそう。
たい平 そりゃあ、緊張しますよ。名古屋から帰ってくる新幹線で、談志師匠の隣の席にお弟子さんが座ってらしたんですけど、やっぱり師匠の隣は緊張するからと違う席に移ったんです。僕は談志師匠の後ろの席だったんですが、師匠が座席のリクライニングを倒して、狭いすき間からこちらを覗き込んで、今の落語界はどうだい、と話しかけてきてくださった。「師匠、隣に行っていいですか」って言ったら、すごく喜んでくれた。お弟子さんにとっては神様みたいな人ですから、談志師匠の隣にすすんで座りたがる人はいなかったんでしょうね。
中島 少し怖いような気もしますが、宝物のような時間ですね。
たい平 養老孟司さんの『バカの壁』という本がベストセラーになっていた頃で、(談志師匠の口真似で)「あの『バカの壁』っていうのを、おまえ読んだかい」「はい、読みました」「『バカの壁』っていうのには、何が書いてあるんだい」「バカにはわからないことが書いてありました」「いいねー」
中島 うわあ。生で聞けた。談志師匠が目の前に蘇ってらしたみたい。感激です。
中途半端にだけは売れるんじゃないよ
中島 師匠は大学を卒業後、落語家になろうと決意して、林家こん平師匠に弟子入りされたんですよね。
たい平 落語の世界で弟子と師匠の関係ってなんだろうと考えたときに、どこの師匠でもお願いすれば稽古をつけてくれる。だから、稽古をつけてもらうために弟子入りするんじゃなくて、芸人としての処世術や人間としての生き方を一番近くで見せてもらって学ばせてもらうのが弟子と師匠だと思ったんです。うちのこん平師匠は本当にガハーッと大きな声を出して、ダダダダーッとやるので迫力がすごい。とにかく笑わせたいという気持ちが、いつも前面に出ている方でした。師匠は新潟の出身で、ふるさとを大事にされていた。僕は秩父の出身。同じような田舎者でしたから、師匠のそういう気持ちも大好きでした。
中島 そこにいらっしゃるだけで、思わず笑えてくるというような素敵な方ですね。
たい平 その源流には、やはり初代林家三平師匠がいる。三平師匠から流れている、人を楽しませたい、笑わせたいという林家の空気の中に自分もいたいというふうに思ったんです。
中島 大学を出たあと、弟子入りをしたいと申し込んだら、海老名家(林家三平師匠の家)に入ってくれと言われたとか。
たい平 言われたんじゃないんです。住まわせていただいた。そこ大切です(笑)。

たい平 言葉は難しいです(笑)。
中島 住み込みで修業されたのは……。
たい平 六年半ほどですね。
中島 たい平師匠は、私と同い年ですが、当時住み込みで弟子入りする人は、もうそんなにいなかったんじゃないですか。
たい平 他の師匠のところにも何人かはいたようですが、六年半も住み込んだ人はいないと思います。長くいたから、そのまま落語になりそうな事件もたくさんありました。先輩と一緒に、朝ご飯を食べてたら、ものすごい糸を引く。前の日の納豆が茶碗に付いてるのか、箸に付いてるのかと思って、先輩に「これ何ですか」って聞いたら、「すえてんだよ」。「すえてるって何ですか?」「腐ってんだよ」(笑)。
中島 そんなの食べたら、お腹をこわしちゃう。
たい平 そうでしょう。でも捨てようとしたら、先輩に怒られて。師匠のうちに住まわせてもらって、ご飯まで食べさせてもらってんだから、全部食べなさい、と。我慢して食べました。
中島 わあ、大変そう。
たい平 一番つらかったのは、自分の自由な時間がないことですね。住み込みじゃない前座さんたちは、寄席が終わるとみんなで飲みに行ったりするんです。僕は師匠の家に戻らないといけない。映画やコンサートに行く時間も一切なく、一番多感な時期に何も新しいものが見られない。それが一番不安でした。
中島 若いときにそれは、なかなかしんどいですね。
たい平 掃除、洗濯、お使い。一年目は行儀見習いですから寄席にも行けない。一日中師匠の家で何か用事を探している。庭に枯山水のようなところがあって、そこの石を毎日バケツに百個ずつ入れてきれいに磨いてみようとか。時間だけはたっぷりありましたから。
中島 なんだか本物の禅僧の修行のような感じ(笑)。
たい平 そうですね。海老名家の屋上には、畑があったんです。おかみさんから「あんた田舎出身だから、野菜くらい作れるでしょう」と言われて(笑)。寂しくなると畑に上がって、土をいじりながら泣いてました。僕が畑から降りてこないと、おかみさんが屋上に上がってきて「修業の前座さんをいっぱい見てきたけど、あんたは絶対頑張れるから頑張りなさい、辛抱しなさい」と励ましてくれました。おかみさんは、ちゃんとわかっていたんですね。よく、おかみさんの胸で泣いてました。後になって、そのことを黒柳徹子さんに話したら、「あなた、おかみさんに抱かれたんですって」(笑)。
中島 ほんと、言葉は難しい(笑)。
たい平 落語家になりたいという夢があったから、最小単位のお客さまが、海老名のおかみさんのご家族だと考えたんです。常にこの子がいるとお家が楽しいと思ってくれれば、ずっとそこにいられるわけですよね。この家族も楽しませられない人に、三百人、五百人のお客さまは楽しませられない。それが僕の落語家としての原点かもしれません。
中島 お願いしても、できないような体験ばかりですね。

中島 かっこいい。ダンディな志ん朝師匠の姿が浮かんで来ます。
たい平 いろんなエンターテインメントが自由に選べる時代です。スターが出ないと落語の世界全体が上にあがっていかない。そのひとりが志ん朝師匠でした。自分だけが食えるような芸人で止まったら駄目だ。この世界のみんなが食えるようなスターになりなさいよということなんだろうなと理解しました。志ん朝師匠にいただいたその言葉を胸に刻み込んで、今も必死で落語と向き合っています。
中島 たい平師匠たちの頑張りもあって、寄席に足を運ぶ人がどんどん増えていると聞きました。お客さんは、何を求めて落語を聞きにいらっしゃるんでしょう。
たい平 たとえば、スマートフォンができてから、人と人の付き合いが濃くなったという人もいます。でも現実は、面と向かってバカ話をしたり、けんかをしたりというリアルの体験が少なくなって、逆に人間関係が薄っぺらになっていると思うんです。みんなで幸せになろうと思って日本中の人たちが走ってきた。ところが気がついたらみんな、あれ、ポケットに入れてた大切なものを、どっかで落としちゃったのかなという感じなんじゃないか。中島さんがいつも小説の中で書いていらっしゃる、生きていく中での大切なもの、それが落語の中にもあるようにお客さまは感じてくださっているんだと思います。落語を聞いて感じるほんの小さな幸せが、人間として一番の幸せかもしれない、と思ってもらえると嬉しいですね。聞き終わった後に、誰も傷つけないで、みんなが幸せになって帰れるような落語がやっぱり自分の中の理想なんです。
中島 インターネットだ、AIだと世の中どんどん便利になっていると言いながら、実は人間の本質的な営みじゃないところで、毎日振り回されている気がしている人も多いと思うんです。たい平師匠のお話を伺っていて、なんだかぎすぎすした世の中だからこそ、みんなにもっと落語を聞いてもらい、落語国の住民になってほしいなと思いました。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、翌年、日本医療小説大賞を受賞。最新刊は『夢見る帝国図書館』。
林家たい平(はやしや・たいへい)
本名、田鹿明。1964年埼玉県秩父市生まれ。落語協会所属。87年、武蔵野美術大学造形学部卒業後、林家こん平に入門。92年、二ツ目昇進。2000年に真打昇進。出囃子は「ぎっちょ」、紋は「花菱」。04年から、日本テレビ『笑点』の大喜利メンバーに。NHK新人演芸コンクール優秀賞をはじめ、第58回芸術選奨文部科学大臣新人賞ほか受賞多数。2014年から落語協会理事に就任している。著書に『たいのおすそ分け ちょっと、いい噺』、『林家たい平の お父さん、がんばって!』ほか多数。
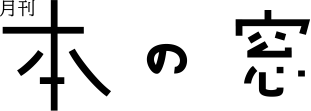
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2019/05/20)






