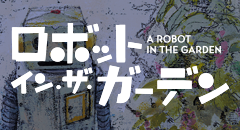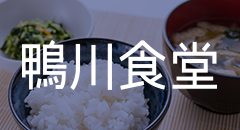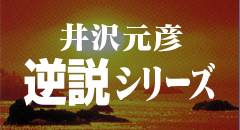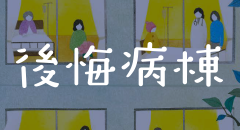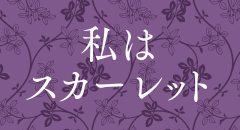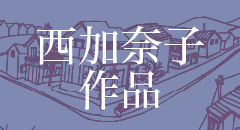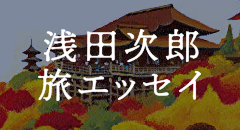許し、許されることの意味を教えてくれる
名作『氷点』の、朝日新聞一千万円懸賞小説入選から五十年を記念して編まれたエッセイ集の文庫化。第一章には、応募にいたる経緯や、新聞連載中の読者からの反響、自身が行った講演の模様など、『氷…
人は人を真に愛することができるのか——。
高校教師の南慎一郎は、妻子がありながら、同僚である藤島の妻・美枝子に心惹かれている。美術教師の藤島から手ほどきを受け、美枝子をモデルに描いた絵が日展初出品にもかかわらず協会賞を受賞。同…
神を愛し、ひたすら人を愛した男の軌跡。
人のため、伝道のためにその身を尽くした西村久蔵。神に愛され、神を愛し、そして人をひたすら愛したその生涯を、自らも久蔵の大きな愛に導かれた三浦綾子が辿った感動の伝記小説。 明治三十一…
愛と信仰を描いた作家による珠玉のエッセイ
家族や親しい人たち、尊敬する師や元の教え子について。生涯暮らした旭川のこと。身の回りのことを書きながら、いつの間にか著者・三浦綾子の思いは、人間誰持つが持つであろう悩みや至らなさに話が…
知らぬ間に麦畑に紛れ込み、はびこっていく毒麦のように、容赦なく人々の心をむしばんでゆく悪意の種子。その種子を蒔くのは、生まれついて悪しき人々なのか、あるいは無垢と見える我々自身なのか。…
キリスト教徒としての愛と許しのまなざしで、救いがたく弱い人間の生を見据え続けた三浦綾子。何気ない日常の中に垣間見える、底知れぬ闇を抱えた人間の弱さを描き出した作品群は、時を経てもいささ…
今は亡き愛の作家が遺した感動の言葉
一九九九年十月、五十余年にわたる闘病生活の末に逝った三浦綾子。死の床で「私はまだ、死ぬという大切な仕事がある」という言葉を遺して。 言葉──人と関わりあうための重要な手段。そこに、伝え…
自己中心に生きがちな現代人へ「夫婦・親子」の真のあり方。
夫婦や親子の愛のあり方、あるいは真実に生きることの大切さを、著者に届いた手紙に対する返信の形をとりながら読者に語りかける三浦綾子のエッセイ集。誰もが自己中心に生きていきがちな病める現代…
初代女子学院院長を務めた矢嶋楫子の波乱万丈の生涯。
"厳しい明治の世、熊本の旧家に生まれた矢嶋かつは、酒乱の夫に再三生命の危機にさらされ、自分から離縁を言い渡す。当時の風潮に反するかつの行いに世間も身内も冷たく、三人の子を置いて単身東京…
不遇な少女の洗礼までを語る三浦文学の名作
北海道・旭川。浜野清美は母子家庭に育った。いじめにあい、大人への不信も募るなか、友達の事故死を目撃したのを黙っていたことや、母の愛人から弄ばれたことなどから清美は暗く無口な子となってゆ…
激動の時代を描く三浦綾子の最新長編小説
昭和16年、思いもよらぬ治安維持法違反の容疑で竜太は、7か月の独房生活を送る。絶望の淵から立ち直った竜太に、芳子との結婚の直前、召集の赤紙が届く。入隊、そして20年8月15日、満州から…
人間の本質に迫る三浦文学の最高傑作
昭和元年、北森竜太は、北海道旭川の小学4年生。父親が病気のため納豆売りをする転校生中原芳子に対する担任坂部先生の温かい言葉に心打たれ、竜太は、教師になることを決意する。竜太の家は祖父の…