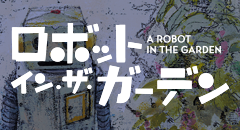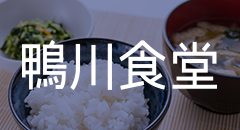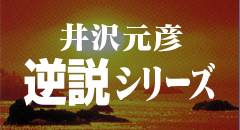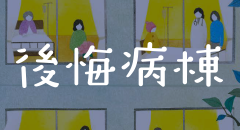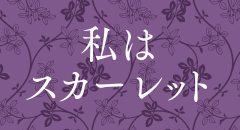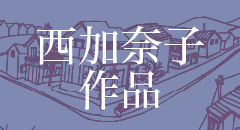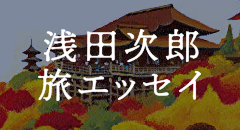マンガで読む。巨匠で読む『徒然草』
「つれづれなるままに、ひぐらし硯にむかひて」という序文で始まる兼好法師の書いた有名な随筆『徒然草』。平安時代の『枕草子』と並び、古典随筆の代表としてとりあげられている。 実際、兼好…
マンガで読む。巨匠で読む「竹取物語」
誰もがストーリーを知る、日本最古の物語と伝えられる『竹取物語』。『源氏物語』にも「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」と記されている。成立年・作者ともに不詳。原本は存在せず、現…
マンガで読む。巨匠で読む。「源氏物語」
紫式部が『源氏物語』を書いた平安時代中期、ヨーロッパはまだ、一部の歴史家に「暗黒時代(ダークエイジ)」と呼ばれるような時代でした。文章だって幼稚なものしか書けなかった。 そんな時代に…
マンガで読む。巨匠で読む。「源氏物語」
紫式部が『源氏物語』を書いた平安時代中期、ヨーロッパはまだ、一部の歴史家に「暗黒時代(ダークエイジ)」と呼ばれるような時代でした。文章だって幼稚なものしか書けなかった。 そんな時代に…
マンガで読む。巨匠で読む「古事記」
現代では「古事記」を「こじき」と読むのが一般的ですが、本書では「やまとことば」の「ふることふみ」と読んでいただきたいと思いました。日本には民族の言語として「やまとことば」がありました。…
マンガで読む,巨匠で読む「方丈記」
日本三随筆のひとつで中世の天変地異ドキュメント『方丈記』を活写! 平家興亡・源平争乱の平安時代末期を生きた無常の歌人・鴨長明の生涯を交えながら完全にコミック化! 名門・下鴨神社禰宜の子…
マンガで読む,巨匠で読む「源氏物語」
紫式部が『源氏物語』を書いた平安時代中期、ヨーロッパはまだ、一部の歴史家に「暗黒時代(ダークエイジ)」と呼ばれるような時代でした。文章だって幼稚なものしか書けなかった。 そんな時代に…
マンガで読む、巨匠で読む「古事記」
現代では「古事記」を「こじき」と読むのが一般的ですが、本書では「やまとことば」の「ふることふみ」と読んでいただきたいと思いました。日本には民族の言語として「やまとことば」がありました。…